朝起きると雨… 午前中はフライブルクを傘をさしつつ歩く。写真が取り辛い。でも、静かな中世の佇まいを楽しむには、雨の日曜日は悪く無い。雨の匂いと、多少湿って聞こえる鐘の音が雰囲気を醸し出す。 街のすぐ裏手に黒い森が迫っており、折りからの霧雨で大変神秘がかって見える。これでは、まちづくりにも自然への畏怖が入って来るのも当然である。さすがに「ドイツの環境首都」と言われるだけあって、自然と人工のバランスが素晴らしい。 また、単に古いものだけで無く、新しい建物や路面電車などもうまく組み合わせているののに感心。随分異なる地方都市ならではのまちづくりである。
昼前から天気も良くなり、いざ長距離ドライブ。しかし、いきなり事故があって渋滞中。おまけに途中から本格的な雨に。それも中途半端では無い叩き付け方である。スピードも80kmまでしか出せず、予想外に時間がかかってしまう。道程は長いのに。 やむを得ず、ボン、ケルンなどに途中で立ち寄る計画は中止し、ひたすら宿泊地デュッセルドルフを目指す。景色はもやがかかっていてはっきりせず、ラジオをつけなければ睡魔に襲われそうである。結局、到着は6時。一日中(実際は6時間)車に乗っていた冴えない日だった。
ここでは知人のツテなどで某日系ホテルに滞在。フランクフルト同様に分不相応な料金だけあって、至れり尽くせりである。サウナとプールで筋肉をほぐし、ビールで体を癒す。本格的な「出張」ならば、こういうホテルに泊まって仕事の効率を上げたいところである。 あと2日、最後の視察頑張ろう。
98年6月8日:地道なまちづくり
いつもすごくきめ細かくメールをくれたヒピンさんと、ホテルのロビーで待ち合わせる。日本に留学したことがある彼は、中身は繊細でも外見は普通にごついドイツ人であった。外見と中身は必ずしも一致しない。今日と明日は一日中、彼の案内&私の運転でルール産業地帯のまちづくりのプロジェクトを回る。中学校の地理で「ドイツ最大の重工業地帯」と習い、今では「環境型まちづくりの成功」で有名なこの地域、両者のギャップの実際に興味津々。
まずはIBAのオフィスでトーマスさんの全体説明。いきなり、「僕が作ったんだ!」という御自慢のケーキをごちそうになり、それから事前に送った質問事項に合わせた「痒いところに手が届く」解説を聞く。なるほど、政治がややこしいのは世界中どこも似ている。 近くの研究所を見学した後、ヒピンさん御推薦のトルコ料理屋でランチ。地元民しか来ない「街の食堂」である。トルコ移民が多いためだろうが、これが美味しい! ヒピンさんは味に結構こだわるようで、「ドイツの軽食は最悪」「外食は下手したら日本より高い」「旨いものは南ドイツにある」など熱く語る。漠然と感じていたことを、ドイツ人の口から聞いてしまった感じ。でも、ビールの旨さとサッカーは御自慢。「ドイツは結構行けそうじゃない?」と言うと、「でも、優勝は出来ないよ」と言われる。日本とは目指す次元が違う。
午後は住宅プロジェクトを回る。かつての鉱山労働者向けの住宅を、一つずつ修繕して住民が住み続けられるように努力しているのは素晴らしい。福祉生活者が自分達の手で造った住宅も、素人っぽい仕上がりが却って愛着を感じさせる。工業製品である日本の住宅メーカーの住宅とは全く違う。 しかし、人が住んでいる家の周囲をごそごそと見学するのは気が引ける。私には勉強でも、彼等にはプライバシーの侵犯になりかねない。ごめんなさい。でも、団体視察者を大型バスで案内することもあるという。南米の低所得者向け住宅地なら、襲われかねない…
このエリアは衰退しているとは言え、今でも重工業は盛んで、あちこちに巨大な工場や鉱業施設がある。これらがこんもりした木々に囲まれて意外と目立たないのは不思議な感じ。東京でもポートランドでも、巨大工場/操業所は水際にあるものばかり見て来たので、「森の中の工場」というのは違和感がある。でも、これらの木々は勝手に生えたものばかり。逞しい自然の力である。 よく見ると、閉山になったボタ山や精製施設なども結構ある。これらは今では単なる廃虚である。土壌の汚染も深刻だし、問題の根は深い。ペンシルバニアのワークショップをふと思い出す。 しかし、どこを走っても「工鉱業のまち」という表情ばかり。炭坑労働者の住宅、戦後の箱型量産住宅、どこか埃っぽい空気、目につく無職の人々など、ベルリンとは異質の「泥臭い重さ」がある。まちづくりのしがいがものすごくありそうな、悪く言えば問題山積の地域である。ローテンブルクのメルヘンも、フランクフルトの機能性も、パリの華やかさも無い。勿論、観光客など全くいない。 さらに車の中で、東欧やトルコなどからの移民問題、そして表には出難い外国人差別の話をヒピンさんから聞かされる。まちづくりって地道な作業だなあ、と改めて思う。
ホテルに戻ると、そこは日本。ツアーの年輩夫婦がロビーに溢れ、ちょっとビビル。隣には日本の本屋まであり、日本食屋もいっぱい。うーん… ぶらぶらしていると、ホテル内の床屋で剃刀でヒゲを剃っているのを発見!あの快感が日本以外でも味わえるとは!と感動する。これは日本価格でも良いや、と思って入ると今日は閉店だそうでがっかり。明日の夕方に時間取れるだろうか?
98年6月9日:視察実質終了
今日もヒピンさんの一日ガイド。まずは、住民が企画段階から参加してつくった住宅地区へ行き、担当のプランナーに解説&案内してもらう。「以前からの住民が住み続けられるように」という大きなコンセプトから、設計や工事の細部にいたるまで総合的に考えられているのが凄い。担当プランナーを住民が指名して選んだ、というのもボトムアップが徹底している。彼女も選ばれたことが誇りのようだ。相思相愛。
ランチはまたもトルコ風サンドイッチ。地元民のたまり場である。店のおじさんは、毎日毎日ラム肉をいぶり続けて数十年というような年輪を感じさせる顔。こういう人生を送った人には幸せに暮らして欲しいなあ、と思う。
午後、デュイスブルクにある廃止された製鉄所を利用した公園へ。初めて溶鉱炉のてっぺんまで上ると、ちょっと足がすくむ。高いところからは、高速道路からは見えなかった、煙突や工場が野生の木々の中から生えているのがよくわかる。排ガスもひどい。さすがにイメージ最悪の重工業地帯である。 公園の中は時間が止まった世界。放置された操業施設が物悲しい。でも、再利用されたイベント会場、劇場、レクリエーション施設などは、非常に面白い。リハーサル中の劇団、社会科見学の子供達など、若い人が生き生きとしている。一方、年配者の集団も。案内してくれた施設マネージャー曰く、「ここは以前は労働者以外は家族すら入れなかったんだ。ああいうおじいさんは、家族を連れて来て、『俺はここで30年も働いたんだ』と自慢するんだよ。」なるほど、廃虚は労働者の誇りでいっぱいなんだ。ジンとしてしまう。 施設運営の資金繰りは非常に苦しいそうだが、できるだけ長く使い続けて欲しいものだ。「ビアホールとかやると儲かりそう」と言うと、「僕はミュンヘンの大学に行ったけど、ここはミュンヘンとは別世界なんだよ」とのこと。確かに同じ国とは思えない違いである。光と陰。 最後に運河沿いの複合再開発へ。倉庫を再利用したオフィスや住宅などはハイクラス。排ガス、廃虚、低所得者住宅などばかり見続けて来たので、少し明るい気分になれて良かった。
ホテルへ戻り床屋へ。自分への御褒美である。ヒゲを剃られ、頭や顔をマッサージされると、思わず声が出てしまったほど気持ち良い。日本の床屋(美容院では無い)は最高である。一方、アメリカの床屋は最悪だと思っていたが、理髪師さんによればドイツも似たり寄ったりらしい。 リフレッシュ完了で一路フランクフルトへドライブ。空港、そしてホテルが見えると、懐かしい気分になる。2000kmのドライブは無事終了。そして、視察も実質終了(イタリアは半分気楽な訪問である)。一気に乗り切った感じ。さあ、明日からイタリアでワインと美味しいもの三昧だ! あと、ワールドカップも!
 メールはこちらへ
メールはこちらへ
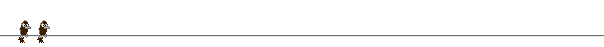
このページは![]()
の提供です。
無料のページがもらえます。