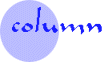
ミュージック ビジュアル プロット コントローラー 世界観
*** ミュージック ***★音源***ビジュアル***ナイトピアでは内蔵音源、ナイトメアでは録音されたCD-DAの仕様となっています。★ナイトピアの音楽についてNiGHTSではユニークな形で内蔵音源を使用しています。
このゲームにはAI(人工知能)の延長線上にあたるA-LIFEシステムを導入しています。これはナイトピアの住人、ナイトピアンを育成するものです。ゲーム中でのナイツの行動でピアンの感情や生態系が変化してくというものです。そしてピアン達の感情によってゲーム中の音楽に変化が現れる仕組みになっています。曲は4〜6くらいの小節に区切られて、各小節がピアン感情に合わせ4つのパターンがあります。そして、それらが組み合わさって1曲のBGMが形成されている訳です。メディアがCD-ROMが主流になってからというもの、ハードに搭載された音源に左右される事がなくなってきたように思います。実際、ゲーム機の音源よりもそれらの演奏を録音したのを流した方がクオリティが高いでしょうし、わざわざ劣化させてまで内蔵音源にこだわる必要性は感じません。敢えて内蔵音源を使用するのは、多くの曲数を扱う為にCD-DAでは入り切らない場合、容量が少なくて済む内蔵音源を使用すると言った感じで容量の関係上くらいでしょうか?
そういった背景からも、このシステムはただA-LIFEの存在意義の1つだけではなく、CD-DAではそう簡単には出来ない内蔵音源ならではの事の様に思います。
NiGHTSの音楽は単品でも聴くに耐え得るクオリティを持っています。そして、もしもゲームをプレイせずに曲だけでも聴いてみるならば、ゲームらしくない曲と思われるのではないでしょうか?NiGHTSはゲームよりも映画に近い音楽だと思います。この事自体はファイナルファンタジー、ポリスノーツと多くのゲームにも当てはまる事で珍しくは無いでしょう。ただNiGHTSはRPGやアドベンチャーではなくアクションゲームです。そして、オープニングとエンディングにムービーがありますが、音声による台詞はおろかテキストの表示などは一切無くそのアクションだけでストーリーを語っています。
それだけにNiGHTSは各ドリームのイメージとテーマにしかっりと沿った曲作りがなされています。NiGHTSの音楽はあまりアクションゲームという雰囲気を持っていません。しかしながらNiGHTSほどゲーム内容と音楽がしっかりと噛合っていると言えるゲームはなかなかないでしょう。
***プロット***NiGHTSは3D的な2Dアクションです。このゲームを初めて雑誌で見た時はどのようにして快適に飛びまわれるのか非常に興味深かったのを覚えています。
蓋を開けてしまえば実に明解で、今までの2Dゲームとゲーム性自体はなにも変化はしていませんでした。この事で同時期にリリースされたスーパーマリオ64みたいなゲーム性に期待していた人には拍子抜けしてしまったかも知れません。3Dには3Dであるといった既成概念があるせいかもしれませんね。
しかしながら、このスタイルはNiGHTS以前にもありました。ジャンルは違いましたがセガのポリゴンゲームを代表するゲームにバーチャファイターにも同じ事が言えました。これも同じように視覚的には3Dではありますがゲーム的には2Dでも可能です(ゲームバランスは大きく変わりそうですが…)。ポリゴン3Dでの演出は2Dのスプライトに比べ非常に視覚的な効果は抜群と言えますが、同時に2Dから3Dへの操作性は複雑化されてしまうハンディキャップを負います。レースゲームであるならばコクピット視点で描かれ、操作系統も決して難しくはないでしょう。これがシューティングゲームになると格段と操作が複雑化されとっつきは決していいとはいいません。今でもシューティングゲームは2D物の方が圧倒的に多いのはこのせいではないとかと思います。
これが乗り物ではなく人間になればより複雑になってしまうのは自明の理かも知れません。セガはバーチャファイターをはじめ、ポリゴンならではのダイナミックな演出、そしてプレイ自体は3Dだから3Dにと言った概念に捕らわれる事なくそれらを上手く消化しています。余談ながらバーチャロンは操作自体も3D空間を意識したものの既存の3Dロボット物では最も簡単な操作であったように思います。(1vs1だったせいもあるでしょうが)
NiGHTSはメガドライブのソニックの要素を押し進め、リプレイ画面には及ばないもののそれをプレイヤーに見事なカメラアングルで魅せる3D的な2Dゲームとして仕立て挙げた事はある意味、純粋なセガゲームの進化形と言えるでしょう。それにこういった大胆なカメラワークは主にプレイヤー視点で描かれるゲームでは難しく、ポリゴンの2Dゲームだからこそ可能だとも言える訳です。
あと、敢えて3D的な2Dゲームと2Dゲームの違いには中氏が雑誌で言っていましたが、天井抜けができない…2Dならではの『嘘』が通用しなくなる事でしょう。逆にナムコの風のクロノアみたく基本は2Dのアクションでありながらポリゴン空間ならではの奥行きのあるアクションができるのも3D的な2Dゲームの特異点かも知れません。これらの面を考えると一概に3D的な2Dゲームであってもそのゲーム性は大きく異なる場合は多々ある事でしょう。
★ツインシーズへの見事な伏線***コントローラー***
NiGHTSはゲームの中では台詞もなければテキストもありません、しかしながらTVゲームの中でもトップクラスのシナリオであったと評価すべきでしょう。ムービーの演出が素晴らしくそちらに目がいってしまいそうですが、最も優れていたのは効果的な伏線ではないでしょうか?
テキストがなく具体的なストーリーが無いのに関わらず伏線があるのか?と思われるかも知れませんが、NiGHTSは実に優れた伏線で多くのプレイヤーに感動を与えました。クラリスとエリオットが空飛ぶツインシーズ序盤での演出です。この演出は3つのドリームをクリアして辿り着いたからこそ得られる感動ではないでしょうか?
3つのドリームではエリオットとクラリスはナイツなしでは空を飛ぶ事はできません、恐らくタイムオーバーしてしまいナイツとのデュアライズが解けてしまった場合は、ナイトオーバーとなってしまうアラームエッグを避けつつ、いち早くナイツの居るイデアパレスに向おうとするのではないでしょうか?それだけデュアライズしていない二人は無力であることをプレイヤーは認識しています。
そして、ただクリアするだけではありません。最低でも各ドリームをCランク以上でなければツインシーズには行けないのです。普通のゲームであったなら、クリアするだけで進めれるものですが、NiGHTSはしっかりとした意図を持って敢えてこういったハードルを用意しているのです。プレイ当初は点の稼ぎ方のコツが判らずなかなかCランクには達しないのではないでしょうか?何度も挑戦してようやくツインシーズにたどり着ける訳です。先述した事をプレイヤーに強く印象付けてこそツインシーズでの演出が輝くように思います。
そういった訳で伏線には色々なタイプがあります。イースやスナッチャーみたいなストーリー全体の構成を重視しあらゆる所に伏線をちりばめるタイプではなく、NiGHTSは演出をより強いインパクトを与える為の伏線だと言えます。
代表的な所でマジンガーZがグレートマジンガーに主役交代するタイプに相当します。最近であれば勇者王ガオガイガーのゴルディオンハンマーやキングジェイダー登場の時でしょうか?
漫画ならドラゴンボール、ゲームでならばサクラ大戦での中盤での展開や同2での序盤もこれに相当するといえます。要は敵味方問わず、新キャラは如何に強いかを示す演出ですね。これはほとんどパターン化されてしまったきらいがあります。NiGHTSはゲームならではの伏線を張ったと言えるのではないでしょうか?プレイヤーにデュアライズ前の飛べない二人の無力さを頭に植え付けさせた上での演出だったと言えるでしょう。
こういった演出はなかなかあるものではありません。例えるならば、もしスペランカーの主人公が高い所から落ちても平気だったら凄い事だとは思いませんか?スペランカーの主人公の貧弱さは折り紙付きです、それを覆してしまうような演出だと言えるでしょう。
★マルコン***世界観***当時、NiGHTSに併せて同時発売されたコントローラーがあります。それが以前の、コントローラーにアナログキーを新たに追加し、LRボタンもアナログ対応にしたマルチコントローラー(通称マルコン)です。
今でこそ、アナログキーは標準とも言えるデバイスですが、当時マルコンは形状が丸い特異なデザインと斬新なコンセプトを持ったコントローラーであったと言えるでしょう。
NiGHTS発売の直前に発売された、NINTENDO64で既にアナログキーを標準に取り入れています。セガや任天堂は同様にドットの概念でなくなった3Dポリゴンのゲームを最大限に活かす為に開発したものであると思います。両社が同時期に同じコンセプトのコントローラーをリリースしたのは実に印象的でもあり、ここから本格的に家庭用TVゲームに3Dポリゴンの時代が来たようにも思えます。NiGHTSはスーパーマリオ64と違い、実際には2Dと同じゲーム性であり、ゲームをクリアするだけならばアナログの必要性はないのです。しかしながら、このゲームをプレイする事に於いてアナログデバイスは大変重要です。
このNiGHTSでは他のゲームと大きく趣が違う面があります。ゲームのプレイ目的は多々あります。より高いスコアを狙う、最短でクリアする…等など、腕の上達を目的とした事がリピートプレイの一般的なゲーム目的でないかと思います。
NiGHTSでは、ただ単純に『空を飛ぶ』それだけでも立派なプレイ目的になりますNiGHTSに限らなくともそういったコンセプトのゲームは、同社のアウトラン(*1)などがあります。でも、多くはありません。それだけにこういったコンセプトを理解してもらうにはなかなか難しいものの様に思いまが、それを受け入れられた人ならよりゲームを楽しめるのではないかとと思います。
そして、その『空を飛ぶ』事を快適にそして、ダイレクトに感じさせる事が出来る事を可能にしたのがこのマルコンなのです。NiGHTSはゲームを楽しむ方法に於いて、忘れてかけていた事を再認識させてくれました。
また、アナログコントローラーはただ精度の高い操作を要求するものではない事も教えてくれたように思います。
*1
アウトランは当時、ドライブゲームでは実にセンセーショナルなゲームでした。それまでのドライブゲームと言えばレース物が主流でしたがその中で、鮮やかなヨーロッパの背景と軽やかなBGMはそれまでのイメージを覆し、そして順位を競わないそのコンセプトは斬新でした。
何より、タイムを競う感覚よりもドライブを楽しむ事にウェイトを置いた着眼点はNiGHTSにも通じるように思います。
NiGHTSは2つの世界が舞台となります。エリオットやクラリスが暮らす、現実の世界。そして、ナイツやピアンが住む、夢の世界です。★ツインシーズこのゲームは現代よりも少し未来という時代設定になっています。街は美しく、公害や犯罪の匂いのしない雰囲気で、まさに理想の街を描いた世界だと言えるでしょう。★ナイトピア・ナイトメア
多くの作品での未来は退廃的なモノばかりのように思います。それが現実的でもあり、メッセージ性及び作品性のあるものだと受け止めがちなのかも知れません。
確かに現状を考えれば実際の未来は明るくはないでしょう。それを危惧し作品の中で示唆する事は良い事だと思います。
では、NiGHTSにはそれがないと言えるのでしょうか?答えは"NO"です。この舞台にした事には単に子供向けと言うものではなく、強いメッセージ性が秘められているようにも思えます。簡単に悲観的な世界を描く事でそれを示すよりも、明るい未来を描く事で現状をより再認識させてくれるように思うのです。
また、相手に言われ考えるのではなく、自ら考えてみようとする気持ちが大事ではないでしょうか?多くの作品では考えさせるようなテーマを相手に伝えますが、NiGHTSでは表面的には皮肉もテーマもなく訴えるものはないように感じるでしょう。しかしながら、その見えにくい所にあるメッセージは、考えさせるきっかけを与えているのようにも思います。NiGHTSにそれだけのモノがあるのかどうかは判りません。
ただ確実に言える事は、真実ほど霧の向こうにあり見えにくいモノはないと言う事です。
NiGHTSはそれを霧で見えない道を少しだけ照らす手助けをしてくれているように思うのです。台詞がないNiGHTSではその世界観もストーリーを語る重要な要素だと言えそうです。
このナイトピアは2人の主人公である、エリオットとクラリスの内面的な意識が反映させて形成された夢の世界というユニークな設定です。(またナイトメアは悪夢という設定になっています。)***クラリス***
理想(スプリングバレー)
可能性(ミスティックフォレスト)
混乱(ソフトミュージアム)***エリオット***
愛情(スプラッシュガーデン)
自覚(フローズンベル)
再生(スティックキャニオン)…と各ドリーム毎にテーマを分けそれをモチーフに形成されている訳です。
実際、これらはかなり抽象的であり、それらのテーマを意識してゲームをプレイしても明確にこれらのテーマはなかなか見えてきません。ただ美しく不思議な舞台にも思えます。しかしながら、例えそれが製作者の意図したものでなくても、どこかしろに何かが見えたならば、それは大きな収穫でしょう。一人ひとりが各々の受け止め方をすればそれでいいのです。
