![]()
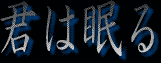 聖
聖
あいつと始めて会ったのは十歳の春だった。
風が強い日だった。その為に、美しく花開いていた庭の桜の花びらが舞い狂い、渦を巻き、空へと舞い上がって、雪のように地上へと舞い下りていた。
そして、あいつはそんな状態の庭にひとり、佇んでいた。
長い髪が風に乱され、なびいていた。その髪の色は、薄い紅。あたかも、桜の実の汁を白い衣の上に薄く刷毛で塗ったような、そんな色だった。
そのような紅い髪を持つ人間は、同じ八神家の人間。それも本家により近く、濃い血を受け継ぐ人間。だという事を示していた。
けれども、それでもなお、その幻想的な光景はあいつを、まるで人ではないかのように見せていた。
あいつの、その庭に佇んでいた少女の名は霞、八神霞と言った。俺の三つ年下の従姉妹であり、そして一族が決めた俺の婚約者だった。
あの頃はまだ、俺も、霞も、まだ普通といえる生活を送っていた。
八神の血と宿命、歴史の重さも、おぼろげには理解していても、まだ所詮おぼろげに過ぎなかった。何も知らない子供にすぎなかったのだ。
八神の血、何代にもわたって行われてきた血族結婚。
それによって凝縮された八神の血を更に濃く、次代へと伝える為に選ばれた婚約者。俺と霞は希に見るほどに濃い血を受け継いでいた。だからこそ俺達をめあわせたのだろう。
いや…案外、俺達の間に子供が生まれるのは、そう期待はされていなかった、のかもしれない。俺はまだいい、肌も少しは日に焼けるし、色素がまだある程度存在している。しかし、霞は違った。
赤と言うにはあまりにも薄い、薄い紅の髪。血のように紅い瞳。雪のように白い肌。霞はアルビノと言ってもいいほどに色素と言うものが存在しなかった。
そんな霞の身体が丈夫な訳はなく、どちらかと言えば虚弱体質だった。丈夫な子供を産める身体とはとても思えない。
ましてや、八神は代々早死にする家系である。
それも、血が濃ければ濃いほど早く死ぬ。自分もまた、そう長生きはできないであろう事は、一族の者全てが理解していることだった。もしかすると子供は、生まれたらしめたものだというぐらいにしか、考えてはいなかったのかもしれない。血を伝えるだけならばなにも俺でなければならない、という事はないのだから。
まあ、そのような大人達の思惑はともかくとしても、俺と霞の仲は、まあ良かった。
お互いに寂しかったのかもしれない。多少髪が紅いぐらいならばまだいい。しかし俺達の髪と瞳の色は、他の人間達の中に入り込み、混ざり込むには、あまりにも異質すぎた。
たとえ、そのような人間を時折輩出する家系の人間だと知っていようとも、人間が本能的にもっている、自分と違うモノを排除する、という行動を完全に止める事などできやしない。
結果、無視はされないが、それだけだった。仲間になど、入れてはもらえない。腫れ物を触るような扱いを皆、していた。
まだ子供の俺達に、その事が淋しくないわけが無い。俺達の、互いへの距離が次第に狭まっていったのも当然な事なのだろう。また、霞は歳の割に大人びており、俺との歳の差を感じさせる事はなかった。それに、俺達は互いの存在が必要だったのだ。
なぜなら、この八神という家。俺達を包む世界、それは、あまりにも広く、冷たく、また非、人間的だったからだ。
妹はまだ幼く、本来守ってくれるべき親は、家という名の化け物に飲み込まれ、その責務を果たしてはくれなかった。まだ力の無い子供が独りで生きていくには、あまりにも冷たく、暖かみが欠けた環境だったといえる。
だが俺達が互いに与える事のできる微かなぬくもり、それさえあれば生きていく事ができたのだ。互いさえいれば、二人ならば、支えあうことができた。
霞が倒れた。その事を知ったのは、95年に行われたキングオブファイターズの大会が終ってから、暫く経った後の事だった。
俺はあの大会で、草薙を殺すという、八神家当主としての使命。自身の存在理由とでもいうべき事を果たす事ができなかった。
この事実は俺を激しく打ちのめした。俺は草薙を殺す為だけに今まで生きてきて、草薙を殺す、その為だけに、その為に必要な、あらゆる教育を受けてきた。
それなのに殺せなかった。奴を殺す為だけに生きてきたと言っても過言ではなかった。それなのに殺す事ができなかった。殆ど何も考えず、ただ今を刹那的な快楽を追い求めて生きている、ように見える、あの草薙家当主、京に勝つ事、殺す事ができなかった。
血に刻み込まれているのは憎しみ、妬み、光、太陽への羨望。そして、どこか懐かしいとでも言えるような、暖かい想い、感情。それらが入り交じった、複雑で入り組んだ想いを、草薙を見るたびに感じる。
血が沸き立つような歓喜、興奮、憎しみ、その全てが存在する。京を見るだけで全身の血が、細胞が、遺伝子が呟き、叫ぶ。殺せ、と。
血の中の記憶、オロチの血、それが草薙を拒否する。排除しろ、と命令する。あれは敵だと捲し立てる。そしてまた、八尺瓊の血は呟く。「…ナツカシイ……」と。
それは八神として、八尺瓊の名を捨てた八神家としては認めてはならぬ感情。抹殺せねばならぬ感情。けれども、そのふたつは俺の中で入り交じり、狂わせる。
憎しみと懐かしさ、決して相いれぬ感情。それは同時に存在し、俺を…苦しめる。
だから殺す。草薙を殺す。苦しいから。自分の内で荒れ狂うこの感情が苦しくてたまらないから。自分が狂う前に、何も分からなくなる前に、息の根を止める。
こんなにも自分を苦しめる草薙が、憎くてたまらない。憎くて、憎くて、憎くて、…懐かしい。苦しい。
草薙を殺す為に力が足りないのならば力を。速さが足りないのならば速さを。技を、身に付ける。草薙を殺す為ならば、何でもする。その為にこの血、オロチの血に狂ってもかまわない。どうなっても構いはしない。
だから、山に篭っていた。その力を手に入れる為に。といっても独りではないのだが。
八神家の当主として、独りで行くことは許されなかった。うざったい身の回りの世話をする者を三人ばかり付けられた。そうやって俺は山に篭っていた。
そんな時だった。霞が倒れたのを知ったのは。教えたのは沙那、俺の妹だった。
妹の沙那は、歳は五つ離れているが、俺の唯一血を分けた妹である。
赤茶の髪に同色の瞳、日に焼けてもなお白い肌。八神の血を引いているが故の独特な外見。だが、それほど八神の血が顕著なわけでもない。まだ人間として、生を営む事に向いている身体。おそらく次の八神家の当主。技を極める為でもなく。草薙を殺す為でもなく。その技を次代に伝える為だけに八神の技を身につけている。自分よりも光の部分に属している、妹。
別に憎いわけでも、羨ましいわけでもなく、自分とは与えられた役割が違うだけに過ぎない。ただそれだけのことだった。
そして、その、俺から最も近く、また、遠い場所に位置する妹が俺を訪ねてきた。
「お兄ちゃん、霞お姉ちゃんに会いにいってあげて」
ある日沙那が、八神家が所有している山の奥深くにある。今は俺が滞在している屋敷に、訪ねてきてそう俺へと告げた。
「何故だ」
今の俺は忙しかった。草薙を殺す為。殺せる力を手に入れる為に。
そのためには時間が必要だった。それ以外の事を目に入れる時間も、余裕も残ってはいなかった。
だから霞にも今は会いたくはなかった。会えば気が緩む。今、草薙を殺す為に高めて、張り詰めさせている気が緩んでしまう。俺はそう考えて霞には会いたくなかった。
でもそれは単なる口実で、力が及ばなく、草薙を殺す事もできぬ己の姿を見せたくはなかっただけ、なのかもしれない。
沙那は取付くしまも無い俺の冷たい態度に、子供のように顔をクシャクシャにして、今にも泣きそうな顔をした。
仮にも殺人をするための拳を身につけた人間が、これぐらいの態度を俺がとったくらいで、泣きそうな顔をするわけが無い。第一、このような俺の態度には慣れっこのはずだ。俺は少しばかり戸惑いながらも沙那に問い掛けてみる。何があったというのだ。
「どうした……?」
「お姉ちゃんがもうすぐ死んじゃうの………」
俺は、その言葉の意味を理解する事ができなかった。誰が死ぬというのだ。
霞が、死ぬ?
「お姉ちゃん、ガンなの。もう、手がつけられないほど広がって、転移して、もうだめなの。後一ヶ月ぐらいの命だって、お医者様がいってたの」
俺より霞に懐いていた沙那は、堪えきれないとでもいうように涙を零す。
「……霞が……?」
まだ俺には沙那が言っている事を完全に理解する事ができなかった。
理解などしたくはなかった。これ以上、沙那の言葉を聞きたくない。
氷の固まりを飲み込んでしまったように胃の腑が冷たい。全身の血がどこか違う場所に吸い取られてしまったように身体が冷たい。凍えてしまいそうだ。
「お姉ちゃんはお兄ちゃんに言わないでくれって言うの。
お母さんは修行の妨げになるからお兄ちゃんに伝えなくてもいいって言うの。でもそんな事できないよ…お兄ちゃん、霞お姉ちゃんに会いにいってあげてよ…お願いだよお」
沙那は俺の気持ちなど知らずに、ひたすら言葉を続ける。まるで、そうでもしなければ心のバランスを取る事ができないとでもいうように。
「嘘だ……」
「嘘なんかじゃないよ…本当だから……お願い、お姉ちゃんのとこに行ってあげて……」
「嘘だ…」
沙那の言っている事を認めたくないあまりに、俺はただ嘘だと呟くことしかできない。
「本当だから…」
沙那もただ本当だとしか言えないかの様に、それだけをただ、ひたすら呟いている。
二人の間にただ沈黙が降りた。俺はただ嘘だと呟くことしかできず。沙那はこれ以上言うことは無い。とでもいうようにただ黙っていた。しかし、その長い沈黙を破ったのは沙那だった。
「じゃあ帰るから…」
小さく呟き、立ち上るとそのまま部屋を出ていく。足音は重く、沈んでいる。沙那にしては、というより、一流の武道家としては、足音で他者に気持ちを悟られるなど、あってはならない事である。それ程にショックな事だったのだろう。
だが、俺はそれを叱責するでも、別れの言葉を掛けるでもなく、ただぼんやりとその姿を眺めていた。
信じる事などできなかった、霞が死ぬことなど。
長く生きないことなど解かっていた。それでも別れはもう少し先の事だと思っていた。命を削る八神の蒼き炎を操り、草薙の命を狙う自分よりは長く生きるのではないか、とさえ思っていた。それなのに。
霞が死ぬ……?
その事を考えると自分の心が、精神が、どうにかなってしまいそうだった。もとから不安定な自分の心。それを現実に繋ぎ止めている。止めていてくれる…霞。それを失ったら自分はどうなるのであろうか。
「……狂うのかも知れぬな…」
静かに笑む。それも面白いかもしれないと思う。それと同時にそのようなことを考える自分はもう狂っているのかもしれない、とも思う。
俺はただ、低く笑った。
「何故隠す、真先に俺に伝えればいい」
霞は俺の言葉にただ困ったように微笑んだ。その微笑みは、身体の痛みの所為か、ほんの少しだけ引き攣っていたものの、記憶と違わぬ美しいものだった。
「庵にこんな姿を見せたくはなかったから……」
今の霞の姿は、本人のいう通りに酷いものだった。薬の副作用により髪の毛は抜け、地肌が見えている。膚も、白いを透り越して青白い。もとが美しい故に、無残とも言える姿なのかもしれない。
「そんな事を俺が気にするとでも思うのか…」
俺は力無く呟く。もしそうだとすれば、そんな風に思わせた自分が情けなかった。
「そういう理由でもないのだけれど…ただ、庵の好きだった髪の毛も抜けてしまったし、こんな姿を見せたくはなかったの…」
「俺はお前の髪の毛だけを好きだったわけではない…それはおまけのようなものだ…お前はお前だ、何も変らない」
草薙あたりが見れば、信じられないような優しい仕草で、俺は霞の手を握り締める。
白い手。今はガン細胞が転移しているのだろうか。所々が硬く、しこりがある。けれども、それでも十分に白く優しい手。
この手はいつも優しく俺の背中を撫でていてくれた。
父親を殺した、初めて人を殺したその時。自分のものではない血に染まった手と、己の犯した罪の大きさに気が狂って、どうにかなってしまいそうだったあの時も、側にいて、ただ優しく背を撫でていてくれた。辛いとき、苦しいとき、いつもこの手は慰めるように背を撫でていてくれた。するといつも、不思議なほどに安心して、身体の震えは止まった。その手を今までの感謝を込めて、優しく握り締める。
「ごめんね……」
「何がだ…?」
「先に死んじゃうね。ごめんね…」
見ると、霞は静かに涙を流しながら、俺を見つめている。
「泣くな……」
「独りにしちゃうね。ごめんね……」
霞は済まないと、そう呟いてはらはらと涙を零す。俺にはただ、その涙を空いた方の手でぬぐってやることぐらいしかできない。
「安心しろ…俺もどうせすぐに遺く」
霞の耳元で低く囁く。すると霞は驚いたように俺を見つめた。
「どうせ俺の命がそう長い訳はない。それに…お前が淋しいのなら、草薙を殺した後、そのまま死んでもいい。どうせそのまま生きていても、何かやらねばならぬことも、やりたいことも、特にある訳でもないのだからな…家のことならば、沙那がいる」
本気だった。俺には草薙を殺した後、どうしたらいいかなど、どのように生きていけばいいかなど、わかりはしない。特にやりたいことも無い。生への執着も無い。ならばそのまま生きるのも、死ぬのも同じようなものである。
そうとしか俺には思えないのだ。霞が望むのならば、そのまま自らの命を絶つのも、全く構いはしなかった。
「駄目…駄目よ…そんなこと許さない」
霞は驚くほどにはっきりとかぶりを振って、俺の言葉を跳ね除けた。
「庵には生きていて欲しい。私の分も……」
霞は、俺が見たことも無いほど、必死な、懸命な顔で俺に訴える。
「俺は…長くは生きん。……その事はお前も知っているはずだ…」
俺は霞の態度に、いささか戸惑いながら呟く。
「わかってる…でも、それでも、生きていて欲しいの……一年でも、一ヶ月でもいい。庵にはほんの少しでもいいから、長く生きて欲しい。お願い、自分で命を絶つということだけはしないで…」
「お前もいないのに、俺だけに、俺だけ、生き続けていけと言うのか…?この…世界を…独りで…」
そのとき、俺は泣きそうな顔をしていたのかもしれない。霞は優しく囁いた。いつも俺が淋しくて泣いていたときのように。
「大丈夫、この世界にいるのは、存在するのは、私だけじゃない…沢山の…本当に沢山の人がいる。その中にいるから。必ず…庵の孤独を埋めてくれる人が…。
独りなんかじゃない。独りになんかならない」
俺を見つめながら、決して瞳を逸らさず、真っ直ぐに俺の、瞳を見ながら囁く。
だが、何処までもその視線は暖かく、慈愛に満ちている。
「庵……愛してるよ…」
微笑みながら霞は呟く。呟くその顔は、この上なく幸福そうで、死期を悟った人間だとは、とても信じられない程だった。
「俺も…お前を愛してる…」
すらりとこの言葉が出た。この胸に息づく想いが、そうさせた。この想いは、ずっと以前から、自分の中に存在している。
今更意識することの無いほどの自然な想い。
俺の言葉を聞くと、霞は無邪気な子供のように微笑むと、ゆっくりと瞳を閉じた。
「庵…疲れた…一人にしてくれる…?」
「ああ…すまない」
俺は霞の掛け布団を身体の負担にならぬように、優しく掛け直すと、静かに部屋を出た。
「お兄ちゃん…霞お姉ちゃん、幸せそうだったよ…ありがとう」
霞が死んで数日後。沙那が霞の骨壷を持って山を訪ねてきた。
俺は、霞の葬式には出席しなかった。俺が愛していたのは霞自身であり、心、魂と呼ばれるものが抜けた、ただの抜け殻、肉塊に用はなかった。それは霞の一部分であって、霞自身ではない。
霞が死んだと聞いても、不思議と涙は出なかった。死ぬと覚悟していた所為だろうか。
ただ、心にぽっかりと穴が開いて、風でも吹いているように、心が冷たい。
その穴の中は、虚無、虚空。何処までも暗く、暗黒で満たされている。俺はただその穴の傍らに立って、その穴を覗き見ている。
吸い込まれそうな、暗黒。漆黒。
時折、その中に身を投げてしまいたくなる。どんな気持ちがするのだろう。誘惑に駆られる。
だが、霞が死ぬ前に囁いた言葉。それのみが、俺を引き止める。
いるのだろうか。この絶望、悲哀さえも救ってくれる人間が。
ではまってみよう。今にも狂ってしまいそうな、この心を抱え。
霞が俺に嘘をついたことなど無いのだから。
終
![]()