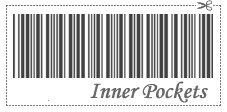| ■駆け出しATCの奮闘記@UF■
#8: 授業を教えるということ②
授業を教えてみていろいろと見えてきたことがあります。
まず、先生は生徒が何をやっているかなんて筒抜けにわかっているということ。例えば高校のとき一番後ろのほうで隠れてしょっちゅう寝ていました。ばれていないなんて思っていましたが先生にしてみれば丸見えだったんですね。そんなことが今回授業を教えてみてわかりました。プリントを見ている振りして次の時間のテスト勉強をしているとか、居眠りしているとか、小声で関係ないことを話しているとか・・・。そんなことは先生からは丸見えなんです。そんなことから「せっかく前日からばっちり準備していったのに」とがっかりさせられます。今考えてみると高校時代の先生も同じことを感じていたんでしょうね。
また試験の採点も難しい。私のクラスの試験は実技試験なのでわりと主観的になりやすい。もちろんスタンダードは決めてあるのである程度のラインは引いてあるんですが、これはどっちかなぁというときは相当迷います。個人的には生徒みんなにいい点を取って欲しいわけですが、たとえば授業にあまり来ない生徒とか、態度が良くない生徒とかにはちょっと自分の感情も影響してしまいそうになります。もちろん公平に採点するわけですが、先生も人間だよなぁと思わされました。
フロリダ大のSATは馬車馬のように働かされるので出来る子とそうでないこのムラが激しいです。個人的には私のクラスでいい点を取るよりも、学んで欲しいと思っていたのでクラス外のスタディーセッションを設けたり、ハンドアウトを作ったり、いろいろやってきました。マニュアルテクニック、とくにジョイントモビリゼーション(Joint
Mob)やPNFは時間を割いて手取り足取り教えたつもりです。そんなせいもあり期末試験にはみんなそれなりにいい点を取ってくれていました。先生として教えた生徒が上達していくのを見るほどうれしいことはないといえます。
ATCは現場で仕事をするだけでなく、自己形成なども必要だとドメインで定められています。授業を教えるということはそういうことにもつながっていくんだなと思わされました。
(05/09/04) |