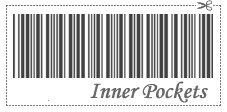| ■ポルトガル遠征記■
#2: 日本代表強化合宿
<2001年9月・愛知県三河安城合宿>
この合宿が私にとっての日本代表参加の初仕事であり、またアスレティックトレーナーとしての日本での初仕事でした。会場は愛知県に本拠地を置くデンソーの体育館、およびその宿舎でした。愛知県はとてもバスケットが盛んな土地であり、その影響を受けてか、知的障害(=FID)のバスケットボールも非常に盛んな地域です。実際、この合宿のみならず以後の強化合宿、そして代表に選ばれた選手は半分以上が愛知県出身です。もちろん、FIDバスケは全国で行われているのですが、なぜこんなにも愛知県に選手が偏っているか?その謎は後々明かすことにしましょう。
はじめて参加して、選手と実際に触れ合ってみた最初の感想は、選手たちはほぼ普通の女の子と見た目は変わりない、ということでした。もちろん、新しいスタッフである私にいきなり心を開く選手はいませんでしたが、徐々にコミュニケーションを重ねるに連れて、私が抱いていた彼女達への印象はことごとく崩されていきました。彼女達は普通に学校へ行き、普通に仕事をし、そして普通に恋愛をしているのです。バスケットに関しても予想以上の技術を保持していました(今となっては、そんなことを選手たちに言ったら怒られるでしょうね)。ただ、決定的に違うのは理解力の遅さです。単純作業であれば問題ないのですが、作業が複雑になればなるほどパニックしてしまうことが、彼女達をFIDたらしめているのでしょう。
アスレティックトレーナーとしての私の仕事は、基本的にアメリカでやってきたこと(健康管理や怪我の処置など)に加えてウォーミングアップとクールダウンでした。正直、アメリカでは選手の準備運動や整理体操などをしたことはなく、ほぼ昔の記憶をたどりながらアップとダウンを選手に指導しました。実際、日本でトレーナー業を営むならば、アスレティックトレーナーの仕事+コンディショニングの知識も必要なのだろうと想像するには簡単でした。また、本職であるアスレティックトレーナーの仕事でも、足首や膝の怪我の処置だけでもかなり忘れていたことがあり、頭と体のブラッシュアップには格好の経験となった合宿でした。結果的に、トレーナーとして現場に復帰するという意味と、FIDバスケットボールを知るという意味でこの愛知合宿は大変有意義な合宿となりました。
<2001年12月・順大合宿>
前回の時点では、私はその場限りのボランティアでしかありませんでした。愛知合宿終了時に小川さんから「次回は12月に順天堂大学で運動能力のテストを兼ねた合宿があるから、もしよかったらまたおいでよ」と誘われていました。実際、私のこの頃の進路はまったくの不透明で、わかっていることといえば、11月にカンザスシティーでアスレティックトレーナーの資格試験があることだけでした。が、無事にこの試験をパスすることが出来、晴れて全米アスレティックトレーナー協会公認のトレーナー(ATC)になることが出来ました。前回は資格を取っていなかったせいもあり、正直仕事をしていてもどこかで気持ちが晴れないことがありましたが、今回は胸を張って参加することが出来ました。
先にも少し触れましたが、今回の合宿のメインは身体能力テストでした。このテストの目的は、知的障害者はトレーニングしても効果が現れないという、非科学的な定説を覆そうというものでした。つまり、知的障害者でもトレーニングを通して、筋力や瞬発力、持久力といった基本的な運動能力を向上することが出来るか、ということです。そこで、総監督である山下先生の母校であり、スポーツ科学に力を入れている順天堂大学が今回の合宿地となったのです。テストは、筋力や持久力、柔軟性、瞬発力などを見るもので、色々な計測機器を用いての本格的な測定となりました。ただ、今になって気づいたことは、このときのテスト結果を聞き忘れているということでした。興味深いことですので、分かり次第このページで紹介したいと思います。
この合宿では、夜のスタッフミーティング(大宴会??)を通じてFIDバスケの実情や他スタッフのFIDバスケに対する情熱などを知ることが出来ました。例えばFIDバスケの認知度の低さから来る慢性的な財力不足や、地元クラブチームや養護学校、そしてバスケット協会との様々な問題、さらには知的障害を持つ選手達への指導方法・・・。私も今まで触れたことのない世界を垣間見ることが出来ました。このミーティングを通じて私が強く感じたことは、スタッフそれぞれが真剣にこの活動に取り組み、どれだけ情熱を燃やしているか、ということでした。同時に日本の悪しき慣習やしがらみを知ることも出来ました。これを期に、私の中でも日本代表FDIバスケチームに対する取り組み方が大きく変わっていきました。
<2002年3月・いわき合宿>
2002年初の代表合宿は福島県いわき市で行われました。この頃になるとメンバーはほぼ同じ顔ぶれで、選手たちとも大分打ち解けるようになっていました。私が帯同しているのは女子チームなのですが、男子選手と違って女子選手は大変な甘えん坊。例えば、誰かが怪我をして私がその選手を診ていると、他の選手が大した怪我でもないのに寄ってきて「私も診て」と言ってみたり、ちょっと痛みを感じただけでさも大怪我をしたようなそぶりを見せて気を引こうとしたり。男子と違って女子にはコーチ達もあまり声を張り上げて怒ったりすることはないので、ちょっと厳しいことを言われるとすぐに泣いてしまう子もいました。それは今まで知的障害者という枠の中で守られて育ってきたということが大きく影響していると思われます。ということで私は極力選手には健常者に対するのと同じように接していくことに心がけました。とにかく私にとってもここでのトレーナーとしての経験は手探り状態だったのです。最初は、痛みを訴えてくる選手を見て、これは本当に痛がっているのか、それともただ甘えているだけなのかを見極めるのが非常に難しく、選手たちの性格やバックグラウンドを知るまでは四苦八苦を繰り返していました。しかし、逆にいうとそういう選手の性格や生い立ちを知ることによって、現在の知的障害者の環境や問題点も自分の中で浮き彫りになっていったのでした。またこの時に、6月のポルトガルの世界選手権に女子のトレーナーとして帯同してもらうという旨を伝えられたのでした。
<2002年5月・横須賀合宿>
この横須賀合宿前に正式に日本代表選手が選出され、ポルトガルでの世界選手権前の最終合宿が5月に行われました。ほぼ全合宿を通して同じようなメンバーが参加していたということで、どんなメンバーが選出されたのか楽しみにしながら合宿地の横須賀市津久井浜高校へと乗り込みました。が、そこには驚愕の事実が!! バスケットボールのスターティングは5人ですが、そろったのはたった5選手。さすがにこれには脅かされました。常に10人弱の選手が毎合宿参加していたのになぜ・・・。それは選手たちの厳しい生活が不参加を余儀なくさせていたのです。もともと金銭的に恵まれていない日本FIDバスケットボール連盟。選手のポルトガル行きの費用は選手持ちだったのです。また、知的障害でありながらやっと就職できた先で10日以上も休むことが出来ないという現実。そういった様々な不条理なことが重なって有力選手たちの不参加という事態が起きてしまったのです。ただ、そういう事実は受け止めなければならないのですが、トレーナーとしてはもう誰一人として試合中もしくは試合前に怪我をさせられないという極めて厳しい状況が待ち構えていたのです。すでにこの合宿で膝を怪我してしまった選手もいて、そのまま最終合宿が終了してしまいました。次選手たちに会うのは一ヶ月後の成田空港で。その時までコンディションは維持できるか? リハビリはちゃんとやってくれるか? そして何とか後一里でもいいから追加で参加できる選手はいないか?そういった不安を抱えながら横須賀合宿を終えたのでした。
そして6月2日、ポルトガル出発に向けて成田空港に向かったのでした・・・。
□ 次の奮闘記へ 次の奮闘記へ
□ もくじへ もくじへ
|