ラテンアメリカはいかがですか
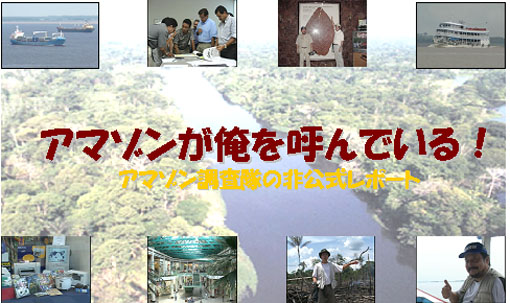
アマゾンが俺を呼んでいる!ーアマゾン調査企画の裏話ー
 逞しい自然の中に意欲的な近代都市が形成されている地域。社会開発と自然が対等に張り合って縄張りを主張しあうところがまだ残されていた。現代人が失った自然との共存能力、そしてサバイバル根性を育てることのできるところはここか。
逞しい自然の中に意欲的な近代都市が形成されている地域。社会開発と自然が対等に張り合って縄張りを主張しあうところがまだ残されていた。現代人が失った自然との共存能力、そしてサバイバル根性を育てることのできるところはここか。
多くの人によって驚きの別世界と言われるアマゾンだが、現代社会の何でも食べ尽くすような経済開発の流れに堪えられるのか。もしかしたらコカコーラの空き缶や古い家電の粗大ゴミで汚れた観光地域になっているのではないのか。
この疑問を拭うべく、そして私の永年の夢であった憧れのアマゾンにもぐりこむために、アマゾンの環境問題を討論する国際シンポジウムを1年がかりで企画し、そして現状把握のためのアマゾン取材調査を企てて、所属先の現地事務所もけんか腰で説得し出かけてきました。
日本のチベットと言われる岩手の北上山系に生まれ、南米でもアマゾンに負けないジャングルが沢山残っていたパラグアイに育った、21世紀最後の原始人(?)と言われる野生児の私はなぜかブラジリア大学大学院で日本の協力によって実施されている「都市交通人材開発プロジェクト」という畑違いの職場のコーディネーター(マネージャー)として派遣されていましたが、芸術的近代都市ブラジリアの環境と、都市交通という仕事柄、「ジャングル禁断症」に陥っていました。そういううことでアマゾンはやたらひかれるところなのです。でも「アマゾンが俺を呼んでいる」だけではお役所は私を出張で行かせてくれません。しかしそのためには妥当な仕事を作ればいいのです。だから手のこんだ国際シンポジウムを企画したのでした。 <アマゾンの交通と環境を考えるシンポジウム>
 まあこれは配属先の日系人所長(東大で工学博士をとっているブラジリア大学院教授)とビールを飲んでいたときに「アマゾンでは開発は避けられないので、先手をとって環境保護にマッチした開発規制を考えるべきだ。そのためにもいつかアマゾンの交通と環境問題のシンポジウムをやりたいんだ」という夢を語ってくれた時に「これだ!」と食らいついたのです。 実際には日本側で協力している分野は「都市交通計画」でそれも主にバスや地下鉄などの内容なので、「船」が主役のアマゾンの広範囲な地域交通は日本側にとっては「畑違い」になってしまい、専門家のリクルートが大変です。そしてなにも仕事を増やすようなことは誰もしたがりません。しかしそこは「何でも見てやろう」「なんでもトライしてみよう」をモットーに経験を増やそうとする私には障害はないのです。(素人の強み)実際にも国際協力は日本側が指導できるものである必要はないのです。途上国側が抱く良いアイデアや計画を実現するために応援してあげるのがもっとも有効な国際協力なのですから。
まあこれは配属先の日系人所長(東大で工学博士をとっているブラジリア大学院教授)とビールを飲んでいたときに「アマゾンでは開発は避けられないので、先手をとって環境保護にマッチした開発規制を考えるべきだ。そのためにもいつかアマゾンの交通と環境問題のシンポジウムをやりたいんだ」という夢を語ってくれた時に「これだ!」と食らいついたのです。 実際には日本側で協力している分野は「都市交通計画」でそれも主にバスや地下鉄などの内容なので、「船」が主役のアマゾンの広範囲な地域交通は日本側にとっては「畑違い」になってしまい、専門家のリクルートが大変です。そしてなにも仕事を増やすようなことは誰もしたがりません。しかしそこは「何でも見てやろう」「なんでもトライしてみよう」をモットーに経験を増やそうとする私には障害はないのです。(素人の強み)実際にも国際協力は日本側が指導できるものである必要はないのです。途上国側が抱く良いアイデアや計画を実現するために応援してあげるのがもっとも有効な国際協力なのですから。

日本的な常識や感覚では多少困難のあるこの計画に幸いだったのは、日本側リーダーの秀島先生がプロジェクトに対して拡散的で冒険心をもっていたことでした。一緒に翌年度の事業計画に組み込み、予算獲得のために数日間夜遅くまで残業して事業費の積算作業をしました。 イケイケモードのブラジル側スタッフは全員張り切って取り掛かりました。日本側が半分くらいだすから後はブラジル側で残りを負担しろといったのには、乗り気のブラジル人には「ノンプロブレム」です。(いやあ、彼らはいい根性をしている!、日本人も少し見習ってほしいこの積極性。)そしてお祭りすきなブラジル人はイベント企画は意外とと日本人よりも慣れているのです。勢いで話を進めながら体制が出来上がっていくのは感心させられました。「これは面白くなってきた、私を招くアマゾンに、今行ってやるからまっとりゃんしゃい!」(どこ弁だ?)と叫びつつ、学会的なイベントを政府関係から国際機関やNGOまで引き込み、州知事からブラジルの運輸大臣と環境大臣まで引っ張り込んでやる企画に発展し、総額1千800万円相当の国際イベントになったのでした。
<シンポジウムの風景>
 私は何でも積極思考で仕事をしますが、遊んでいるような印象を受ける人もあり、よくあまり真剣に受け取ってもらえないことも多く苦労します。人に世話をやくことが好きな私は国際協力は使命感で仕事をしているので、相手側に対する「効果的な援助」にこだわっており、人のうちにきてマスターベーションだけをして帰るような失礼なODAは(実際は結構多い)やりたくないというポリシーがあります。ですからよく見かける「予算消化型税金無駄遣い援助」は絶対にしないよう心がけています。
私は何でも積極思考で仕事をしますが、遊んでいるような印象を受ける人もあり、よくあまり真剣に受け取ってもらえないことも多く苦労します。人に世話をやくことが好きな私は国際協力は使命感で仕事をしているので、相手側に対する「効果的な援助」にこだわっており、人のうちにきてマスターベーションだけをして帰るような失礼なODAは(実際は結構多い)やりたくないというポリシーがあります。ですからよく見かける「予算消化型税金無駄遣い援助」は絶対にしないよう心がけています。
今回の調査は個人的な関心と入れ込みがあったことは事実ですが、アマゾンになにかできることがあるのではないか、とかアマゾンだからこそ今の世界に貢献できることがあるのではないか、といった考えに基づいて行くからには最大限今後の日本の国際援助に役立つ調査にしたいという、結構うるさいこだわりがあり、遊びだと思われると頭にきます。また効果的な調査をするためには、プライベートな旅行では州や市や連邦政府が持っている情報は手に入らないし、専門の研究機関などは訪問できないわけで、環境問題を調べるのに個人でごそごそかぎまわっていると地元のマフィアか軍関係者に消される危険があるので観光旅行では無理です。
そういう訳で多くの同僚がプライベート旅行でアマゾンに出かける中、しっかりと調査として出かける機会と仲間が現れるチャンスをまっていたところ、とうとう現れたのが、私の職場であるブラジル都市交通人材開発プロジェクトにリーダーとして広島大学からきた奥村誠助教授でした。
 このプロジェクトにおける日本側の協力分野は、都市交通で、しかもバスや鉄道などの日本で一般に利用されている技術だったのですが、実は広島大学 工学部はもともと伝統のあった船舶工学がメインで多くの航海技術や船舶関係の技術についての研究者が多いことから奥村先生も瀬戸内海の水運技術の研究などに関心をもっていました。そういうことから、日本の瀬戸内海で開発されている水運技術をもってアマゾンの水運システムの改善に貢献できることがあるのではないかという興味深いプロジェクト案も浮かび上がってきたのです。一方私の心の中には「アマゾンに自給自足のサバイバル学園をNGO活動として設立するのはどうだろうか」という個人的な計画もありました。そういう二人の関心が合わさって、さっそくアマゾン地域の資料集めが始まり、マナウスやサンタレンなどのアマゾン都市にあう関係当局とのコンタクトが始まりました。
このプロジェクトにおける日本側の協力分野は、都市交通で、しかもバスや鉄道などの日本で一般に利用されている技術だったのですが、実は広島大学 工学部はもともと伝統のあった船舶工学がメインで多くの航海技術や船舶関係の技術についての研究者が多いことから奥村先生も瀬戸内海の水運技術の研究などに関心をもっていました。そういうことから、日本の瀬戸内海で開発されている水運技術をもってアマゾンの水運システムの改善に貢献できることがあるのではないかという興味深いプロジェクト案も浮かび上がってきたのです。一方私の心の中には「アマゾンに自給自足のサバイバル学園をNGO活動として設立するのはどうだろうか」という個人的な計画もありました。そういう二人の関心が合わさって、さっそくアマゾン地域の資料集めが始まり、マナウスやサンタレンなどのアマゾン都市にあう関係当局とのコンタクトが始まりました。
 国際シンポジウムに先立ってアマゾン流域の交通と環境に関る問題把握のための調査ですから訪問を受ける機関にとってはそれは、会計監査の「手入れ」と環境省の「手入れ」みたいな「怖さやヤバさ」があります。 地方行政機関では緊張を感じられました。
国際シンポジウムに先立ってアマゾン流域の交通と環境に関る問題把握のための調査ですから訪問を受ける機関にとってはそれは、会計監査の「手入れ」と環境省の「手入れ」みたいな「怖さやヤバさ」があります。 地方行政機関では緊張を感じられました。
しかし一方では公式な部分だけを見て歩いたのでは実際の現状がよく見えないことがよくあります。私は裏を覗いてあるくのが好きですがこの好奇心が日本のODAを無駄な援助にしない重要な情報をつかんだことがよくあります。つまりどこでもあることですが、途上国の政府が日本の援助を要請するときには政府関係者は都合のよいところしか見せてくれません。蓋をされている部分が多く、時にはそこに致命的な事実がかくされていることが多いのです。私は対象となる政府または機関の実状を把握するためには裏表両方を見なければだめだといつも痛感しています。そのためにも幅広い好奇心は失いたくありません。
 問題はどこにもあります。地方行政機関としては見られたくない現状はどこにもあるようです。我々が「市の中心に行きたい」といえば「いえこれからは港湾視察が予定されています。」とかスラム街に連れてってください」というと「そこに行くには今日は時間がありませんとか」とか言われると「これは今度絶対非公式にこっそりと調べにくる必要があるな」とか私のジャーナリスト根性がうずくのです。残念ながら今回の調査では裏を調べてあるく時間的余裕があまりありませんでした。しかし次回に、形を変えてきた時にはなにを調べるべきか課題をたくさん見つけたことは、それだけでも収穫があったという気がします。アマゾンに多くの興味が湧いたわけですから。
問題はどこにもあります。地方行政機関としては見られたくない現状はどこにもあるようです。我々が「市の中心に行きたい」といえば「いえこれからは港湾視察が予定されています。」とかスラム街に連れてってください」というと「そこに行くには今日は時間がありませんとか」とか言われると「これは今度絶対非公式にこっそりと調べにくる必要があるな」とか私のジャーナリスト根性がうずくのです。残念ながら今回の調査では裏を調べてあるく時間的余裕があまりありませんでした。しかし次回に、形を変えてきた時にはなにを調べるべきか課題をたくさん見つけたことは、それだけでも収穫があったという気がします。アマゾンに多くの興味が湧いたわけですから。
先進国に負けずに近代化するアマゾン



貴重な自然が残っているアマゾン

向こう岸が見えないアマゾン河の支流タバジョス河は青く、きれいで透明度が高いため淡水珊瑚まで生存していた。
公式調査報告
<アマゾン地域の交通システムと環境保全に係るフィールド調査>
<ブラジル都市交通人材開発プロジェクト>
<夢見るものたちが築いた理想郷ブラジル> <ラテンアメリカはいかがですか> 【WEB MASTER】
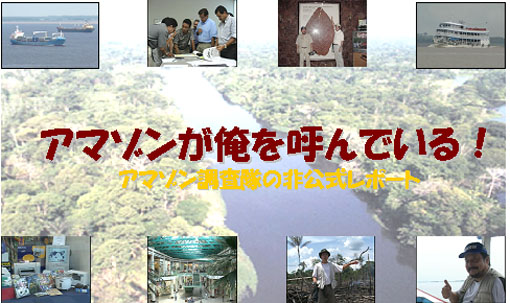
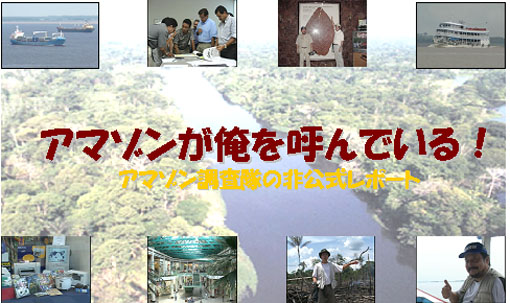
 逞しい自然の中に意欲的な近代都市が形成されている地域。社会開発と自然が対等に張り合って縄張りを主張しあうところがまだ残されていた。現代人が失った自然との共存能力、そしてサバイバル根性を育てることのできるところはここか。
逞しい自然の中に意欲的な近代都市が形成されている地域。社会開発と自然が対等に張り合って縄張りを主張しあうところがまだ残されていた。現代人が失った自然との共存能力、そしてサバイバル根性を育てることのできるところはここか。 まあこれは配属先の日系人所長(東大で工学博士をとっているブラジリア大学院教授)とビールを飲んでいたときに「アマゾンでは開発は避けられないので、先手をとって環境保護にマッチした開発規制を考えるべきだ。そのためにもいつかアマゾンの交通と環境問題のシンポジウムをやりたいんだ」という夢を語ってくれた時に「これだ!」と食らいついたのです。 実際には日本側で協力している分野は「都市交通計画」でそれも主にバスや地下鉄などの内容なので、「船」が主役のアマゾンの広範囲な地域交通は日本側にとっては「畑違い」になってしまい、専門家のリクルートが大変です。そしてなにも仕事を増やすようなことは誰もしたがりません。しかしそこは「何でも見てやろう」「なんでもトライしてみよう」をモットーに経験を増やそうとする私には障害はないのです。(素人の強み)実際にも国際協力は日本側が指導できるものである必要はないのです。途上国側が抱く良いアイデアや計画を実現するために応援してあげるのがもっとも有効な国際協力なのですから。
まあこれは配属先の日系人所長(東大で工学博士をとっているブラジリア大学院教授)とビールを飲んでいたときに「アマゾンでは開発は避けられないので、先手をとって環境保護にマッチした開発規制を考えるべきだ。そのためにもいつかアマゾンの交通と環境問題のシンポジウムをやりたいんだ」という夢を語ってくれた時に「これだ!」と食らいついたのです。 実際には日本側で協力している分野は「都市交通計画」でそれも主にバスや地下鉄などの内容なので、「船」が主役のアマゾンの広範囲な地域交通は日本側にとっては「畑違い」になってしまい、専門家のリクルートが大変です。そしてなにも仕事を増やすようなことは誰もしたがりません。しかしそこは「何でも見てやろう」「なんでもトライしてみよう」をモットーに経験を増やそうとする私には障害はないのです。(素人の強み)実際にも国際協力は日本側が指導できるものである必要はないのです。途上国側が抱く良いアイデアや計画を実現するために応援してあげるのがもっとも有効な国際協力なのですから。
 私は何でも積極思考で仕事をしますが、遊んでいるような印象を受ける人もあり、よくあまり真剣に受け取ってもらえないことも多く苦労します。人に世話をやくことが好きな私は国際協力は使命感で仕事をしているので、相手側に対する「効果的な援助」にこだわっており、人のうちにきてマスターベーションだけをして帰るような失礼なODAは(実際は結構多い)やりたくないというポリシーがあります。ですからよく見かける「予算消化型税金無駄遣い援助」は絶対にしないよう心がけています。
私は何でも積極思考で仕事をしますが、遊んでいるような印象を受ける人もあり、よくあまり真剣に受け取ってもらえないことも多く苦労します。人に世話をやくことが好きな私は国際協力は使命感で仕事をしているので、相手側に対する「効果的な援助」にこだわっており、人のうちにきてマスターベーションだけをして帰るような失礼なODAは(実際は結構多い)やりたくないというポリシーがあります。ですからよく見かける「予算消化型税金無駄遣い援助」は絶対にしないよう心がけています。 このプロジェクトにおける日本側の協力分野は、都市交通で、しかもバスや鉄道などの日本で一般に利用されている技術だったのですが、実は広島大学 工学部はもともと伝統のあった船舶工学がメインで多くの航海技術や船舶関係の技術についての研究者が多いことから奥村先生も瀬戸内海の水運技術の研究などに関心をもっていました。そういうことから、日本の瀬戸内海で開発されている水運技術をもってアマゾンの水運システムの改善に貢献できることがあるのではないかという興味深いプロジェクト案も浮かび上がってきたのです。一方私の心の中には「アマゾンに自給自足のサバイバル学園をNGO活動として設立するのはどうだろうか」という個人的な計画もありました。そういう二人の関心が合わさって、さっそくアマゾン地域の資料集めが始まり、マナウスやサンタレンなどのアマゾン都市にあう関係当局とのコンタクトが始まりました。
このプロジェクトにおける日本側の協力分野は、都市交通で、しかもバスや鉄道などの日本で一般に利用されている技術だったのですが、実は広島大学 工学部はもともと伝統のあった船舶工学がメインで多くの航海技術や船舶関係の技術についての研究者が多いことから奥村先生も瀬戸内海の水運技術の研究などに関心をもっていました。そういうことから、日本の瀬戸内海で開発されている水運技術をもってアマゾンの水運システムの改善に貢献できることがあるのではないかという興味深いプロジェクト案も浮かび上がってきたのです。一方私の心の中には「アマゾンに自給自足のサバイバル学園をNGO活動として設立するのはどうだろうか」という個人的な計画もありました。そういう二人の関心が合わさって、さっそくアマゾン地域の資料集めが始まり、マナウスやサンタレンなどのアマゾン都市にあう関係当局とのコンタクトが始まりました。 国際シンポジウムに先立ってアマゾン流域の交通と環境に関る問題把握のための調査ですから訪問を受ける機関にとってはそれは、会計監査の「手入れ」と環境省の「手入れ」みたいな「怖さやヤバさ」があります。 地方行政機関では緊張を感じられました。
国際シンポジウムに先立ってアマゾン流域の交通と環境に関る問題把握のための調査ですから訪問を受ける機関にとってはそれは、会計監査の「手入れ」と環境省の「手入れ」みたいな「怖さやヤバさ」があります。 地方行政機関では緊張を感じられました。 問題はどこにもあります。地方行政機関としては見られたくない現状はどこにもあるようです。我々が「市の中心に行きたい」といえば「いえこれからは港湾視察が予定されています。」とかスラム街に連れてってください」というと「そこに行くには今日は時間がありませんとか」とか言われると「これは今度絶対非公式にこっそりと調べにくる必要があるな」とか私のジャーナリスト根性がうずくのです。残念ながら今回の調査では裏を調べてあるく時間的余裕があまりありませんでした。しかし次回に、形を変えてきた時にはなにを調べるべきか課題をたくさん見つけたことは、それだけでも収穫があったという気がします。アマゾンに多くの興味が湧いたわけですから。
問題はどこにもあります。地方行政機関としては見られたくない現状はどこにもあるようです。我々が「市の中心に行きたい」といえば「いえこれからは港湾視察が予定されています。」とかスラム街に連れてってください」というと「そこに行くには今日は時間がありませんとか」とか言われると「これは今度絶対非公式にこっそりと調べにくる必要があるな」とか私のジャーナリスト根性がうずくのです。残念ながら今回の調査では裏を調べてあるく時間的余裕があまりありませんでした。しかし次回に、形を変えてきた時にはなにを調べるべきか課題をたくさん見つけたことは、それだけでも収穫があったという気がします。アマゾンに多くの興味が湧いたわけですから。


