|
特急は、都市間をできるだけ高速で結ぶ列車であるはずだが、そのスピードは千差万別である。新幹線ならば、最高速度300km/hの「のぞみ」と、各駅ごとに速い列車に追い抜かれる「こだま」の速度差は大違いである。在来線でも、ほとんど同じ特急料金をとられるのに、時速130km/hで快走を続ける特急と、山あいの曲がりくねった細道を、隣の道路を行く自動車に抜かれるような鈍足でたどる特急の走りには大きな差がある。 ここでは、どのような要因で特急列車の走りっぷりが決まってくるのかを見て行きたい。 全国の在来線特急列車の表定速度一覧 とくに速度が高い区間は以下のとおりである。 ・函館本線 札幌〜旭川 ・函館本線・室蘭本線・千歳線 函館〜札幌 札幌〜東室蘭間では表定速度が110km/h台で日本最速である。沼ノ端〜白老間には日本最長直線区間(28.7km)がある。 ・津軽海峡線 蟹田〜木古内 青函トンネルは、将来の北海道新幹線の延伸に備えて200km/h以上の運転も可能な規格で建設されており、現在の最高速度は140km/hである。 ・東北本線 青森〜八戸 ・常磐線 上野〜日立 ・湖西線・北陸本線・北越急行線 京都〜金沢〜越後湯沢 湖西線は全線立体交差の高規格路線であり、京都〜金沢間の表定速度は110km/hを越える。北越急行線も全線立体交差で、最高速度は160km/h。 ・鹿児島本線・日豊本線 博多〜大分 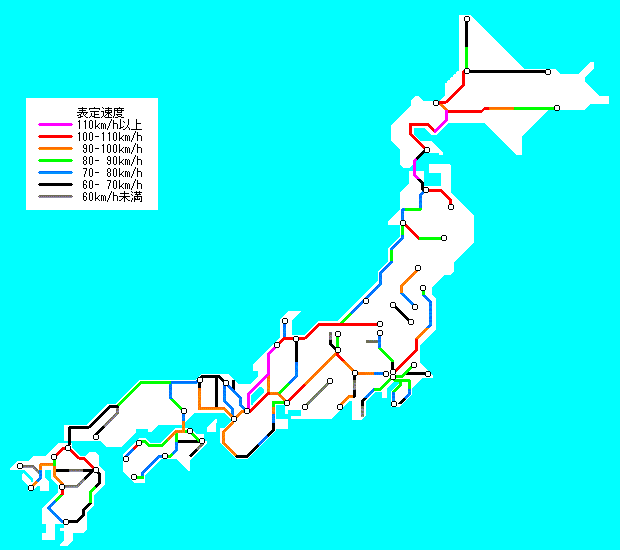
最高速度・線路の立派さ 路線によって、認可されている最高速度は異なる。これは主に、高速運転に適した太くて重いレールを使用しているか、バラスト・路盤が厚く整備されているか、レールの狂いが少なく高精度の線路保守がなされているかという線路の規格によって異なる。 現在、在来線では特急が頻繁に運行されて線路改良の進んだ重要幹線では120〜130km/h、改良が不十分な地方幹線では95〜100km/h、ローカル線では85km/h程度の最高速度が一般的である。線路改良を行えば当然スピードアップが可能であり、近年は地元自治体がその費用を一部負担するケースも多く見られるようになった(日豊本線延岡〜宮崎間、山陰本線出雲市〜益田間、石勝線・根室本線など)。 わが国の在来線特急列車の最高速度は、現在、原則として130km/h以下となっている。これはかつて、運輸省令の鉄道運転規則により、列車は非常ブレーキをかけたときに600メートル以内で停止しなければならないこととされており、これを満たすには、現在の一般的な車両のブレーキ性能では130km/hから停止する場合が限度であったためである。高架・トンネルが連続し踏切がない区間では例外が認められ、青函トンネル部分(津軽海峡線・蟹田〜木古内間)は最高140km/h、北越急行線(六日町〜犀潟)は最高160km/h運転が行われている。 旧鉄道運転規則に代わって、2002年3月より施行されている鉄道に関する技術上の基準を定める省令にはこの600メートル規定は盛り込まれなくなったが、わが国は人口過密で踏切事故の危険が高く、またカーブも多いため仮に最高速度を引き上げてもその速度を出せる区間がほとんどないことなどから、人口が少なく直線区間の長い北海道の平野部や、全線高架で造られた湖西線など一部の路線を除けば、多額を投じて抜本的な線路改良を行わない限り、在来線では最高速度の引き上げは難しいと思われる。 なお、ドイツ、フランス、イギリス、スウェーデン、アメリカなどでは、在来線区間でも最高速度200km/h以上の運転が行われている。これらの国では、山間部の多い日本より地形がなだらかで広い平野部が多く、人口密度が低いため踏切も少ないなど、高速運転のための条件が大きく異なっている。また、中国でも近年160〜180km/hの高速運転が開始されているようである。 車両の性能 高速性能、加速性能が優れているかどうかによって、所要時間にも差が出てくる。たとえば北陸本線の最高速度130km/h運転を行う681・683系を使用する「サンダーバード」と、最高速度120km/hの485系「雷鳥」では、停車駅が同程度であっても大阪〜金沢間で10分程度の差が生じている。また機関車牽引による寝台特急は最高速度、加速度ともに電車よりも大きく劣っており、北陸本線、鹿児島本線などでは昼間の特急列車に追い抜かれるという例も見られる。 さらに近年スピードアップに大きな効果を発揮しているのが、カーブでの通過速度の高い振子式車両である。カーブで車体を内側に傾けることによって遠心力を緩和し、乗り心地を悪化させることなく、通常の車両より20-40km/h程度、高速でカーブを通過できる。1973年に特急「しなの」に導入された381系電車が最初であり、JR登場後、特急「南風」に初の振子気動車である2000系も登場。カーブが多くスピードアップが難しかった地方幹線に、広く普及している。乗り物酔いを生じるなどの欠点も指摘されてきたが、近年の車両はカーブのデータをあらかじめ読み込み、傾斜幅を調整する制御付自然振子車両となり、乗り心地は改善されている。 カーブの多さ・地形 わが国は国土の7割を険しい山岳地帯が占めており、さらに鉄道建設時にネットワークの拡大を優先するために費用を節約して線路を敷設したため、非常にカーブが多くなっている。鉄道ではカーブの半径に応じて下のように制限速度が定められている。一般にカーブの半径は、平地部では最小600メートル程度、地形の険しい山間・海岸部では300〜400メートル程度となる。 このため、幹線では平野部で120〜130km/h以上の高速運転ができても、山間部に差しかかると速度は90〜100km/hに低下する。さらに線路規格が低い亜幹線では、山間部の速度は70〜80km/h程度である。 なお新幹線の最小曲線半径は、連続して超高速運転を行えるよう、建設時期の古い東海道新幹線で2500メートル、それ以外では4000メートルとなっており、在来線と比べて大きな差がある。
単線・複線 単線の場合は、対向列車の待ち合わせのための停車により速度が低下する。とくに列車本数の多い単線区間が続く予讃本線、高徳線、鹿児島本線八代以南などでは、交換待ちのために表定速度が1割程度低下している。一方向が遅れるとすぐに交換のサイクルが狂い反対方向の列車も遅れだし、ダイヤが乱れたときの影響も大きい。 さらに単線区間では、駅の部分だけ線路が2本以上あり、ポイントがY字型になっており、ポイントの規格が低い場合は駅を通過するごとに45km/hまで減速して再び加速しなければならない。最近は、分岐部の曲線半径が大きいポイントや、通過線を直線としたポイントを導入し、速度制限を緩和する路線が増えている。 ライバルの有無 そもそも鉄道会社がスピードアップを行う強い意思があるかどうかも、列車の速度に大きく影響する。高速バスや航空、並行する私鉄といったライバルが存在する場合、高速化に力が入れられる場合が多い。代表的な事例は中京圏、関西圏の都市間を結ぶ新快速列車があり、料金不要の列車ながら、表定速度90〜100km/hという特急クラスの高速運転を行う。これは、名鉄、阪急、京阪、阪神といった私鉄が主要都市間で並行し、競合関係にあることが大きな要因となっている。関東圏では比較的JRと私鉄が同じ都市間で競合している路線が少なく、そのほかに輸送量が大きいため高速ダイヤを組むことが難しいという事情もあるが、列車の表定速度は60〜70km/hにとどまっている。 一般に、競合相手がいる区間ではサービスに力を入れ、乗客を独占できる区間や、逆に少々の努力では勝ち目のない区間では、サービス改善がなされないという傾向がある。たとえば東北・上越新幹線は、航空との競争が激しい秋田行「こまち」で、優先的に停車駅を減らして高速運転を行う一方、乗客を独占できる仙台、新潟や山形行き列車のスピードアップは行われていない。また九州の日豊本線では、高速バスとの競合が激しい博多〜大分間に新型の高速振子車両が集中して投入され、航空と高速バスが圧倒的優位にある北九州〜宮崎間の列車はスピードアップがなされず本数も減少している。 |