

| 園長、少数民族の村に行く、の巻 |
●少数民族の村に行く
タイに行きたい!
そう思ったのは「タイは若いうちに行け!」というCMを見たから、ではなかった。少数民族の人に会ってみたい、と思ったからだ。
タイ北部には、少数民族の方々がまだ多く住んでいる。日本でもよく知れ渡っているのが、「パダウン族」。パダウン族という名前は聞いたことがないかもしれないけど、「首が長いことが美しいとして、首に何重もの金属の輪をまいている民族」をテレビで見たことがあると思う。あの方々がパダウン族。この他にも独自の文化を守っている民族の方々がいる。
タイ北部ではそういった少数民族の方に出会うことが楽しみの1つなのだが、個人で出かけるとなると、山奥に住んでいて道が分からなかったり、ミャンマーとの対立、麻薬など危険なことがたくさんある。できれば、現地でトレッキングツアーに参加するのがいい。「ツアー」といってもちゃんとした旅行会社が主催するわけでもなく、バスで移動するわけでもない、トレッキングなのだ。
私が拠点としたのが、北部のチェンマイという町。ここは飛行場もあるし、首都バンコクからの北行列車の終点なので、交通の便はよい。チェンマイについて、まずはゲストハウスを選びにかかった。
「ゲストハウス」というのは、ホテルよりも割安な簡易宿泊所のようなところで、高いところですら1泊500円ぐらいで泊まれる。そして、チェンマイの大部分のゲストハウスには、トレッキングツアーの申込デスクが併設されていて、トレッキング会社と提携しているか、独自のツアーがある。
園長が選んだのは「LIBRA HOUSE」。市内の裏路地を歩いていると、日本語で話しかけてくる中高生ぐらいの兄妹がいて、うちがゲストハウスをやってるんだと言ってくる。何だかあやしいと思いつつも、個人旅行者御用達の「地球の歩き方」をパラパラとめくったら評判のよいところだったので、そんじゃ、ということで泊まることとなったのだ。そして翌日から2泊3日のトレッキングツアーへと出発した。
●1日目/旅立ち
トレッキングツアーは8人ぐらいで、案内役はタンさんというおじちゃんだ。案内役といっても、「右に見えますのは〜」というものではなく、自動車の運転・食料運搬・調理、道案内などなど全てのことをひとりでこなすエキスパートなのだ。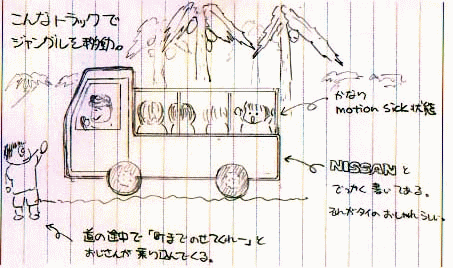
バスはなく、こんな感じのトラックに乗って移動する。これは、タイでは日常茶飯事の光景で、荷台に何人もの人が乗っているのだ。しかも、ヒッチハイクも当たり前のようで、「町まで乗っけてってくれよ」と気軽に言ってきたりしている。それが、タイなのだ。
タイでは「MADE IN JAPAN」を持つことが一種のステイタスらしい。この時に乗ったトラックはもちろん、たくさんの車の後ろには、でかでかと日本車であることをアピールするかのように社名が書かれている。余談ながら、テレビで「おしん」をやっていた。タイ語でしゃべるおしんは、不思議だ。それはともかく、私が日本人と分かると「ニッサン、トヨタ、オシン、ドラーモン(ドラえもん)」と日本の知りうる単語を教えてくれる人が多い。でも、その単語はテレビ関係か社名かだ。なんとなく、日本のイメージというのが「商売」しかないのかと、悲しく思った。
さて、話をトレッキングに戻すこととしよう。トレッキングポイントの一番近くの町が「パイ」というところで、ここを過ぎると砂埃舞う山へと進んでいく。この山は日光のいろは坂も目じゃないぐらいにきっつい曲がりくねった坂道続きで、私は気持ち悪くなって途中で止めてもらったぐらいだ。
山道を走ること約1時間、トラックを降りると今度はジャングルのような道を歩きに歩く。道といっても獣道のようなところなので、もしひとりで来たら絶対に迷うだろうし、一度行ったからといって、今もう一度行こうと思っても、たどり着けないような場所を通っていった。荷物は必要最低限に、と言われていたものの、水だけは数本のパックを持っていかなければならず、これが重い。でも、この水がなくなると、生水しかなくなり、それを飲めば重い病気になる可能性も。どっちの重さをとるかといえば、もちろん前者なので、我慢して運んでいく。
どれぐらい歩いたのだろう。2時間以上か、気持ち的には4、5時間は歩いた。やっとのおもいでたどり着いたのが、1日目の宿泊地「ラフ族」の村だ。
●1日目/ラフ族〜村に到着〜
ラフ族の村に到着した。写真が撮れてなかったのが残念だが、村は小学校の校庭よりも1まわり小さいぐらいの広さだとうか。竹の屋根に、竹などで作られた壁でできている家ばかりだ。いわゆる「日本の田舎のイメージ」というよりも、もっと時代がさかのぼり、縄文時代とかのイメージに近い感じがした。とは言っても、家の中はかまどとかあり、工夫されているようだ。ツアーの人は、ちょっとゴージャスな「高床式」の部屋に通された。
ぶらぶらと村を歩いていると、事件が起きた。
なんだか騒がしく、喧嘩しているような感じだったので村の真ん中に行ってみると、男が口から血を流している。なぐられたようだ。何だか大変なことを話していることだけは分かったので、英訳してもらったところ、どうも「隣村の男の人で、この村の男が自分の妻と浮気をしたと思い込み、殺しに来た」ということらしいのだ。それで、取り押さえられたらしい。事実無根の話らしく、「こんな騒動はめったにない」と村人も驚いている様子だった。
ひと騒動あったあと、村の子供たちと遊んでみた。どの子も目が純粋そのものだ。おそらく、テレビやパソコンの画面などを見ずに一生を過ごすことになるだろう彼らは、そんなものとは無縁でも楽しげで、自分たちの仲間で遊ぶことに夢中であった。私は子供たちの前で、日本から持っていったおりがみでつるを作ってみた。でも、「つる」というものを子供たちは見たことがないし、あいにく私も「つる」という英語を知らなかったのでガイドさんに訳してもらうこともできず、「これは鳥だ」と真似て見せるとキャッキャと笑っていた。言葉はなくても、動作でコミュニケーションすることができるのだ。特に子供の場合は。
そういえば、この写真の左側の子が着ているのがラフ族の民族衣装だ。赤と黒という色遣いと、銀の装飾品が特徴のようだ。右側の子は普通のTシャツのような感じだ。
●1日目/ラフ族〜少数民族の運命〜
食事はラフ族の人と一緒、というわけにはいかなかった。ガイドのタンさんが作ってくれる、タイ風やきそばのようなもの(だったかな?)を食べる。食後は、ラフ族の子供たちが集まってきて、歌を歌ってくれた。そして、民族衣装をつけた大人たちが集まって…と思ったら、今度は物売りを始めた。刺繍した布とか、ハチマキのようなものとか、どんどん押し売りしてきた。あとでガイドさんから話を聞いたが、今の少数民族の収入は観光で成り立っているのだという。ちょっと前までは、高額の収入源があった。それが「ケシ」の栽培だ。ケシは麻薬「アヘン」のもとになる植物。それを栽培して合法的に(?)売っていたらしい。しかし、禁止となり、ケシの栽培地を焼くことで補償金を政府が払うようになった。薬としての必要最小限の栽培はまだ行われており、実際に栽培している畑があったが、何重にも柵が設けられていて、不法に取り扱われないように管理されていた。村によっては、まだケシの栽培を続けているところがあるらしい。それが現実なのだ。
●2日目/ラフ族〜豪華なトイレ〜
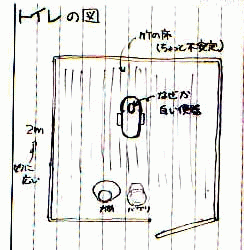 竹の屋根にあるトイレ、そう考えるとどうもきっついイメージが浮んできてしまう。かなり汚いような、ちょっと崩れているような。しかし、私の悪い予想とは裏腹に、最も近代的な雰囲気があるのがトイレだったのだ。トイレの広さは2帖より狭いぐらいなので、日本のトイレからすれば結構広い。作りは村の家と同じで、竹で作られた屋根と壁。床も竹だ。そしてそのまん中にはなんと白い便器が鎮座していたのだ…。こんなところに白い便器が…?でも、これはいわゆる「ボットン便所」?と思っていると、そうでもないらしい。よく言えば、新幹線の中のトイレのように「見た目」は水洗トイレで、「実際」はボットン、ということなのだ。なので、便器の穴から下を覗いても別に嫌な思いをすることはない。なお、水洗とはいったが、ラフ族のトイレは「人力水洗」で、広いトイレの片隅におかれたカメの水をヒシャクですくって流すのだ。カメの水は手を洗うため、と思い込んでいたら、そういうことだったらしい。
竹の屋根にあるトイレ、そう考えるとどうもきっついイメージが浮んできてしまう。かなり汚いような、ちょっと崩れているような。しかし、私の悪い予想とは裏腹に、最も近代的な雰囲気があるのがトイレだったのだ。トイレの広さは2帖より狭いぐらいなので、日本のトイレからすれば結構広い。作りは村の家と同じで、竹で作られた屋根と壁。床も竹だ。そしてそのまん中にはなんと白い便器が鎮座していたのだ…。こんなところに白い便器が…?でも、これはいわゆる「ボットン便所」?と思っていると、そうでもないらしい。よく言えば、新幹線の中のトイレのように「見た目」は水洗トイレで、「実際」はボットン、ということなのだ。なので、便器の穴から下を覗いても別に嫌な思いをすることはない。なお、水洗とはいったが、ラフ族のトイレは「人力水洗」で、広いトイレの片隅におかれたカメの水をヒシャクですくって流すのだ。カメの水は手を洗うため、と思い込んでいたら、そういうことだったらしい。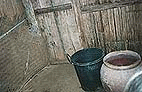
●2日目/ジャングルへ〜出川哲郎事件〜
2日目のスタートは、またジャングルからだった。昨日とは違い、もっと「ジャングルらしいジャングル」で、ターザンがいるというよりもインディージョーンズが歩いていそうなジャングルだ。そして、その日も事件が起きた。1時間ぐらい歩いてからだったろうか、休憩をとることになった。そして、ふと見るとガイドが2人になっていた。「へえ、いつの間に合流できたんだろう」と思いながら、その人と一緒に記念写真を撮った。英語で話し掛けても通じなかったが、とりあえず分かったのは、その人が出川哲朗さんに似ているということと、二の腕に立派な入れ墨をしているということだけだった。なぜか、休憩はあっけなく終わり、ふと気付いてみたら、今度は前後にアーミールックの人が合計3人ついて歩いている。手にはライフル。優しげな感じも受けたのでタイの軍隊の人で、悪い人たちではなさそうだ、ということを感じた。そして、この後にバンブーラフティング(竹で作ったいかだで川下り)をするのだが、その時もこの軍隊の人が一緒についてきたのだ。2日目の夜、私はガイドのタンさんに呼び出された。しかも恐い顔で。いつの間にかタイの慣習では悪いことをしてしまったのか
、と思っていると、意外なことを口にした。「ジャングルで写真を撮ってたよね?」しまった、ジャングルで何か軍隊の秘密基地かなんか写してしまってフィルム没収になるのか…「明日、町に戻ったらすぐに現像して欲しいんだ。君がジャングルで記念写真を撮っていた男(=出川)、あいつはミャンマーから不法入国しているテロリストなんだ。君の写真をもとに町、及び空港などに指名手配をかけることとなったんだ。」…あまりの展開に驚いた。聞けば、ガイドのタンさんはこの地域のことは全て知り尽くしている。道はもちろん、住人もだ。あの男は見たこともないし、入れ墨で正体が分かったらしい。それが分かっていたので、早めに休憩を終えて出発した、しかも運がいいことにタイ軍の人が訓練中だったので、事情を話して途中まで一緒に来てもらった、ということだったのだ。そして心配しないように、夜までだまっていたらしい。ミャンマーのテロリストと記念写真を撮る…一生できない経験をしたのだった。
●2日目/ジャングルへ〜バンブーラフティング〜
今日の目的地はリス族の村。上で書いたようなジャングルドキドキトレッキングのあと、バンブーラフティングがまっていた。写真のような竹で作った巨大いかだで、たてに並んで6人ぐらいは軽く乗れるものだ。先頭と最後に乗る人が舵取り棒を持つのだが、私は最後となった。たいしたことが無いとおもっていたが、これが大変だ。いかだが巨大なため、川に沿って流れたとしても、岩にぶつかりそうになる。そのため、川の流れに逆らうように思いっきり川底に棒をつきたてていかだの方向を変えていかなければならないのだが、川は2メートル以上の深さだ。なぜそれを知っているかといえば、川に落ちたからだ。棒をつきたてるのはいいが、つきたてすぎると川底の砂にめり込んだり、岩の間にさしてしまったりして、いかだは前に進むが私は棒とともに取り残されることになり、そのままドボン!棒を川にさすときにおおよその深さは分かっていたつもりだったが、本当に川底に足がつかないときはちょっと恐怖だった。ちなみに、3回落ちた。