ジョセフソン接合の謎を解き明かし、電子波素子の世界初の実用化を果たす |
1999年6月にプレス発表されたコンパクトで高性能なSQUID脳磁界計測装置は、従来の能力を大幅に上回る画期的なCT装置として各界の注目を集めている。常にその開発の中心となってきた太田 浩表面界面工学研究室客員研究員(郵政省通信総合研究所横須賀無線通信研究センター主任研究官)は、「この装置のポイントは高温超伝導体を使った磁気シールドと低周波領域にも高感度な超伝導電子波素子の開発にありますね」と語り、さらに「単に素子ができたというだけでなく、理論的にもその特性を解明することができたのです」と‥‥。 |
ジョセフソン接合の統一理論 |
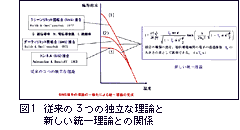 超伝導体同士が、間に何らかのごく薄い障壁を介した構造によって弱く結合したシステムをジョセフソン接合という。超伝導体電極間の障壁を通して超伝導電流が流れるが、従来これには3種の温度依存のパターンがあるとされていた(図1)。 超伝導体同士が、間に何らかのごく薄い障壁を介した構造によって弱く結合したシステムをジョセフソン接合という。超伝導体電極間の障壁を通して超伝導電流が流れるが、従来これには3種の温度依存のパターンがあるとされていた(図1)。
ひとつは1962年に、この現象を最初に予言した英国のB.D.ジョセフソン自身によって解明されたもので、超伝導体(Superconductor)電極の間に薄い絶縁体(Insulator)をはさんだ“トンネル(SIS)接合”に流れる電流についてである(図1の(3))。
もうひとつは、太田客員研究員が大学院の博士過程で手がけた超伝導体同士を点接触させる方法や、結合部の超伝導体を細くくびれさせる、あるいは超伝導体間に薄い常伝導金属(Normal metal)層を介するなどによって生じる“弱結合(SNS)接合”というものである。弱結合接合には2種あり、それぞれ“クリーンリミット弱結合(SNS)接合”(図1の(1))、“ダーテイリミット弱結合(SNS)接合”(図1の(2))と呼ばれている。
「この3つの中で、素子開発という意味でも理論の浸透性においても、長い間、トンネル接合が群を抜いていました。一方、私自身は博士過程の時から弱結合接合一筋です。しかしながら、弱結合接合のデバイスでどんなに良い実験結果を出しても、論文のレフェリーにトンネル接合の理論とは違うといわれることが多かったのです。それで理論も何とかしなければならないと思っていました。」
 世の主流から少し離れ、冷静な目でこの3つの超電流パターンを眺めていた太田客員研究員たちは、超伝導体電極間の位相差に依存する超伝導電流を導き出す理論式を厳密に求めていった(図2)。 世の主流から少し離れ、冷静な目でこの3つの超電流パターンを眺めていた太田客員研究員たちは、超伝導体電極間の位相差に依存する超伝導電流を導き出す理論式を厳密に求めていった(図2)。
「電子の自由エネルギーを位相で微分して電流値を出すわけですが、この仕事を進めている最中に、大変勇気づけられる事実に気づいたのです。」
それは、マックス・プランクが今世紀の初めに導き出じた黒体放射の式(図2の緑色の式)との類似である。
「SNS接合の電気抵抗は電極間の量子力学的な位相差に依存しますが、このSNS接合の熱力学ポテンシャルが、量子論の事始め、プランク定数導入の発端となった黒体放射の式と極めて美しい対称性をもつことは、『我々の進んでいる方向は正しいんだ』という大きな自信を与えてくれましたね。」
こうして導きだした理論式を検討し、3種のパターンは超伝導体電極間に設けた障壁における電子の通りやすさ(透過係数)の違いによって説明できることが、明らかになった。約4年前のことである。透過係数が小さくて「0」に近いとトンネル接合のパターンになり、大きくて「1」に近いとクリーンリミット弱結合(SNS)接合、透過係数が中間の「1/2」程度だとダーティリミット弱結合(SNS)接合になるのである。
「ちょうどマックスウェルの電磁場方程式が、電波、可視光、X線などの波長の違いを越えてすべての光の性質を統一的に説明したのと同じようなものだと、私たちは自負しています。」 |
電子とホールの対により軌道を形成 |
 ジョセフソン接合の統一理論への道を歩み始めた頃、接合部分でどのような現象が起こっているか」のイメージも太田客員研究員の頭に浮かんできた。障壁を通して1個の電子が一方の側の超伝導体に入る場合、スピンの向きが逆向きの電子とペアにならない限り超伝導の基底状態には入ることができない。超伝導状態では電子は常にペア(クーパー対)で運動することが理論的にも確かめられている。そこで電子は障壁内からスピンと運動量が反対符号の電子を捕って対となって一方の超伝導体に流れていく。すると障壁には電子が抜けた正孔(ホ一ル)が形成され、これが反対側の超伝導体に流れる。ホールも対にならない限り超伝導の基底状態には入れず、超伝導体は電子を1個障壁部に吐き出してホールの対をつくる(アンドリェフ反射)。 ジョセフソン接合の統一理論への道を歩み始めた頃、接合部分でどのような現象が起こっているか」のイメージも太田客員研究員の頭に浮かんできた。障壁を通して1個の電子が一方の側の超伝導体に入る場合、スピンの向きが逆向きの電子とペアにならない限り超伝導の基底状態には入ることができない。超伝導状態では電子は常にペア(クーパー対)で運動することが理論的にも確かめられている。そこで電子は障壁内からスピンと運動量が反対符号の電子を捕って対となって一方の超伝導体に流れていく。すると障壁には電子が抜けた正孔(ホ一ル)が形成され、これが反対側の超伝導体に流れる。ホールも対にならない限り超伝導の基底状態には入れず、超伝導体は電子を1個障壁部に吐き出してホールの対をつくる(アンドリェフ反射)。
「『超伝導体にエレクトロンがぶつかって障壁部にホールを作る、そのホールが反対側の超伝導体にぶつかってエレクトロンを吐き出させる』、この繰り返しによって、クーパー対が運ばれ続けて、超伝導電流が流れるというのがSNS接合の新しいイメージです(図3)。」
 従来はトンネル接合に関するジョセフソンの理論にしても、2個の電子が障壁部を横切って遷移する結果としてクーパー電子対が透過することはわかっていたが、障壁内部の透過過程はブラックボックスのままであった。 従来はトンネル接合に関するジョセフソンの理論にしても、2個の電子が障壁部を横切って遷移する結果としてクーパー電子対が透過することはわかっていたが、障壁内部の透過過程はブラックボックスのままであった。
「我々の考えた電子とホールによる軌道を理論的に解析すると非常に面白いことがわかりました。」
原子核を巡る電子軌道のように、この軌道もボーアーゾンマーフェルドの量子条件を満たすことが明らかになったのである(図3)。つまり、この状態では電子は粒子ではなく、波として振る舞っている。
「この意味するところは、我々の開発した素子が、まぎれもなく電子波素子であるということです。」
電子を非常に小さい空間に閉じ込めれば粒子としてではなく波としての性質が現れ、これを利用した電子波素子、デバイスを開発しようという動きが近年盛んになっているが、ナノメーター(100万分の1ミリ)程度の超微細加工披術などを必要とし、実現はなかなか難しい。太田客員研究員によれば、「SQUIDに使った私たちの超伝導電子波素子が、実用化に至った最初の例でしょう」ということだ。なぜ現状の加工技術を使って実用化レベルにまでもっていくことができたのか?ここにも電子・ホール系の妙味が活かされている。電子だけの場合だと、障壁部の厚みを「プランク定数を電子の運動量で割った値より小さく」しなければならず、数オングストローム程度となる(1000万分の数ミリ)。 一方、電子・ホール系の場含は、プランク定数を「電子の運動量とホールの運動量との差」で割った値以下でいい。当然、電子とホールの運動量の差は非常に小さく、その結果障壁の厚みは100オングストローム(10万分の1ミリ)程度の値が許されるようになる。 一方、電子・ホール系の場含は、プランク定数を「電子の運動量とホールの運動量との差」で割った値以下でいい。当然、電子とホールの運動量の差は非常に小さく、その結果障壁の厚みは100オングストローム(10万分の1ミリ)程度の値が許されるようになる。
「これだと、今の微細加工枝術で可能です。このような理論的な裏付けを得たのは4年前くらいですが、実はずいぶん前にそのような障壁の厚さの素子を作っており、すでに10年前には70%以上の歩留まりを確立していました。」
この素子は“準平面型ジョセフソン接合”と呼ばれ、その構造は図4のようになっており、1977年に太田客員研究員が特許を出願している。赤色の部分が障壁部となり、80オングストローム程度の厚さに押さえられている。 |
高性能SQUID脳磁界計測装置の開発へ |
 さて、開発された素子を実験的に確かめていったところ、透過係数が1に近い、つまり“クリーンリミット弱結合(SNS)接合”の場合に低周波雑音が少ないことが明らかになった。 さて、開発された素子を実験的に確かめていったところ、透過係数が1に近い、つまり“クリーンリミット弱結合(SNS)接合”の場合に低周波雑音が少ないことが明らかになった。
「脳の場合、10ヘルツくらいで動いているので、低周波雑音が少ないということは重要なことです。」
脳が作る磁界というのは、地磁気の1億分の1というたいへん小さなものであり、その計測は太田客員研究員によれば、「往来の激しいガードレールの下で蚊の音をキャッチするようなもの」だそうだ。そこで雑音に強い検出用の素子をつくるだけでなく、外界の磁場を遮蔽するシールド装置も必要になってくる。
1999年6月のプレス発表のもうひとつの目玉は、高温超伝導体を使ったコンパクトなセラミックのシールド装置だ。ニッケルシリンダーの内壁にビスマス系の高温超伝導体を2週間かけてプラズマ溶射し、その後8日間にわたり熱処理を施した装置である。
従来の強磁性体のパーマロイを使った装置の実に1000倍の磁気遮蔽効果をもち、低周波領域でもその効果の落ちないことが確かめられている。
 「この装置については、金属材料研究所や各種企業の協力を仰ぎ、まさにチーム研究の成果といえますね。」 「この装置については、金属材料研究所や各種企業の協力を仰ぎ、まさにチーム研究の成果といえますね。」
脳磁界の検出のほうは、64個所で計測できる(64チャンネル)。1チャンネルにつき2個のクリーンリミット弱結合(SNS)接合が使われており、神経電流によって生じる脳磁場のごくごく微細な変化をとらえている(図5)。その計測結果の一例が右手首の正中神経刺激後にあらわれた磁場の分布である(図6)。分解能としても従来のSQUID脳磁界計測装置では雑音に埋もれていた5フェムトテスラ(200兆分の1テスラ)以下の計測を可能にしている。
「この装置は専用の磁気シールド室を必要としません。ですから、この装置を備えた移動検診車ができて、胃や肺の定期検診と同じように、気軽に脳の働きを調べる日が来るのも案外早いのではないでしょうか。そうすれば老人性の痴呆症の早期発見、進行防止が可能になるのではないかと期待しています。」
ジョセフソン接合の基礎理論の解明から応用に至るまで、太田客員研究員の若き日の夢とこだわりはどんどん現実化している。 |
| 文責: |
広報室 |
| 監修: |
表面界面工学研究室客員研究員
太田 浩 |
| 取材・構成: |
由利伸子 |
|
 |