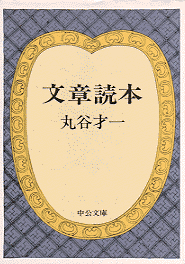 石川がここで語つてゐるのは、書くに値する内容がなければ字を書いてはいけないといふことである。この教訓は、文章においてさらによく当てはまるだらう。すなはち、記すに値することがあつてはじめて筆をとれ。書くべきこと、語るべきことがあるとき、言葉は力強く流れるだらう。これこそは人間の精神と文章との極めて自然な関係にほかならない。
石川がここで語つてゐるのは、書くに値する内容がなければ字を書いてはいけないといふことである。この教訓は、文章においてさらによく当てはまるだらう。すなはち、記すに値することがあつてはじめて筆をとれ。書くべきこと、語るべきことがあるとき、言葉は力強く流れるだらう。これこそは人間の精神と文章との極めて自然な関係にほかならない。
(p308)
|
|
じつにこれは敬服するべき所業といはざるをえない。と書いてしまいたくなるほど魅力的な本であった。装丁の絶望的なカッコ悪さのゆえに、古本屋でこのタイトルを見かけたときは躊躇したものだが、しかし頁を数回も繰るうちにたちまち釣り込まれた。すぐにレジに直行し、その晩から読みはじめて、先程までじっくりじわじわと読みつづけ、まさに今読み終わったところである。名著である。
「解説」の大野晋に指摘されているように(読了直後である。つい「やうに」と書きたくなってしまう)、私は丸谷才一を明確にではないが嫌っていた。文壇の古老であり旧字を使うスタイルを崩さない彼は、私にはあまりに保守的な存在に見えていた。大野晋が書いたように、斯くの如くにである――「世間には丸谷氏の国字問題に対する姿勢を一見しただけで、氏を目して復古的なあるいは反動的な思想の持ち主であるとしている人もあるように見える。」 しかし、この一冊を読むとその認識は否応もなく変質する。せざるを得ない。丸谷才一の深い洞察と文章の、そう、一見の字面からは連想不可能なほどの流麗さ・読みやすさは、ただわれわれを感嘆させるにとどまらない。論として深淵にして広大で、かつなによりもこの一冊は、文章を書くという現場にあたって「有用」なのだ。 もちろんそれは英会話学校的な、いってしまえば対処療法的な即効性をもった有用さではない。この一冊はぜんたいに丸谷才一の文章論であり、すなわち文章・文藝というものにたいしての思想が語られている。それを熟読し、玩味することによって得られる認識の深化は、あたかも漢方医学のように思考の枠組みを微妙に変革させるはずだ。
さて、最後にこの本の、きわめて重要な部分を一つ引用して紹介を終わろう。
もっと読まれていい一冊である。
Grade [ A ]
version.1.5.98.03.05. |