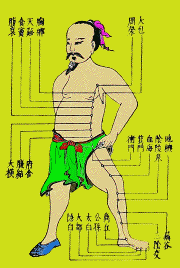
鍼灸治療について
築地書館:意釈皇帝内経霊枢の図に着色
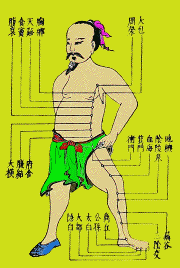
鍼灸治療の種類
古典的治療
現代(医学)的治療
鍼灸治療の適応範囲
得意とする分野
不得意な分野
適応を考慮するべき分野
注意点
感染の問題
折針の問題
その他
内出血(血腫)の対応
抜き忘れ防止について
鍼灸治療を紹介するに当たり、通常なら、その歴史から掘り起こして行くのが道筋かも知れない。しかし、今回はあえて実質的な話しから入りたい。何故なら、我々が問題とするのは、歴史的評価でなく、現実の医療場面での意味こそが問題となるからである。
鍼灸治療の種類 1-1
鍼灸治療は、その治療者が用いる手法、即ち、診断や診察方法、治療方法より、古典的治療と現代(医学)的治療に分けられる。
古典的治療
古典的治療とは、中国で体系化され日本に輸入され、さらに日本独自に発した鍼灸治療体系と言える。基本的には、脈診、腹診、舌診、切診と呼ばれる診察方法と補瀉と言われる治療方法が根幹を為す。
脈診について
脈診は、橈骨動脈拍動部の拍動状況を前腕下部橈側にて触知して、経絡の虚実やその変動を診る方法である。触知部位を橈骨茎状突起を中心に三個所設定することによって、対応する経絡がそれぞれ表と深で計12経ある。即ち、橈骨茎状突起を中心に示指、中指、環指を用いて橈骨動脈の拍動を診、少し力を入れて拍動が圧迫で止まる直前の深さと強さで触知した脈が沈脈であり、陰経の脈をこれにて診る。圧を弛めて浮かし触れなくなる直前の深さでの脈が浮脈であり、これにて陽経の脈を診る。さらに、その中間の位置で診る脈を胃脈と言い、別に分類している。他に、人迎脈診等もある。脈状の分類もかなりあり筆者は恥ずかしながら詳細には分からない。
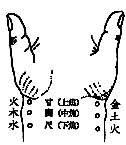
腹診について
腹診は、鍼灸だけでなく漢方でも重視される診察方法である。腹部の観察、触診を通して臓腑の異常を診るのである。腹診には幾通りかの見方があり、熟練を要する。基本となる自分のスタイルを持ち、セカンドオピニオンの意味で他の見方でも見直してみるという位に考えて、あれもこれもと混乱しない方が無難と思われる。
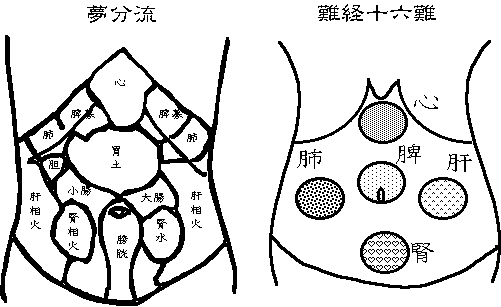
舌診について
舌診は、患者の舌の状態を観察して、その病態を把握する方法である。特に、舌質と舌苔を区別して観察する。アトラスなどの書物と熟達者の観察を参考に勉強するしかない。
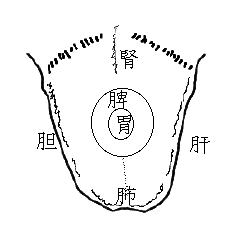
補瀉について
補瀉は、東洋医学的考え方に基盤を置く。その基本は、陰陽五行と相生相剋関係である。陰陽五行の理論は、理論というより世界観と言った方が適切かも知れない。即ち、生命、宇宙を構成する要素を、陰陽と木火土金水の五要素に分け、そこから全ての創造が始まると考える世界観である。
補瀉は、五行の運行法則から導かれる。相生関係は、木から火が、火から土が、土から金が、金から水が、水から木がと云うように、生み出して行く関係であり、例えば、木にとって水は母となり、木にとって火は子となる。相剋関係は、抑制していく関係である。即ち、金が実し過ぎると木を抑制し、水が実し過ぎると火を抑制し、木が実し過ぎると土を抑制し、火が実し過ぎると金を抑制するというように、働きが強すぎるために、他の要素に影響を及ぼすという関係である。

このような関係を元に、経穴の性質による補瀉と手技による補瀉がある。経穴の性質による補瀉とは、各経絡の中にも、木火土金水の性質をもつ経穴が定められており、経絡間の関係による補瀉と経絡内の経穴の性質を組み合わせて治療穴を選ぶのである。例えば、金(肺経、大腸経)の虚とみなされたとき、金の母である土(脾経、胃経)のなかの金の性質を持つ経穴、金に属する経絡中の金の性質をもつ経穴を用い、金の働きを抑制している、火(心経、小腸経、心包経、三焦経)の火の性質を持つ経穴を用いるのである。
東洋医学は全体のバランスを重視するという特徴を当に示す関係であると言えよう。しかし、近年、あまり詳細に拘りすぎ、術者の主観なのか熟練の問題なのかが曖昧となりがちな反省からか、微妙な感覚だけでなく全体を通しての比較、左右の比較、上下の比較など比較的捉えやすい観点で工夫した診方、治療法が研究されている。
現代的治療 トップ
現代的治療は、例を上げれば、疼痛部即治療部というような考え方を一部とる。軽傷な疼痛や障害がその部位の保護や処置で症状が取れる事は、日常経験する事である。従って、何でも、脈を診て、腹を押さえてというような方法を取る必要はないという考え方である。現代的治療では障害の由来や発症の状況と、患者の身体的愁訴との関連から、主たる治療部位は選ばれる。しかし、そのような中にあっても、あえて対側の同部位を刺激するとか、効果を促進するために腹部等の慢性的な症状(下痢とか便秘とか不快感、足腰の冷え)等にも目を向ける事は当然の事である。
鍼灸治療の適応範囲 1-2
適応に関する考え方 1
鍼灸治療の適応は幅広い。その為に、返って分かりにくい側面が生まれる。適応疾患を一つ一つ上げるよりも、何を対象としないかを上げた方が早い。
急性疾患、伝染性疾患、妊娠初期の婦人等は、現代では適応外と考えた方がよい。しかし、妊娠初期の婦人でも、薬を用いられないとか慎重に対応する必要のある状態などの時には、限定的に用いることは可能である。例えば、鼻炎とか肩凝り、不眠等である。書物には、赤痢とか盲腸炎等のに対する治療法が記されているものがあるが、今日では、特に先進国の我が国では急性疾患、伝染性疾患は対象としない。
無論、眼球、内臓、生殖器、創傷部等に直接鍼や灸を施す事は基本的にないし、教科書的にも禁忌とされている。
適応に関する考え方 2
適応疾患、症状であっても効果が期待しにくい場合がある。それは、炎症性疾患等での病勢の激しいときである。鍼灸の治療効果の出現にはある程度のタイムラグが有るために、取りあえず疼痛を止めるという様な処置には向かない事もある。また、症状とそこから類推される病態との間に大きなズレがある場合なども、効果が期待しにくい。それは、結果が示すところとなるが、患者や術者は凝りとか蓄積した疲労程度に考えていても、例えば、骨折などがある場合には、期待した効果は得られず、「どうしても痛みや腫れが取れないので、詳しく診てもらったら、骨折があった」等という事になる。
適応に関する考え方 3
疾患本体の治療にはならないが、周囲から補助的に鍼灸治療を用いる場合がある。例えば、末期患者の不定愁訴、吐き気の抑制等である。
適応に関する考え方 4
現代医学的に病態を把握できない症状に対して、対症療法的に用いる場合がある。心理的側面、社会的背景等を考慮するべき病態や、疾患本体と愁訴との関係が複雑に絡んでいる場合に、愁訴の方から治療を始めると、案外疾患本体の治療が進みやすい場合がある。
鍼灸治療の問題点 1-3
1、治療に場所と時間がかかる。
2、術者の力量に大きく左右される。
3、日本中どこでも同様の治療が受けられるとは限らない。
4、患者の好みや恐怖心によって、受診態度や効果に大きな差が出る。
5、施術料の基準があってないような、曖昧な部分がある。
6、保健適応が、不十分、不完全。
注意点
感染の問題
今日では、エイズ、肝炎等社会的にも注目される感染性疾患が出てきた。鍼灸治療では、灸自体はウィルス感染に関しては特に問題ないが、鍼は患者の体内に刺入するので、細心の注意が必要である。しかし、注射針と違い、鍼は中空でないために、鍼表面に付着した血液、その他蛋白質などをきちんと洗浄し薬物消毒、高圧蒸気長時間滅菌消毒の各段階を経ることで問題はない。しかし、肝炎等のウィルスキャリアの場合には、ディスポの鍼とかその患者専用の鍼を別に消毒しておく等の措置が望ましい。ディスポの鍼の普及が進みつつある。
灸療法では、灸痕部が化膿する場合があり、その為に瘢痕が非常に大きくなってしまう場合がある。灸の火傷部の清潔と自宅施灸時の消毒についてよく説明をしておく。問診時に、傷いたみしやすい体質か確認しておくことも必要。また、幼少期の施灸痕は皮膚の伸展により大きくなるので注意すること。

写真と上記説明は完全には一致していません。
折針・気胸の問題
鍼灸師が一番恐れる事故の一つが、鍼の切断、即ち折針である。埋没針法という故意に鍼を体内に埋め込んでしまう治療法がごく一部でなされている点から見て、折針そのものは考えようによっては、さほど害がないと思われがちである。しかし、埋没療法を受けたあとはしばらく痛みが持続しなれるまでには時間がかかる。しかも、埋没療法では、極細の金性の鍼を用いる。通常の治療には主にステンレス鍼を用いるから、鍼の硬さや太さの点から、折針すると患者はかなりの苦痛と不安を訴え、しばしば医療訴訟の対象になる。従って、古い鍼は用いない事、鋭角に曲がった鍼は用いない事、治療中の体動は注意しておく事が必要である。

写真と上記説明は完全には一致していません。
気胸は起こりうる医療過誤の一つである。しかし、実際には頻繁に起こることはない。患者の骨格の発達具合の観察や触診を行うこと、過去に気胸の経験や肺気腫等の既往の有無の確認、そして、肩背部の施鍼には細心の注意を払い、深い鍼はしないことである。斜刺でも十分効果はある。
出血の問題
鍼治療部に出血を見ることは希ではない。出血と言っても点状の出血である。しかし、頭部や後頸部等では、注意しないと衣服やシーツに流れる出血を見ることがある。原因は血管の損傷であるが、それ自体はさほど問題はない。出血部位を確認して酒精綿等でしっかりと圧迫止血を行えばよい。顔面部などでは、皮下に拡散しないように少し搾るようにして出血をむしろ促し、出血量が少なくなれば圧迫止血を行う。部位によっては、血腫を創ることがある。鍼の抜去後少し時間が経過いてから気が付くこともある。軽く圧迫し、マッサージを行い周囲に血腫を散らせるとよい。ほっておくと血腫の圧迫が新たな痛みなどに結び付くことが懸念されるからだ。出来れば、患者に出血した旨伝え、後で紫色になるけど、1〜2週間で治るから「ごめんなさいネ」とさらりと説明する。

肩関節痛の為に多くの灸治療を患者本人が行った灸痕が多数見られる。
写真中央やや斜め右上の肩関節の前側の青紫の出血痕は鍼治療時のもの
鍼の抜き忘れ
鍼の抜き忘れは、「うっかり」しやすい盲点である。衣服の影、バスタオルの影等に注意したい。
以上
ご参考までに。
トップ
付録
鍼の点検
鍼を再生して用いる場合、鍼の傷みを観るために、酒精綿でしごくようにして擦ると、鍼体の傷に綿花の線維が引っかかり、鍼先が抜ける時に、酒精綿に抵抗を感じる時がある。その様な鍼は、傷があるか鍼先が鋭角に曲がっているから、直ちに廃棄する。顕微鏡で傷を検査・確認する事もあるという。
超音波洗浄器の利用
眼鏡洗浄用の超音波洗浄器を用いる事が出来る。
伝承医学の一面
科学的と言えば聞こえが良い。しかし、鍼灸治療には伝承的側面もある事は事実だ。そうは言いながらも、そのような高名な師匠に弟子入りできる人は一握りであるし、全てが受け継がれると言う保証はない。結局は、病める人一人を如何に治療するかという事に尽きる以上、そこにはどうしても、その人に治療を受けられる人と受けられない人と言う一種の不公平が生じる。鍼灸治療を医療と観るなら、より多くの求める人に等しくその効能を示すようにする責任が我々にはある。ここに、鍼灸療法に内在する矛盾点がある。
即ち、術としての側面と、医療としての側面である。どちらにしても、日々の研鑽と謙虚な態度を忘れてはなるまい。
To Master