(3)梁のたわみ -ヤング率の測定-
実験目的
両持ち梁の中央に荷重をかけると梁はたわむ。この時、たわみ量は梁の形状とヤング率のよって決まる。従って、たわみ量を測定することによって、その材料のヤング率を知ることができる。このようなヤング率の測定法はユーイング
(Ewing)法と呼ばれ、この方法を用いて実際の材料のヤング率を測定することを目的とする。
実験方法
(1)図のように、測定装置のナイフエッジの上に試料棒と補助棒を起き正確な中央に鏡の中足が乗るように“おもりかけ”をつるす。
(2)読みとり望遠鏡をのぞいて、鏡の中の写っている目盛りに焦点を合わせる。この操作を簡単にする方法は最初望遠鏡を通さないで鏡に写っている目盛りを探し、その目の位置へ目盛りを見失わないようにしながら望遠鏡をもってきて望遠鏡の中に目盛りをとらえる。
(3)“おもりかけ”におもりを一つずつ乗せて目盛りを読む。この操作は静かにやらなければ目盛りの揺れが生じて測りにくくなる。
(4)7個のおもりについて全部測定したならば、次におもりを一つずつはずしながら目盛りを読んでいく。そして、全部はずした時に最初の目盛りに戻っているのを確かめる。もし、実験の途中で鏡などがわずかでもずれると、目盛りは元には戻らない。その場合、最初から測定をやり直さなければならない。
(5)寸法測定。厚さ
(a),試料棒の幅(b),ナイフエッジ間の距離(L),鏡~目盛間の距離(x),鏡の前足~後足二本の中央間の距離(z)。(6)補助棒を新たな試料棒として
(3)~(5)をおこなう。(7)以上のようにして、用意されている三本の試料棒(鋼鉄,真鍮,銅)のヤング率(縦弾性係数)の測定をおこなう。
実験結果と課題
(1)片持ち梁と両持ち梁の“たわみ
(e)”を「曲げモーメント」の式から導く。 たわみ曲線状に微小長さ![]() をとり、P,Qにおけるたわみ角をそれぞれ
をとり、P,Qにおけるたわみ角をそれぞれ![]() ,
,![]() とすれば、
とすれば、![]() は近似的に円弧とみなされるから、その曲率半径をRとすると、
は近似的に円弧とみなされるから、その曲率半径をRとすると、
![]()
上式の符号は図のようにP点が正の方向に進むに従い、角![]() は減少するために用いた。
は減少するために用いた。
上式より、
![]()
P,Qのたわみの差を![]() として、たわみ角θが小さいならば、
として、たわみ角θが小さいならば、
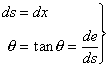
![]() ‥‥①
‥‥①
①式と、曲げモーメント![]() の関係から、
の関係から、
![]() ‥‥②
‥‥②
式②がたわみ曲線を表す微分方程式で、Iは中立軸に関する断面二次モーメント,Mは中立軸のまわりの曲げモーメントで、xの関数として与えられる。
![]()
![]()
ただし、![]() は積分定数である。
は積分定数である。
(a)
片持ち梁 ![]() であるから、微分方程式は、
であるから、微分方程式は、
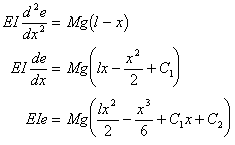
積分定数![]() は固定端の条件、
は固定端の条件、![]() で
で![]() ,
,![]() から、
から、
![]()
![]()
最大たわみは自由端で生じ、
![]() ‥‥③
‥‥③
式③において、Eは材料の種類により、Iは断面の形で決まるが、![]() が同じなら、EIが大きいほどたわみeは小さい。
が同じなら、EIが大きいほどたわみeは小さい。
(b)
両持ち梁 図の場合、AC間![]()
![]()
CB間![]()
![]()
AC間
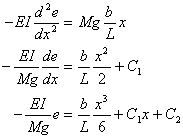
CB間
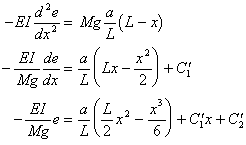
![]() はつぎの条件から決められる。
はつぎの条件から決められる。
(ⅰ)両支点におけるたわみが0である。
(ⅱ)荷重点Cでは、AC間,CB間を別々に計算したたわみ及びたわみ角が等しい。
(ⅰ)の条件はAC間において、![]() で
で![]() から
から![]()
CB間において、![]() で
で![]() から、
から、
![]() ‥‥④
‥‥④
(ⅱ)の条件は
AC間で、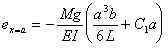
CB間で、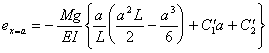
であるから、
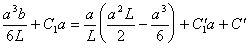 ‥‥⑤
‥‥⑤
また、AC間で、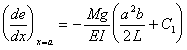
CB間で、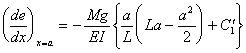
であるから、
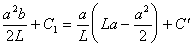 ‥‥⑥
‥‥⑥
式④
,⑤,⑥を整理して連立させると、![]() ‥‥⑦
‥‥⑦
式⑦をそれぞれAC間・CB間のたわみの式に代入すると、
AC間![]()
![]() ‥‥⑧
‥‥⑧
CB間![]()
![]()
そして、スパン中央のたわみは、式⑧で![]() とおいて、
とおいて、
![]()
さらに、荷重がスパン中央に作用する場合、たわみ曲線は左右対称となり、左側半分に着目して求めればよいことになる。式⑧で![]() とおき、
とおき、
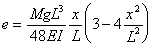
![]()
この場合の最大たわみは、
![]()
となる。
(c)
曲げモーメントの証明![]()
上式より、![]()
力のモーメントより、
![]()
断面全体における力のモーメントは、
![]()
![]() ‥‥断面二次モーメント
‥‥断面二次モーメント
断面全体における力のモーメントは、断面の形状によって決まることがわかる。
よって、曲率半径Rだけ曲がっているときの曲げモーメント。
![]()
(2)光のてこ
(Optical Lever)の原理 鏡Mが角度φ回転すると、反射光線の方向は2φ変化する。これを測定するには、スケールSをMに写し、その反射像を望遠鏡Tで見る。実際は、試料の変位による望遠鏡の十字線の交点の読み(スケールS上での)の移動![]() として、読み取ることができる。
として、読み取ることができる。
スケールと鏡の間の距離をxとすると、
![]()
の関係がある。φが小さければ、
![]() ‥‥⑨
‥‥⑨
となる。
図は、三脚IJKに鏡Mをつけたもので、これを光りてこと呼ばれる。JKを結んだ線上を軸としてIが上下に動くとMは回転する。
IからJKまでの垂直距離をzとすると、
![]() ‥‥⑩
‥‥⑩
となるので、式⑨
,⑩より、![]()
となる。この式から、小さい変位eは
(
(3)測定結果を以下のようにまとめる。
・1回目
(a=0.0045[m],b=0.01604[m],x=1.620[m])|
荷重 [kg] |
目盛 (増)[mm] |
目盛 (減)[mm] |
平均目盛 [mm] |
荷重 [kg] |
目盛 (増)[mm] |
目盛 (減)[mm] |
平均目盛 [mm] |
0.8kg の目盛変化 |
|
0 |
290 |
290 |
290 |
0.8 |
196 |
196 |
196 |
94.0 |
|
0.2 |
267 |
267 |
267 |
1.0 |
173 |
173 |
173 |
94.0 |
|
0.4 |
243 |
243 |
243 |
1.2 |
149 |
149 |
149 |
94.0 |
|
0.6 |
220 |
219 |
219.5 |
1.4 |
126 |
126 |
126 |
93.5 |
|
平均 |
93.875 |
1回目の寸法測定
![]()
![]()
・2回目
(a=0.0045[m],b=0.016[m],x=1.610[m])|
荷重 [kg] |
目盛 (増)[mm] |
目盛 (減)[mm] |
平均目盛 [mm] |
荷重 [kg] |
目盛 (増)[mm] |
目盛 (減)[mm] |
平均目盛 [mm] |
0.8kg の目盛変化 |
|
0 |
200 |
200 |
200 |
0.8 |
153 |
152 |
152.5 |
47.5 |
|
0.2 |
188 |
188 |
188 |
1.0 |
141 |
140 |
140.5 |
47.5 |
|
0.4 |
176 |
176 |
176 |
1.2 |
129 |
129 |
129 |
47.0 |
|
0.6 |
165 |
165 |
165 |
1.4 |
117 |
117 |
117 |
48.0 |
|
平均 |
47.5 |
2回目の寸法測定
![]()
![]()
・3回目
(a=0.0045[m],b=0.016[m],x=1.590[m])|
荷重 [kg] |
目盛 (増)[mm] |
目盛 (減)[mm] |
平均目盛 [mm] |
荷重 [kg] |
目盛 (増)[mm] |
目盛 (減)[mm] |
平均目盛 [mm] |
0.8kg の目盛変化 |
|
0 |
330 |
329 |
329.5 |
0.8 |
240 |
239 |
239.5 |
90.0 |
|
0.2 |
308 |
307 |
307.5 |
1.0 |
218 |
218 |
218 |
89.5 |
|
0.4 |
285 |
284 |
284.5 |
1.2 |
196 |
195 |
195.5 |
89.0 |
|
0.6 |
263 |
261 |
262 |
1.4 |
174 |
174 |
174 |
88.0 |
|
平均 |
89.125 |
3回目の寸法測定
![]()
![]()
・それぞれのヤング率Eを求める。
今回の実験で用いたはりは両持ち梁なので、先ほど求めた両持ちはりの式を用いる。

ここで、光てこの原理で求まった式を適用して、
![]()
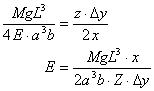
M
=0.8[kg],g=9.8[m/s2],L=0.4[m],z=0.03[m]x
=スケールと鏡の距離[m],a,b=それぞれの値[m],Δy=目盛の変化の平均値[m]
上記の値と実験より求まった値を用いて計算すると、
1回目
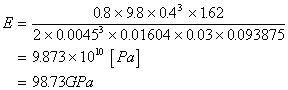
2回目
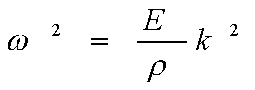
3回目
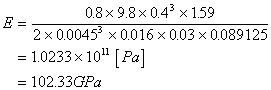
(4)3本の試料棒のヤング率を文献値と比較・考察する。
|
実験値 |
文献値 |
材質 |
|
|
1回目 |
98.73GPa |
91 ~96GPa |
真鍮 |
|
2回目 |
194.41GPa |
203 ~211GPa |
鋼鉄 |
|
3回目 |
102.33GPa |
103 ~130GPa |
銅 |
実験値をもとに文献値を調べるとこのようになる。
多少ずれてはいるが、ほぼその材質ということができる。
感想・考察
今回の実験では最初は、鏡がずれるなどの細かいトラブルなどで時間を使ってしまった。それでも簡単に鏡は修理され、実際に実験が始まると順調に進んだ。
今回の実験で、材料力学などでよく使う『E』がどのようにして求められたかよくわかった。計算結果の値はそれなりに近い値になったと思う。
今回の実験では、SI単位系を用いて計算をしたがよかったのだろうか。
たわみの式を導くところで、曲げモーメントの説明もなしに進めて後からその部分を補っておいた。今度からは順序よく導くように心がけようと思う。