
「神様の木」 No.1
神様の木 渚 水帆
あらすじ
ネロとカイトは、同じ神学校に通う6年生、2人とも最終学年で、学校でも優等生で有名なネロは来年の春から遠くの進学校に進むことが決まっている。
ヤン先生の授業に感銘を受けた2人は、この夏の思い出つくりに村はずれのドーンの森で1晩のキャンプをする計画を立てる。
ドーンの森には古くからの言い伝えがあって、白いふくろうを見た夜には、森のすべての木々に明かりが灯るという。
進学校で1番の老教師、ヤン先生は、ちょうどネロとカイトと同じ年の時にドーンの森で神秘的な体験をしたという。
植物の声を聞いたというヤン先生の言葉を確かめるためと、来年の春になると離ればなれになるネロとカイトの友情を暖めるためのひと夏の冒険でもあった。
2人ですべて計画を立てて、食料品などの物質を買い出しに行く。すべて初めての体験でネロとカイトはわくわくしていた。
キャンプの初日、ネロとカイトは森の散策に出かけ、森で一番大きな「神様の木」を見つける。カイトは、いたずら心で神様の木にナイフで傷をつけてしまう。
夜になって、カイトはネロに昼間見た「神様の木」をこれから見に行こうと誘う。
カイトとネロは懐中電灯の光を頼りに、夜の森を彷徨う。
そこで2人の見たものは───。
![]()
−1−
「植物は人間の考えていることが分かるんですよ。これが確かな学説です」
ヤン先生が教壇から熱弁をふるう。
「ある学者が調査した論文からの引用なのですが、植物の前でハサミを持って『ちょん切るぞ、ちょん切るぞこれからお前をちょん切るぞ』と唱えると、植物の方から『切らないでわたしを切らないで』というように、ある一定の乱れた周波が測定されます。
その時、逆に『だいじょうぶ、もうお前を切るのを止めにする』と唱えると、その乱れた周波は、すーっと水が引くように、正常な周波数に戻るらしいです」
カイトの隣の席に座った、優等生のネロが感嘆の溜め息ををついた。
「この一種、テレパシーのような現象をひらめきの光に似た言葉で『シャイン』と呼ぶことにする」
−2−
ヤン先生は文献を片手に、黒板に大きく、「SHINE」と英語で書いた。光る・輝くの意味と注意書きが横に書かれた。
黒板をノートに写す鉛筆の音だけが、しゃかしゃかしゃかと教室中に響いていた。
授業が終わった後、ネロがヤン先生に質問をした。
「先生、どうして植物は人間の考えてることが分かるのに、切られたくないというちゃんとした意志があるのにも関わらず、口に出して言わないのでしょう。どうして、植物は口がきけないのですか」
ヤン先生は黒板の眼鏡の奧から、しげしげとネロの顔を見つめていた。
それから、教室の窓から遠くの方の山を眺めながら、
「きっと植物は本来、穏和な性格でな、私の思うにはだな、言い争い、無駄な暴力を好まないのだよ」
−3−
そう言って、窓をガラリと開けた。
ひとひらの風に混じって、木の葉が数枚、教室の中に舞い込んできた。
「この校庭の大木も何百年、私達を見守っているんだろうね」
そう言って、ヤン先生は自分の一言一言を、ひとつ残らず聞き逃すまいと耳をそばだてているネロの小さな肩を抱き寄せた。
「きっと、木々は私達よりずっと穏やかな雄大な時間を過ごしているのだろう。一人の人間が生まれて死んでいくその何十倍もの時間をずっと見守ってくれている。そう思わないかい」
ネロは大木の葉が風にそよぐのを、何も言わずにじっと見ていたが、
「でも、先生、やっぱり納得いきません。なぜ、木はもっと快適な場所に自ら移動しないのでしょう。ずっと同じ場所で、変わらない景色をずっと眺めている。同じ場所に、深く深く根を張ったまま」
−4−
ネロはじっと答えを待っていた。
ヤン先生は、ふうっと深く息を吐いた後で、
「木は自分の種が落ちた場所を、きっと天命だと悟っているのだよ。例えば、ネロがこの国に生まれて、この国の言葉をしゃべって、この国の食事を愛するのと同様にね」
ネロがしばらく考えた後、
「天命ってどうやって決まるのでしょう」
「きっともう生まれる前から、あらかじめ決まっているのさ、偉大な『力』によってね」
「それは『神』というものなのでしょうか」
「どうだろうね。国によっても宗教によっても神の姿はそれぞれに異なる。荒々しい神もいるし、優しい女神のような神もいる。極端な話、ある文化では神であるものがある文化に行けば反対に邪悪なものかもしれない」
「先生は博学ですね」
「なになに。たいしたことはない」
ヤン先生は、真夏なのに淡いグレーのトレンチコートを羽織った。
−5−
「年をとると、風も骨身にしみる」
ネロとカイトとヤン先生は一緒に校門を出て歩き出した。
「これから長い夏休みが始まるし、君たちはもう最後の学年だから、思い残すことなく遊べばよいし、人生について色々考え悩めばよいし、答えは一つでないし、最初から与えられた答えなどなにもないのだよ。
数世紀前に正しいとされた学説も、新しい世代になって、また新しい学説に次々に塗り替えられていくし、そうならなければならないのだ」
ネロとカイトは顔を見合わせて笑った。
この夏は2人でキャンプに行く約束をしていたのだ。この学校でも優秀なことでひときわ有名なネロは来年の春にはひとりみんなと離れて私立の進学校に進むことがもう決まっていた。
「もうこの村で過ごす最後の夏だから、しっかり日焼けするくらい遊びますよ。新学期に会うのを楽しみにしていて下さい」
−6−
元気そうなネロの顔を見て、ヤン先生も微笑んだ。
「ネロは生真面目すぎるところがあるし、物事を深く考えすぎる。突き詰めて考えるところは悪くないのだけれど、たまには普通の子供に戻って思いっきり太陽の下で遊ぶがいい」
「先生は子供の頃は、どこで遊んでいたんですか」
カイトの無邪気な質問に、
「私の小さな頃はね、村はずれのドーンの森でよく遊んでいたよ。もちろん夏にはテントを張ってキャンプもしたし、小川では魚釣りもした」
ヤン先生は久しく目を細めて、なつかしい笑顔を見せた。
「ドーンの森、あんな遠いところまで遊びに行ってたんですね」
「今と違って、昔はもっと緑も多くて、空気も水も綺麗だった。残念な話だが……けれどやはり人類の文化はもっと進歩をしなければ
−7−
ならんのじゃよ」
「これ以上ですか」
驚くカイトに向かって、
「そうじゃよ。進歩をやめた文化はすぐに退廃の道を辿る。この村でも、今までにいくつの工場が潰れたことか」
ヤン先生は、もう煙の上がっていない煙突を1つ2つと指を折って数えかけて、途中で止めた。
「ところで、今日の先生の授業なんですけど。先生はどうして学者の最新の論文なんか引き合いに出して、植物の思考について論じだしたのですか。いつからそういう風に考えるようになったのですか」
ネロの質問に、ヤン先生は村はずれのドーンの森の方角を遠い目でしばらく見つめていたが、
「先生が若い頃。そう、ちょうど君たちと同じくらいの年に、確か学年最後の年だった。ドーンの森で神秘的な体験をしたのじゃよ」
−8−
しばらく経ってから、ヤン先生が重い重い口を開いた。
2人はしばらく息を呑んだ。
カラスが数羽、カアカアと声を上げながら夕焼けの空に消えていった。
ドーンの森は赤い空に暗く映っていた。
「その時にな、先生はある声を聞いたのだ」
うんと頷くようにして、ヤン先生はネロとカイトの顔をじっと見つめた。
その瞳は、知恵の光が宿っているかように一筋の明るい光がいつも前方を照らしているかのようだった。そして、いつも思慮深そうに眉間を寄せるその広い額には、大木の年輪のように幾重もの皺がその生きてきた歴史を刻んでいた。
「いちど、ドーンの森に行ってその私が若い頃に聞こえた声を聞いてくるとよい。森の中では授業では学べない自然の声がたくさん聞こえるのだから」
ヤン先生は、十字路のところまでくると、
−9−
山吹色の山高帽子を深く被って、
「じゃあここで」
と言って門の中に姿を消した。
ネロとカイトはしばらくの間、ヤン先生の言った言葉について考えていたが、いつも楽しいことばかりを提案して、みんなを喜ばせることが天才のカイトが口を開いた。
「ねえ、ネロ。今年はさ、2人で過ごす最後の夏休みなんだからさ、前から言ってたキャンプをさ。ヤン先生が僕たちと同じ年の頃に神秘的な体験をしたドーンの森でするっていうのはどう?」
ネロも今度は嬉しそうに笑った。
「いいね。今年は最高の夏にしようよ」
2人は手をたたき合って笑った。
次の日は、2人で一緒にキャンプ用品をそろえに町に出ていくことにした。
クラッツ通りは、日常品から野外用品まですべてそろう有名な市場だ。
−10−
そこで、ネロは赤いリュックを買い、カイトは青いリュックを買った。あと、非常食料品としてチュナの缶詰と桃の缶詰、鳩マークの板チョコを2枚買った。
「雨が降ったときはマットがいるよ」
カイトが言い出して、2人は銀色のマットを買った。
「ほかに何かなかったかな」
「テントはうちの親父のを借りることにしてるし、ほら、虫よけスプレーなんかもいるよな」
大きな藪蚊のマークの虫よけスプレーと、万が一のためにガーゼと包帯も買った。
「そうそう、それから一番大事な自炊の用具」
カイトがネロを引っ張るようにして、隣の店に入っていった。
「ガスコンロは燃費のよいのを買わないと、一生かかってもご飯が炊けないんだぜ。うちの親父が言ってた」
カイトがいつになく真剣な眼差しでコンロ
−11−
選びをしている。
「飯合もいいのを選ばなくちゃ」
結局、深緑色のいかにもご飯がよく炊けそうな大きめのコンロとガス缶2つ。黒くて丸みのあるブーメラン型の飯合2つに、直火にかけられるアルミのお皿を2人分買った。
「レインコートもついでに買っておこうか」
今度も、ネロが赤いレインコートを買い、カイトが青色のレインコートを買った。
これでほとんど準備は揃った。
「いよいよだね」
「明日は、野菜なんかの食料を買い出しに行こう」
ネロとカイトはこの日も笑い合って別れた。
次の日は、新鮮な野菜とうま味のある肉で有名なフレッシュアワー食料品街でキャンプの食料を調達することにした。
ネロが野菜好きでカイトが肉好きだったので、お互いに買う役割を分担することにした。
−12−
ネロが好きな野菜は、じゃがいもに人参、ピーマン、コーンに半分に切ったカボチャ。とれたてのトマトにキャベツとレタス、なすびとタマネギを買い物かごの中に入れた。
「これだけあればシチューと、バーベキューにサラダができるよ」
「それじゃ、シチュー肉とバーベキュー用の肉と、サラダに入れるハムを買わないとね」
カイトがシチューの角切り用の分厚い肉片と、バーベキュー用の火が通りやすい適当に脂身のある赤肉を買い。最後に薄切りハム5枚セットを買った。
「おいしそうだろ」
カイトがバーベキューの串で、じりじり焼けていく肉をひっくり返して、脂身が溶けてじゅーっと音を立てるところをネロに想像させた。
「うまそうで、たまらないな」
ネロとカイトは、ぱちんと手を鳴らした。
「朝食用のパンと牛乳も買おうよ」
−13−
デイリー牛乳の白に黒ぶちの牛のラベルのパックをしげしげと眺めた後、買い物かごの中に入れた。
パンは普通の5枚切りの食パンと、レーズンパンを選んだ。
「キャンプのごはんはおいしいぜ」
カイトが舌なめずりをした。
「いよいよ明日出発だな。朝8時に学校の校門前で集合」
分かったというように、ネロが手をあげた。
「包丁とまな板は家から持ってくる」
「まかしたからな」
ネロとカイトは笑顔で別れた。
次の朝、天気は良好でキャンプ日よりだった。
カイトはお父さんから借りた黄色のテントをナップサックに詰め込んで、ネロと一緒に買い込んだ食料品の入った青い自転車の荷台にくくりつけた。
必要最低限の着替え(トレーナー数枚、T
−14−
シャツ数枚、下着数枚)と洗面道具一式(歯磨き、タオル、石鹸)をネロと色違いで買った青のリュックの中に詰めて背中にしょった。
自転車に乗ると、その重みで左右に揺れそうだったけれど、少し走るともう大丈夫だった。
まっすぐ走るには少しスピードがいるね。
カイトは集合場所目指して一目散に青い自転車をこいでいった。
校門の前では、もうネロが待っていた。
ネロの赤い自転車の荷台には、ガスコンロにバーベキュー用の薪、簡易食器一式、大きなペットボトルの水がくくりつけられていた。
「準備完了」
「出発進行」
2人は元気に笑顔を交わした。
真夏の朝の太陽は、これからじりじりと地面を焦がしながら上昇していく前の、不思議な静けさに満ちていた。
清々しい朝だ───。
咲夜さん作
−15−
カイトの青い自転車とネロの赤い自転車は寄り添いながら、村はずれのドーンの森に向かって進んでいた。
2人がドーンの森に着いたのは、正午過ぎだった。森の中では、見たこともない鳥が空高く飛び、小動物の足跡があちこちに残されていた。
ネロとカイトはテントを張る場所を探してしばらく森の中を歩き回っていた。
結果として、小川からはほどよく近い地面の乾燥した平らな場所を選んだ。
テントの四隅をきっちりと張って、中に重しを兼ねて食料品を入れた。
「これで大丈夫」
カイトが青いトレーナーの袖をたくしあげてガッツポーズを作って見せた。
気持ちよいそよ風が、小川のせせらぎと共にそよいできて、ネロがまっ白なタオルで顔の汗を拭った。
「せっかくだから森を散歩してみようか」
−16−
カイトの提案で、必要最低限の物だけそれぞれのリュックに背負って、真昼のドーンの森の中を散策に出かけた。
小鳥の鳴き声があちらこちらから響いてきて、動物好きのカイトが、あれはヒヨドリ、それはツグミ、あっちはムクドリ、あそこをちょこんちょこんと飛んでいるのはセキレイと楽しげにネロに説明してみせた。
ネロは真剣にカイトの鳥の説明を聞いていた。
「夜になるときっと白ふくろうが見られるよ」
それを聞いたネロは素直に喜んでいた。
この村では、白ふくろうはひとつの伝説になっていた。
ドーンの森に白ふくろうが現れると、木々に松明かりのような光が灯るとという伝説。聞くところによると、ネロたちの祖父のもっと先の代からの言い伝えだそうだ。
「楽しみだね」
ネロが大きな樫の木の下で、そっと囁くよ
−17−
うな口調でカイトに言った。
今夜、ネロとカイトの2人だけでドーンの森でキャンプをすることは、実は両方の親にも秘密にしている。
ネロもカイトも学校の林間学校のような行事で多数でキャンプに行くと親にわざと嘘をついてきた。
今夜、2人だけの秘密が出来る───。
小川の水はひんやりして冷たかった。肘までの腕を小川の水で洗い、登山靴を脱いで足の指を川底の小石の上で広げた。
5本の指の間を、小川の自然の水が勢いよくすりぬけていき、ネロは危うくバランスを崩しそうになった。
あっと声を上げるより早く、ネロの小さな肩をカイトの日に焼けた褐色の力強い腕が、しっかりとつかんでいた。
「この辺の流れは速いから気をつけろよ。何年か前に小さな子供が溺れ死んでいる」
−18−
ネロは、ドキドキする鼓動を抑えきれないまま、急に速度を増した小川の水の流れに耳をすませていた。
自然の力をあなどってはいけない───。
カイトの力強い目がそう告げていた。
「ありがとう、カイト」
ネロは一足先に小川から岸に上がって、体をタオルで軽く拭いてカイトに渡した。
カイトはタオルを無言で受け取った。
テントに戻った2人は、今度は黙々とバーベキューの用意を始めた。
ネロは持ってきた包丁とまな板で、手際よく野菜を刻むついでに、固いかぼちゃを火が通りやすいように数ミリの厚さに切っていく。タマネギはくし型に切り、なすびは輪切り、キャベツは手で簡単にむしって置いておいた。
一方、カイトの方はというと、同じくらいの大きさの握り拳3つ分くらいある石を等間隔に立てて、その間に持ってきたガスコンロ
−19−
にマッチで火をつけた。
鍋にうすく油をぬり、赤みの肉を焼いた。
油がじゅうじゅうと煙に混じって焼ける匂いがドーンの森中に漂っていた。
「外で食べるご飯はなんでもおいしいな」
カイトがまっ先に肉にかぶりついた。
肉のたれがカイトの口のまわりにべったりとついて、めんどくさそうにカイトは口元を手で拭った。
「野菜もちゃんと食べないとだめだよ」
ネロがそんなカイトを見て笑った後、カイトのお皿にかぼちゃとタマネギとコーンを入れた。
「偏食はだめだよ。食に偏るって書くんだ。バランスよく食べないと血が汚れるし、体の調子が悪くなるよ」
ネロが網の上のだんだんすすで黒くなっていく寸前の野菜を全部まとめてカイトのお皿の上に注いだ。
「このなすびはまだ生焼けだ。口の中でもさ
−20−
もさする」
ひとり苦しそうにしているカイトをネロは愛おしそうに眺めていた。
「ごめんな」
「いいよ」
カイトはネロの前で、長い舌をべーっと出して見せて、やっぱり生の野菜は食えないと笑った。
食事の後は、森の木々に沿った小道を歩いた。昔はこの小道を行商の人が毎日行き来していたらしい。村と村をつなぐ物質はこの小道を抜けて山を越えて民家に届けられた。
カイトがこの森で一番の大木を見つけた。
どこか神々しい趣のその大木は神様の木と先人から讃えられていたらしく、根本に小さな石の碑が建てられていた。
「神様の宿る木なんだね」
ネロが石碑に書かれてある小さな字を、長くて繊細そうな指で触れながら、ドーンの森
−21−
で一番の大木を仰いでいた。
ネロが「神様の木」の大きな幹ににそっと耳を当ててみた。
「神様の木の考えていることが分かる?」
カイトが尋ねた。
2人はヤン先生の授業の植物に宿る光についてじっと考えていた。
「どくんどくんいう音が聞こえてくるような気がする」
ネロが答えた。
「鼓動のような音」
カイトがいつの間にか、ジャックナイフを青いトレーナーのポケットから取り出していた。
「切るぞ。切るぞ。お前を切っちゃうぞ」
カイトがまるで舞台役者のように脅す口調で「神様の木」に向かって叫んだ。
いきなりその場の空気が、しーんと静まり返って緊迫したきりりりという微かな音が聞こえたような気がした。
−22−
「切らないで、切らないでって」
ネロが大木に耳を当てたまま、目をそっと閉じた。
「生きているんだね、森も木も」
「うん」
大木の生い茂った葉の隙間から優しげな木漏れ日が一筋、不意に射し込んできて、目を閉じたネロの安らかな横顔を照らし出した。
ネロの横顔はやさしい影を落として、まるで精密な造りの白亜の人形のように美しかった。
カイトはそっと、手に持ったジャックナイフをネロの顔のすぐ近くの枝に、ためらいがちに刺した。
ネロは、まだ目をつむっていた。
カイトに刺されたばかりの「神様の木」の小枝からは勢いよく樹液が滴っていた。
カイトは宗教の時間に習ったキリストの血について思いを馳せていた。
甘い液のような「神様の木」の樹液には、
−23−
オオクワガタやカブトムシがいつの間にやら多数群がっていた。
ネロの整った小高い鼻の上に、カイトは手に持ったオオクワガタを乗せてみた。
ネロはびっくりしたように目を開けると、カイトのいたずらを笑ってゆるしてくれた。
「刺しちゃったんだね」
かわいそう……ネロはカイトが刺したばかりの大木の小枝を愛しそうにさすった。
そして、リュックの中から水を取りだして一杯飲んだ後で、捕まえたばかりの2匹のオオクワガタで決闘をさせて遊んだ。何回しても、カイトの方のオオクワガタが優勢だった。 2人は時が経つのを忘れて、ドーンの森中で心ゆくまで遊んだ。
赤い夕焼けが迫ってきた頃、カイトが一人で晩御飯のシチューを作るからと言い出した。
ネロはそれならと、木に吊したハンモックの中に横になった。
−24−
カイトが手際よく、シチュー用の肉を刻んでいくのを見て安心したのか、ネロは持ってきていた外国語の活用表にハンモックの中でざっと目を通し始めた。
来年の春から通う、新しい神学校でちゃんと授業についていけるようにとネロはカイトに断った。
「ネロだったら大丈夫だよ」
とカイトは言った。
しばらくして、「痛い」というカイトの短い悲鳴がドーンの森中を木霊した。
ネロはハンモックの上から起きあがって、カイトの顔を見た。
まな板の上では、シチューの肉片が散乱していて、カイトのよく日に焼けた人より大きな親指から真っ赤な血がぽたりぽたりと白いまな板の上に滴り落ちていた。
「大丈夫、カイト」
ネロがそばに駆けよって、カイトの親指の根本をしっかりと布でしめつけた。
−25−
「これですぐに血が止まるから」
持ってきた携帯用の救急箱からガーゼと包帯を取りだしててきぱきとカイトの親指に巻きつけた。
「しばらくその切り株の上にでも座ってじっとしていて」
カイトは痛みを堪えながら、黙って切り株の上に座った。
「あとは僕が作るから」
ネロがなべに薄く油を引いて、シチュー用の肉を炒めだした。
野菜をことんことんと刻む音が、テンポよく聞こえてくる。
カイトは近くにあったネロの新しい外国語活用表を見て、
「上の学校で、こんなわけの分からないことをしないといけないんだったら、僕はもう勉強なんかやめて町工場でも働こう」
と言ってネロを笑わせた。
「来年になったら、お互い離ればなれになる
−26−
んだよね」
カイトがつぶやいた。
「うん」
とネロは答えた。
「だから、こうやって2人っきりでキャンプする計画を立てたんだったじゃない」
「そうだよな」
カイトとネロは目を合わせて、くすくすっと笑った。
「さびしくなるよな」
「先のことなんかどうなるか分からないよ」
ネロがタマネギを刻みながら答えた。
肉の焦げるじゅーという音で、ネロはおなべに水を注いだ。
「ずっとネロと一緒にいたいな」
カイトはつぶやくように言った。
「うん、ずっとね」
そう言ったきり、ネロは黙っていた。
それぞれの巣に帰る小鳥のさえずりと、大きな夕焼け空が2人の心を支配していた。
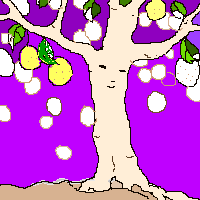
鈴蘭さん作