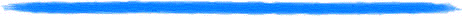
官公庁の規制緩和の必要性
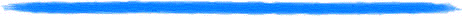
役人の仕事の非効率性は、いろんな人が話題にしてる。彼等の仕事はとにかく遅い。競争すべき相手がいないと、当然組織はフットワークが鈍る。保身の為に余分な仕事を作る。一度できた仕事は、無駄だと判っていても、誰もやめようと言い出さない。
この辺の内部カルチャーは、公務員をやったことが無い私には、判らないけど、何年か前に、厚生省の検疫課長が「お役所の掟」という内情暴露本を書いたのを読んで、面白かった記憶がある。
そのあほらしさは、私が勤めていた銀行の、デュッセルドルフ支店に匹敵するものだった。
橋本内閣がうちだした、政策の柱に「行政改革」と「ビッグバン」があるが、どちらも本当に実現してほしい。外から日本を見続けて10年、この二つを本当に今やらないと、バブルの傷から二度と立ち直れないだろうと思う。
どちらも、既存のジャーナリズムが、十分に論じているから、私がここで持論を出しても、きっと誰かの二番煎じにしかならないから、書かない。
日本を、離れて永くたってしまい、日本のお役所仕事に触れる機会があまりなかったので、気にしていなかったが、今日たまたま日本とドイツのお役所対応を見て、その歴然とした差を如実に感じたので書き留めておきたい。
ドイツのお役所仕事も、効率的とは言い難い。しかし日本よりはかなりマシだ。
ドイツ語で、いい加減な仕事や、もったいぶっている割には、中身の無い仕事をBeamtenarbeit(役人の仕事)と言ったりするぐらいだから、決して誉められてはいない。
今日、第二子直美ソフィアの誕生に関する、役所手続きを済ましてしまおうと思い、
出生届をドイツ、日本の両国に提出した。
まずは、病院の事務局で出生証明書を作ってもらう。
窓口に行って、証明書下さいといったら、そこに座れと言う。既に新生児のデータは揃っていて、内容を確認する質問をしながら、証明書用紙に旧式のタイプライターでおばちゃんが、バチバチと打ち込む。両親の名前とか、宗教だののデータは、戸籍記録をもとに、またバチバチと打ち込む。ペンペンッとサインして所用時間約10分。
両親のサイン欄ってのがあって、「そこんとこサインしておいて」って言われただけで、非常にイージー。
ドイツの場合、国籍を持っていなくても戸籍に相当する、家族登録書を編成できる。
ドイツでは、Stammbuchと呼ばれるルーズリーフ式のバインダーになっていて、家族の登録事項に変更がある度に追加、変更される。だから、それを一冊持っていけば、家族構成する全員の公式データが全部揃っているので、諸手続きを行なう時に、非常に楽だ。もちろん、有効期限なんてものはなく、ずっと使える。
日本の場合、戸籍謄本、抄本は、いちいち本籍地の役場が発行したものを取り寄せなければならない。しかも発行後3ヶ月以内とか6ヶ月以内じゃないと、認めないなんていう手続きもあります。こんなの、オンラインで結んでどこでも発行出来る筈だ。
これは、海外に居住していると非常に面倒。いちいち親戚に頼んでは送ってもらっている。これもコピーに役場の角印が押してあるだけのぺらぺらの代物。
さて、ドイツ側の手続きの為に、市の戸籍役場に行く。病院の発行した出生証明書と
バインダー式のStammbuch、私と妻のパスポートを持っていったら、その場で、書類チェックしただけで、内容を確認。何も申込書も書いてないし、サインもしてないけど、どんどん書類が打ちあがっていく。
「戸籍役場として、出生証明書4通を無料に作ります。それ以上いる場合は有料になります」と言うので、日本国籍申請用に、国際証明(英仏語など、8カ国語の翻訳が付いている)を2通頼む。
これだけの書類が所有時間20分で出来た、Stammbuchには娘の出生データがきちんと追補されていた。
結局最後まで、私は何も申請書を書いていないし、何もサインしていないのに、手続きは終了。
その後、デュッセルドルフの日本国総領事館に出向き、日本国籍の為の出生届を出す。
これは、日本で日本人の出生を届ける時と全く同じ用紙だから、こまかく説明する必要はないと思うが、ぺらぺらのパラフィン紙みたいな、でかい紙に2枚記入する。
これが、記載項目がやたら多い、いやんなるくらい多い。しかも記載方法が非常にややこしく、間違えずに前項目を埋められる人は、ほとんどいないのではなかろうか。
多くの項目は、戸籍謄本に既に記載されている事の繰返しだ。
戸籍役場が発行してくれる、国際証明は8カ国語がついていても、日本語訳はないので、自分で翻訳を作り、署名捺印する。これも2通。
日本のお役所は、原本2通ってのが、非常に好きだ。多分、一部は金庫の中にしまわれる大切な保管用の原本で、もう一通は、役場で一般事務用に閲覧するものかな?と思うけど、これはコピー機が出現する前に必然的にやっていた風習なんだろう。
出生届のぺらぺらの半透明パラフィン紙も、きっと感光紙で、青写真とる為だろう。
コピーと言う文明の利器が出来た今、申請者に手書きで、同じ内容の紙を2通欠かせる必然性は、もはや無いに違いない。
でも、役所の掟では、誰も効率化なんて考えないから、50年前に制定されたものを誰も変えようとは言い出さないのだろう。
戸籍謄本の記載と、綴り方が違うとか、枠をはみ出しているとかで何度も訂正を繰返し、申込を受理されるまでに、結局1時間半かかった。また、日本の書類というのは、署名だけでは認められず、署名捺印が条件だ。海外の生活では印章なんてものは、使う機会がないので、日本人でも、普通は、持っていない。
そうなると、あちこちに拇印を押す。これもあまり意味の無い風習だと思う。本人確認なら、署名だけで十分の筈だ。銀行の印鑑照合と違い、この印章を何かと照合する作業がないからだ。
実印を要求するなら、印鑑証明との照合作業が必要だが、それを要求していない以上、意味のない形式を満たす為だけの、行為に他ならない。
同じ出生届けに、ドイツの手続きと、日本の手続きで一時間以上違う。しかもドイツ側は既に全証明書も発行済み、戸籍の記載もすでに終了している。
一方、日本側の手続きは、まだ受理だけである。これから戸籍に記載されるまでには、数週間かかりますと言われた。
これでは、日本の役所は、無駄な人間と作業を作りだしているとしか思えない。
きっといろんな官公庁で、絞れば、濡れ雑きんのように無駄だらけなんだろう。だから政府の支出は膨大になり、財政赤字を抱え込んで赤字国債を出しまくる体質になってしまった。
役人に競争原理は無いと、前述したが、一つだけあった。予算の獲得争いだ。
役所には、バランスシートの発想はない。資産、負債の概念がないから、もらった予算は、目的がなくてもとにかく使い切る。さもないと、翌期の予算が削られるからだ。
民間会社なら、経費を予算以下に削減すれば、利益を生み出し、それが従業員のボーナスとなり、あるいは、株主の配当に回り、誉められる。
使い残した利益があれば、それが再投資に使われ、会社の資産となり、さらに利益を出す為のバネになる。
この役人の、予算使い切りの習性を変えなければどうしようもない。
カラ出張、架空残業手当てを受けた役人なんてのは、納税者に謝罪すべく、実名公表したらいいと私は思っている。
この機会にちょうどいいや、と思い。長男の日本国籍のパスポート申請をした。ドイツで出生し、EUの外に行く事もなかったので、いままでパスポートも持たずに、2年以上、国境を行ったり来たりしていた。EUの決断とシェンゲン協定のお陰である。
長男は、ドイツ国籍も持っているが、これもやはり必要性がなかったので、ドイツのパスポートも、まだ持っていない。
いちおう、何か身分証明書を作っておいた方が、いいなと思い、ついでに総領事館で申請。
申請用紙に、申請者の氏名、ふりがな、ローマ字表記という欄がある。
幼児の場合は、代理署名が認められているので、全部私が代筆した。
申請者の氏名:朝倉ヴィンセント一行
ふりがな:アサクラ ヴィンセントカズユキ
ローマ字表記:Asakura Vincent Kazuyuki
こう書いたら、駄目だと言われた。なぜか?
ローマ字は、ヘボン式表記じゃないといけないのだ。だから一旦、ヘボン式で申請して、その後、追加で非ヘボン式の使用許可を別途申請する。
結果、 BINSENTO という名前で届け出、その後 VINCENTというつづりを使えるように、非ヘボン式申請書を提出。
これも、無駄としか言いようがない。なぜ、いまだにヘボン式にこだわる必要があるのだろうか?
これも役所の頭が堅い典型例だ。ヘボン式表記というのは、明治初期に英国人のヘップバーン氏が、当時アルファベットに慣れていなかった、日本人の為に、五十音表に対応させて、わかりやすくしただけのものだ。
いまや、義務教育でアルファベットも英語も教える時代なのである。
もっと自由にしてもいいのではないか?国際社会で通用しやすい様に、弾力的になったらどうだろう?
理沙ちゃんのローマ字表記を Risaでなく、Lisaにしてあげたっていいじゃないか?
麻里ちゃんだって、Mariでなく、Maryにしたかったら、認めればいいのに。
BINSENTO って名前を書きながら、非常にばかげた制度だと思いました。
たしかこんな川柳がありましたな。
ギョエテとは、俺のことかと ゲーテ(Goethe)言い。
©1997
copyright Hiroyuki Asakura