『とかげ』
吉本ばなな
新潮文庫 350(367)円
ISBN4-10-135912-1
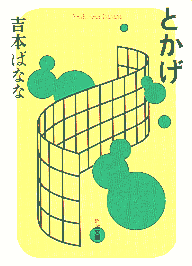 この文章の中で彼女をとかげ、と呼ぶ。
この文章の中で彼女をとかげ、と呼ぶ。
そう呼ぶのは、彼女の内ももに小さなとかげの入れ墨がしてあるからではない。
彼女の目は黒くて丸い。は虫類の目、無心の目だ。
彼女は小さく、体は隅々まで冷たい。あまりにも冷たいので、私は彼女をこの両手のひらに包み込んでやりたいと思う。でもそれはひなどりや子ウサギのようではない。包み込んだ手のひらでちょろちょろと違和感のある感触の尖った足でくすぐったく動き回り、のぞきこむと小さな舌を出して、そのガラス玉の目で「何かを慈しみたい」という私自身の、心細げな顔を映し出す。
そういう生き物の感触だ。
(p25、「とかげ」より)
「とかげ」である。ここ最近吉本ばななづいているようだ。
今更なんで「とかげ」? という印象もあるけれど、小泉今日子が朗読したりしていて、そういう売れかたが私は好きではなかったのでこれまで敬遠していたのだ。つい最近、古本屋で文庫を発見したので、「ま、このくらいなら出してもいいか」と思って買ってみました。
装丁は田中英樹という人がやっていて、ちょっとよすぎるくらいにいい。触感が良いです。ただ、これを全肯定はできない……とも感じる。はまりすぎは退歩にもなりうる、ということ。
内容。
短編集です。全編をとおしてトーンが共通していて、それはあとがきにも書かれているとおり「時間」と「癒し」、「宿命」と「運命」といったもの。ある宿命的な事件があって、ある時間が流れて、どこからか癒しが得られる、そういう構造です。淀まず読ませる文体で、重力とそこからの脱出を感じさせる技術はやっぱりすごいな、こうは書けないよな、と思わせるだけのものはあるけれど、けれどやっぱり印象として「こんなに簡単に救われていいのだろうか」という疑問はある。
『FRUITS BASKET』という対談集の中で高橋源一郎が指摘していたように、吉本ばななの小説は「少女マンガ」なのだと思う(負のイメージとしての「少女マンガ」ではなく、たんに、性質として)。それは『吉本隆明×吉本ばなな』で吉本ばななが言っていたように、「ひとつも人間を書いていない」ということだ。たとえば、どうやっても赦せないほどの「嫌なヤツ」というのは出てこない。主人公たちの心理的な混乱は表層を上滑りしているかのようにわかりやすい。
……これは吉本ばななの作品が、小説よりも物語に近い、ということでもあるといえる。
だから、それゆえに絶対的に救いのない状況というのは出てこない。いつも最後では、どのようなかたちであるにせよそこに救済はあるし、赦しがある――あってしまう。
吉本ばなながヒーリングの効果をねらって小説を書いているのだとしたら、それは成功しているのだろう。すくなくともこれだけ売れているということは、それだけ多くの人々がこの「救い」に適応しそれを求めているということだ。
だが、その救いのあんまりな絶対性は、安直さは、私には受容しがたいように思える。
(救済がない、というのが真実だし、もしなにか救いがあるとすれば、救済の非在という深い絶望の先に存在するのではないかと思えるのだ。私には。なんて大上段に振りかぶらないところが、きっと吉本ばななのいいところで、だから売れるわけだよ、とは思います)
総評。
なんかほっとしたい人、とりあえずの救いがほしい人には、いいと思う。
……なんて、まあそこまで厭味になる必要もないか。
小説としての完成度はけっこう高いので、ちょっとした短編を読みたい、というときに手にとって見るのもいいかもしれない。そういう意味ではおすすめできる一冊だ。
version.1.2.97.05.16.
少女マンガ・レディースコミック/少年マンガ・その他のマンガ/小説/評論・対談・エッセイ
月下工房インデックス/Book Review index/book BBS
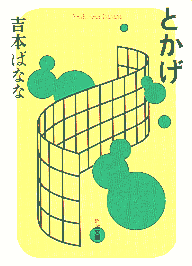 この文章の中で彼女をとかげ、と呼ぶ。
この文章の中で彼女をとかげ、と呼ぶ。