昨日、ヘダーさんが見学を勧めてくれたハケシェヘフェ(←カタカナで書きにくい)という再開発を見に行く。古い建物をきれいに改装して、居心地の良い中庭が連続する複合施設である。映画館、お店、カフェ、そして住宅まで何でも一体にしているのがすごい。ベルリンの路上カフェは、うっそうとした樹木のジメジメか車の排ガスがひどくて、今一つ落ち着かないところが多かったが、ここは適度に静かで気に入った。旧東側の静けさがプラスに生かされている感じ。 中庭の一角に、おまけに洒落た本屋さんを発見し、街の写真集や本を物色。きれいな写真集を購入。
オイローパセンターに急いで戻り、話を伺う約束をした日本食屋のKさんと会う。わざわざ休日の時間を割いてくれたことに感謝。 彼女はベルリン暮らしは約1年ほどだが、それでも住人ならではの興味深い話がたくさん聞けた。日常生活の様子がおぼろげにわかったことに加え、ドイツ人には尋ねにくかった東西分断の社会的後遺症について聞けたことは、観光やヒアリングだけではわからない貴重な情報である。(家に泊めてくれたロンドンのT、パリのUにも改めて感謝。) 帰り際にはこちらが礼を言う前に、「ベルリンの新しい見方や、アメリカの様子などが聞けて面白かったです。ありがとう。」とKさんに言われ、ちょっと照れる。
Kさんとの話が盛り上がり過ぎて、2時のヒアリングに少し遅刻。恐縮しつつドアをノックすると、クンストさんが笑顔で迎えてくれてホッとする。 彼の話からは、知性の奥行きが感じられる。ヒアリング中に部下が次々とやってくることからも、どうやら頼られる上司らしい。混沌を極めているベルリンのまちづくりについて、その混沌ぶりの概要を掴むことができたのは大きい。 東西地域の格差については単純に西高東低と言い切れることばかりではないこと、また住民が東西地域を分けて扱うことを本能的に避けていることなど、頭では想像できていても、現場の人の口から語られると苦労の深さに驚かされる。
ヒアリング後、ようやく旧市街を歩く。初めて目の当たりにする社会主義国のまちづくりである。 駅から出ると、いきなり非人間的に巨大な広場。周囲には無味乾燥な「箱型」集合住宅、レーニン(のわけはないだろうが)らしき銅像、そして空き地。各建物は中南米の途上国にもどこか似ているのだが、人々の表情がどことなく暗いのが決定的に違う。経済停滞と強権政治も、社会主義と(建前では)自由主義では結果が異なるのか? テレビ塔の回転式展望レストランに上がって、お茶をしながら市街を360度一望する。遠くを見る限りは至る所に森や木々が残され、工事用クレーンが立ち並んでいるので東西の違いはよくわからない。しかし、足下の荒涼としたアレクサンダー広場、モニュメンタルなマルクス・エンゲルス・フォーラム、そして巨大な箱である旧東ドイツ国会議事堂などを見ると、社会主義の思想が強烈である。非人間的。気が滅入る。 でも、一番威圧的なのは、テレビ塔自体である。ベルリンを歩いていると、ほぼ常に視線に飛び込んでくる冷戦のシンボル。これを壁越しに見た旧西側の住民は何を感じたのだろう?また、足下から見上げた旧東側の住民は何を感じたのだろう? 近くにある文化華やかな頃の建築が、どこか色褪せている。
結局、ベルリンはあまりにも分断の傷が生々しく、どこか陰鬱さが漂う印象であった。物理的、経済的にも勿論そうなのだが、人々の日常の隅々にまで染み込んでいるのは、社会的な傷である。文化の華に酔い、反動でファシズムの暴走を引き起こし、さらに戦勝国の理論で分断されて来た歴史は、永遠に拭えないだろう。 異邦人の自分は、どこかでこの街に強く惹き付けられつつ、一方で逃げ出したい衝動にかられてしまう。自分の中のどうしようもないナイーブさをえぐられた感じ。底なしの消費文化に浸り切った東京では、あり得ない感覚である。
ホテルへ戻りがけに、まちづくりなどの専門書店にもう一度立ち寄る。すると、隣にいたお兄ちゃん達が英語で「どこの大学を出たんだい?」と話し掛けてきた。唐突な質問にあっけにとられつつバークレーと答えると、「どうりで見たことあると思ったんだ。僕らも卒業生だし、(もう一人を指差し)こいつは講師もしてるんだ。」 おお、こんなところで同窓生と出会うとは!バークレーは(異常に)愛校心の強い大学だけあって、いきなり意気投合。旅行の情報交換、仕事の様子など、話し込んでしまう。久しぶりだと、アメリカン英語が心地よい。
ベルリン滞在は延長しなくてきっと正解。フランクフルトで疲れた脚と心のリフレッシュを図ろう。
P.S. オランダvsギリシャ、ユーゴスラビアvsナイジェリアのサッカーをテレビで観た。オランダばらばら。大好きだけど期待しない方が良さそう。ユーゴ強すぎ(かつ美しい!)。結構、良いところまで行けそう。
 メールはこちらへ
メールはこちらへ
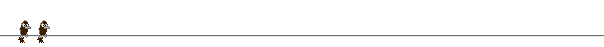
このページは
の提供です。 無料のページがもらえます。