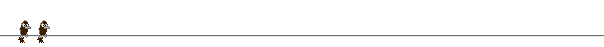---メトロはアメリカで唯一の直接選挙で選ばれた地域政府ですが、そのことの利点と欠点を教えてください。
---メトロはアメリカで唯一の直接選挙で選ばれた地域政府ですが、そのことの利点と欠点を教えてください。長期的な利点は、住民が地域を所有していくことです。実際過去5年間に、興味深い住民意識の変化が見られました。5年前の新聞で地域の記事を見ると、ポートランドなどある一つの市の地図で場所が示されていました。しかし、今では都市成長境界線の地図が描かれているのですよ!つまり、人々は地域を一つの単位として捕えるようになってきているのです。 ---都市成長境界線ならばシアトルなどにも見られますが、人々の捕え方の変化は、メトロが直接選挙で選ばれていることとも関係していますか? そう思います。シアトルの地域政府は優れたものですが、その形態は上から任命された委員会であって、政府というより「クラブ」のようなものです。「クラブ」は何もないよりはましですが、大変カジュアルなものです。これに対し、メトロが直接選挙による政府である利点は、地域全体として行政が取り扱うべき問題が数多くある、と住民が認識することです。地域政府はどこにでも必要な訳ではありません。都市圏が一つの市や郡の境界内に収まっていれば、市や郡が地域全体の問題を扱うことが出来ます。しかし、ポートランド都市圏は3郡24市にまたがっており、個々の自治体だけによる対応では、断片的になってしまいます。それに、アメリカ人は組織をつくるのが好きですから(笑)。 しかし、現実の都市を統括する新しい組織が必要なのは、世界中に共通した問題です。過去50年間に世界の人口は急増し都市は爆発的に拡大したため、既存の都市境界線は既に意味のないものになりました。物理的な都市構造全体を一つの単位として扱わねばならないのです。 ---では、メトロが地域全体の計画を行う際に、既存の自治体や産業界、非営利団体(NPO)、住民個人の果たすべき役割は何でしょうか? メトロと自治体(注:ここでは市や郡のことを差します。自治体の階層構造は、おおまかに「州>メトロ>郡>市」だと理解してください。)の関係は大変重要です。最も大切なのは、メトロと既存の自治体のサービスが重複しないことを住民が理解することです。これは、効率の観点からだけではなく、同じサービスを行う2つの対立する行政機関の間で、住民が板ばさみにならないためです。実は、これこそが直接選挙で地域政府を選ぶことの最大の課題です。つまり、直接選ばれた政治家はその選挙区のためにサービスをしようとするため、本来その地区の自治体が行うべきサービスと競合してしまうのです。そこで、ポートランド地域では自治体が細部を扱い、メトロが全体を均して扱いながら、自治体同士をコーディネートします。自治体は、管轄エリア内の住民の要求を把握すると同時に、地域全体の要求をも理解せねばなりません。産業界には地域メンバーの一員として地域の要求に責任を持つこと、そして具体的には地域経済を活発にすることを期待します。実際、産業界は自治体の境界を越えて地域全体を一つとして捉えていますから、地域問題に大変強い関心を持っています。住民個人はメトロの議員を直接選び、またメトロの活動に参加することで、住んでいる市を越えた巨大な地域全体の形成に直接参加することができます。これは、人々の生活を左右する隣接する市や郡の意思決定に、効率的に働きかける方法です。 ---実際にはポートランド地域の一部はコロンビア川対岸のワシントン州内にあります(注:メトロはポートランド地域のオレゴン州内全域のみを管轄しています)。このことの問題は何でしょうか? うーん、それは大きな問題なのです。もしもワシントン州側も一体に扱えたら、はるかに望ましいのですが。でも、人生は完璧ではありません(笑)。そういった境界を作るのは、人間の性でしょう。できる限りの調整は州境を越えて行うべきです。実際、交通計画のコーディネーションは大変高度に行われていますし、都市成長境界線内部の容量の計算や、開発可能な土地の指定なども両岸一緒に行うべきです。両岸の結び付きを強めるのには、大変なエネルギーが必要ですが、長期的には実現されていくと思います。私達はそのためには何でもするつもりですし、それが対岸の歩み寄りを呼ぶでしょう。 ---他の地域がメトロやポートランド地域から学べることは何でしょうか? 私達は壮大な実験を行ってきました。そして、車に依存しない低密度な現代的都市をつくるのに有効な技術を、数多く開発してきました。この定義にあてはまる場所は、カナダ、アメリカ、オーストラリア、南アメリカなどには沢山あると思います。日本やヨーロッパなど密度がはるかに高いところでは、全く異なった都市をつくるのでしょうから、私達のデザイン自体を大きな変更なしに応用するのは不可能ですが、デザインを生み出した住民参加型プロセスと科学は応用可能だと思います。「プロセスを応用する」という意味は、「住民の価値に基づいたデザインを行う」ということです。その結果、どの場所にも異なったまちができていきますし、まちづくりが人々に優しいものになり、官僚や専門家に仕切られた何だか恐ろしいものではなくなります。そして、住民に支えられた計画は、実現可能な計画でもあります。 ---日本を訪れたことはありますか? ありません。しかし、オレゴンで日本人と触れ合う機会は沢山ありました。私がかつて働いたアシュランドには、毎年日本人がやってくる大学があり、その生徒の中にまちづくりの調査を手伝ってくれた女性がいました。それ以来、私は日本に大きな関心を持つようになりました。また、私の息子のスコットが所属していたアシュランド高校のアメフト部は、日本の姉妹校のアメフト部と対戦しに大阪と神戸へ行ったことがあります。スコットは大阪と神戸の日本人家庭に泊めてもらい、大変良い経験をしたのです。私は移民の二世であり、様々な文化に住んだことがあるので、他文化を経験することは大好きですし、感受性も強いと思います。そして、人々が自分の文化を他の文化を通じて眺めることに感動します。アメリカ人の多くが他文化を一生経験せず、アメリカ流が絶対正しいと考えたり、他文化を遠ざけがちなのは問題だと思います。「お前らも俺達を見習え!」とか(笑)。私はそうではないし、息子にもそうなって欲しくない。息子は日本に行ってから、アメリカを日本の視点から見ることができるようになったかもしれません。あと、(壁にかざってある和凧を指差しながら)日本の文化は大好きです。寿司とか刺身は勿論好きです。実際、ここ20年の間にアメリカと日本との文化交流は大変活発になり、日本の精神も広く紹介されてきました。 ---最後に、日本の市民や、今後ポートランド見学に来るであろう日本のプランナーにメッセージをお願いします。 人々は都市成長境界線ばかりに目をやってしまいがちですが、私達の成功はまちづくりプログラム全体のおかげなのです。そして、そのプログラムがオレゴン人の価値に基づくものであることを理解せねばなりません。そして、私達がどうやってそのプログラムを築いたかを学んで欲しいと思います。それを日本に応用することは可能だと思いますが、それは大きく異なったものになるでしょうし、日本人でなければできないのではないでしょうか。私には大変難しいでしょう。しかし、大切なのは、応用する先の文化に身を置いた上で、その文化を外側から眺めることができる能力です。私の日本への印象は、神聖なもの、皆に共有された価値、多くの田園、秩序や予測可能性への願望、古い伝統、などです。これら日本人に大切な価値を掘り下げることで、素晴しいまちづくりプログラムを作り成功に導くことは可能でしょう。 ---時間のようですね。今日は本当にありがとうございました。 「終」 |
 メールはこちらへ
メールはこちらへ
このページは![]() の提供です。
の提供です。
無料のページがもらえます。
 ホームページに戻る
ホームページに戻る