 メールはこちらへ
メールはこちらへ
神戸編の目次に戻る
世界まちづくり見聞録に戻る
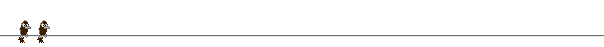
このページは![]() の提供です。
の提供です。
無料のページがもらえます。
 住宅政策の問題:恒久化した仮設住宅
住宅政策の問題:恒久化した仮設住宅
私は六甲道地区のプレハブ製の仮設住宅(写真)に住む老夫婦を訪ねてお話しをさせていただく機会を得ました。仮設住宅に入居が決まった当時は大変嬉しかったこと、そして、仮設住宅の住み心地は理想からは程遠いものの他に移るあてもない辛い状況であることを伺いました。この意見と状況は他の多くの仮設住宅入居者に共有されているそうです。生活の根本である住宅は、まちづくりにおいて再重視されなければならないものの一つですが、この認識は日本ではまだまだ普及しているとは言えません。オフィスや大規模な商業施設は大資本の手で次々に建て直されていますが、住宅や中小商店は個人の資本負担の限界から再建することが大変困難です。「仮設」住宅に震災後1年以上(正確には1997年9月現在で2年半以上)も住んでいる被災者がいるという現実、そして数多くの人が仮設住宅の中でひっそりと亡くなっていった事実は、住宅政策の問題を象徴しています。
 住宅政策の問題:今も人が住む被災した住宅
住宅政策の問題:今も人が住む被災した住宅
つっかえ棒で支えられ、ビニールシートで雨を防いでいる写真の家に、大きな余震が来たらひとたまりもないことは承知の上で、震災後1年以上も住み続けている人がいます。上述したように、仮設住宅は長期の居住の為のものではありませんが、その仮設住宅にすら入れなかった被災者がいるのです。この事実も住宅政策の問題を浮き彫りにしています。
 メーカー製住宅のデザインと拡幅された道路の潤い
メーカー製住宅のデザインと拡幅された道路の潤い
比較的裕福な住民の多い地区では、個人の力をベースにした住宅の再建が急ピッチで進んでいます。その殆どが大手住宅メーカー製の住宅であり、震災でほとんど被害を受けなかったことによる耐震性能への信頼によるものだと思われます。私は、このタイプの住宅が性能的に優れ、かつ今日の日本的風景をつくりだしていることは肯定的に受け入れますが、もう少しデザイン面への配慮があると望ましいと考えています。この写真で注目していただきたいのは、新しい家が道路から後退した位置に建てられていることです。これは宅地の一部を供出して道路を拡幅したためで、安全の確保には望ましい方法ですが、宅地に十分な広さのない(一部を供出するゆとりのない)地区では実施することが困難です。また、拡幅したら終わりではなく、道路沿いに木を植えるなどして、日常の潤いを演出する工夫が欲しいと思います。
 個人の努力を支える行政
個人の努力を支える行政
住民と行政、また住民同士の溝が深まり、計画案がまとまらないために、復興が進んでいない地区があります。これは、重点復興地区に指定された地区では、全体計画が出来上がる以前に個人が再建を行うことが法律で禁止されているためです。この問題は、全体計画が官民の協同で立てられていないことに因ります。まず道路計画を行政主導で決めてから民間部分の計画を立てるというかつての新規開発では一般的だった手順は、近年では官民協同での全体計画の立案作業に取って代わられつつあります。既存のまちの復興という非常事態においては、行政は個人の努力を支えるものという視点から住民と行政が協同して、地区毎に手順や計画に柔軟に決めていかねばなりません。
 住民の参加するまちづくり
住民の参加するまちづくり
上述したように、既存のまちの復興においては、まちづくりの手順と計画を住民と行政が話し合って決めていくことが必要です。しかし、それには時間がかかります。震災という非常時には、一刻も早い復旧が望まれるので、話し合いはますます難しくなります。では、どうしたら良いのでしょうか?解決策は、平常時から住民が参加してまちづくりを行っていくことです。日頃からまちを災害に強くする方法を皆で考え、皆で少しずつ実施していくことです。これによって、長期的には災害に強いまちができていきますし、住民同士のネットワークが強まり、災害に対応する体制も整っていきます。「計画ができ上がる前に大地震に襲われたらどうしようもないではないか」という議論は、「ただ運命に身を任せ、永久に何もしない」ということと同じです。そして、私が最も強調したいのは、「災害に強いまちづくり」は、日頃の「住みやすいまちづくり」から生まれるということです。緑の溢れるまち、公園の多いまち、人のふれあいのある街、安価で頑丈な住宅、十分に広い道路、これらを実現していくことで、安全なまちはつくられていくのです。私はこれこそが阪神淡路大震災の最大の教訓だと考えています。
 メールはこちらへ
メールはこちらへ
神戸編の目次に戻る
世界まちづくり見聞録に戻る
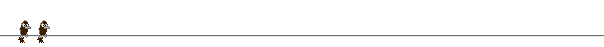
このページは![]() の提供です。
の提供です。
無料のページがもらえます。