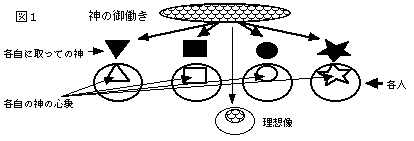
不定期 抄読会
※このコーナーは川上教会青年会での抄読会の資料を掲載したものです。
平成9年5月18日 青年会
抄読会資料 「神と人 共に生きる」ー金光教 教義の概要ー 金光教本部教庁発行
P122〜140 担当:小笠原
4【信心】
信心とは、神からの呼びかけに応えていく人間の側の営み。
その人間は、一般的な人間でなく、個別の「わたし」である。「わたし」には、既に、神からのいのち、はたらき、慈しみが贈られている。その「わたし」が、どうするのかの問題。それが信心。
従って、ある時ある状況の中での「わたし」に取っての応えかけ。「わたし」の目覚めを呼び起こすものと言う性格を信心は持つ。
本教の信心は、神を単に信じるというより、神と共にあることに目覚め、神と共に生きて行くこと、と言える。
4ー1【目覚め】
今 天地の開ける音を聞いて 目を覚ませ
「天地の開ける音」とは、自分にとって天地が開ける、立ち現れてくる、つながった自分が開けてくることへの呼びかけ。
しかし、その成就は「わたし」の目覚めにかかっている。それも、今この時になるかどうかだ。
おかげ・・・信心によってもたらされる有形無形の成果。
それは、人間に贈られてきている神の恩徳(慈しみ)が、信心によって現実化したものである。・・信心を通しておかげに出会える?
心眼・・・・神と共にあることは、肉眼では確かめきれないことに属する。それを見る目(心眼)を開くことが大切になってくる。
夢からの目覚めと信心の目覚めとは似ている。ただ、信心の目覚めには、「難儀」という目覚めへの契機がおとずれ、目覚めを促す神からの迫りがある。契機と迫りを切実に受け止めながら時が熟すのを待つことになる。
4ー2【難儀 そこからの解放】
総括的道筋
人間が存在していること自体が、既に広く神のおかげをうけていることを示す。そのことを自覚し、「この身この心を神に向け」「一心に取りすがって」いくことによって、さらに目を見張るような、信心によるおかげが顕現される。
そのおかげを他の難儀な人の救いにも向けて行く時、一連の助かりが成就する。
わが心の改まり
天地の道理に目覚め、納得し、それに基づいて人間の考え方、生き方が改変されることをさす。難儀からの解放は、道徳的問題でなく、心を改めるかどうかによって決まる。
これらのことを端的に示すのが、天地書附だ。本教のおかげは、人間の自己中心的ではない、天地の道理に沿って改まった心にあるとされる。
一心に頼む・・神と共にある人間、間柄になり切るように神に向かうこと。
和賀心になる・そのように自分に向かうこと。
難儀を解放するおかげは、天地書附に示される間柄になろうとする人間の担う実践的な動きに現れてくる。
4ー3【既成の信心イメージからの脱却】
人間がどうして助かるのか><どのような信心をするのか><如何に既成の信心イメージを乗り越え、新しい信心を打ち立てるかという問題
難儀が、既成の信心イメージに由来することもある。・・・見えざる足枷、助かりの障害。
「日に日に生きることが信心である」とは、日常の中に信心を進めて行くこと。
「生きている間は修行中である」とは、日常出会う事柄を信心の修行と心得て行くこと。
・・信心に基づいて生活を進めて行く。・・・信心を特別な事にしない。
いつでもどこでも神は人と共にある。という神観や、助かりは全ての人に開かれたものだ。という救済観と結び付いている。
当面の目的、目当てを持つと、信心に励みが出る反面、信心が小さくなる。・・裾すぼまりな信心でなく、次々とおかげの輪が広がるような信心をせよと説いている?
「信心するという心でなく、させていただくという心におかげがある」とは、信心が意図的に人が操作し得るものとして、錯覚される事を突いた言葉。神との関わりが抜け落ちた落とし穴。・・・わしが、わしがの意識にも通じる。
・・信心は、誰でもない、ここにいる個別の、唯一の「わたし」と神との関わり方である。
4ー4【人間の向上】
人間の魂の向上を願っての信心。
「本心の玉を磨け」とは、自らを磨く側面を失った信心は「身勝手な」信心だ。それでは、人間が内側から光り輝くものにならない。・・・優れた業績や、功績をなす人は、往々その人自身にも大変な魅力を感じさせられる事がある。
信心の成長も、自らを磨くことと深く関わる。
自分に取っての神の働きであっても、神に取っての自分の働きが如何なるのものか?という視点を忘れてはないか。・・私の難儀が助かるおかげ。自分に取って・・。神に取っては?
あいよかけよの関係になって行くことが、自らを磨く事、信心の成長の中身。
4ー5【神・人の実現】
神と人との関係をいのちに実現する営み。くずれがちな関係を、常に回復して立て直して行くことを目指す信心。
しんじんとは、しんはわが心、じんは神。心が神に向かう事を信心という。
さらに、金光大神はしんじんを神人と書く。・・・神の願いを直感し、自らのいのち(生き方すべて、立ち振る舞いすべて)にその事を実現して行く事を信心、神人。
その事が実現するとき、他の難儀を助ける働きも生まれる。このことは、「生き神=神が生まれる」、「神になる」事に通じて行く。
感想
金光教における信心は、神に向かう人間の側の態度と深く係わる。しかも、その人間は、一般化された人間ではなく、唯一の存在、個別の人としての「わたし」である点は重要な意味を持つと思われる。
その重要さとは、各自の抱える問題、世界観、引き受けられる状況等が全て異なる中での、神との関わりを問題としている事。従って、立ち現れてくる神の「姿」も、実は各自で全て異なる心象を持っているのではないかと思われる事である。同じ場所、同じ教師の教えの元にあっても、実はそこにある、信心の内容は両者において異なっているのではないか。そこに、信心する者と、導く者との関わりの個別性があり、また難しさがある(図1)。
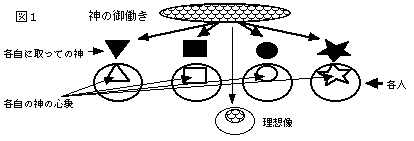
ここで、敢えて、同じ神(のイメージ)を皆が持つべきだとする必然性が金光教にはあるのかどうか問題となる。本教の根本は、天地の道理をどう自己の存在のなかに体現して行くかにある。各自がめいめい、天地に目覚めて生きながらも、全体としては調和が保たれている状態が理想の概要ではないかと思われる。
天地の道理と神はどのように係わるのか? 本教の神は、天地の道理を創った、いわゆる創造主としての神、と言うよりも、天地の道理に最初に目覚め、人間各自にその事を伝えようとする、普遍的な伝道者のイメージが適当な気がする。天地の道理を、人間の言葉に翻訳して伝える唯一の仲介者としての存在が神ではないか。
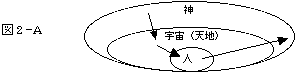
このイメージは、他の宗教の世界観と大きく異なる。他宗では、神>宇宙(天地の道理)>人の順で関係(図2-A)が成り立っているように思う。しかし、本教は、宇宙(天地の道理)<神>人の関係(図2-B)になっていると私は思う。神は宇宙(天地の道理)に命(言葉)を与えた存在とも言えるのではないかと思う。
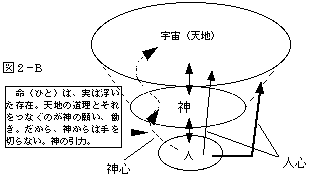
信心を神人と読み換え、神と人との関係の改まりを説く教えは、信心の本質が「関係」と言う構造の中にあることを物語る。そしてそれは、自己をも突き放すほどの、厳しい捉え方でもある事を、見逃してはならない。そこでは、単なる「わたし」はいとも容易く捨て去られ、新たなわたしが生まれる契機が促されているように思う。ここで実現される私は、神の願いを体現して行くものとして、神を通して神がその意味を見出し<言葉>を与えた宇宙(天地)の道理にまで通じて行く存在となるのではな
いかと思う(図2-C)。
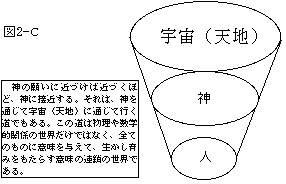
※我々は、抱かれるとか包まれるというイメージで神仏と私達の関係を捉えようとする。その原形は、母と子の関係にあるように思われる。もし、最初から無条件に母と子の関係のように、私達と神仏との関係が決定されているなら、我々は何時でも無条件に「甘え」ていれば良いことになる。様々な教えや戒めがあるのは、実際の我々の関係は、常に脆く危機の縁に立たされたような、危うい間柄になりがちだからではないかと思う。
ご意見・ご感想は下記までメールして下さるか BBS伝言板に書き込んで下さい。
oai208@dokidoki.ne.jpThis page hosted by ![]()
Get your own Free Home Page