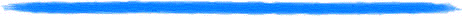
マルチリンガル考-其の②-
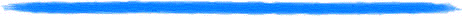
以前、同じ題でエッセイを書きましたが、一日に4カ国語を使い分けていると、ごちゃごちゃにならないか?との質問がありました。
ドイツ語とオランダ語は、相互に類似性があるので、たまに単語を取り違えたりする事はあります。ドイツ語をずっと喋っていた直後に、オランダ語に切り替えると、動詞を間違えたり、或いはその逆に、ドイツに行ってきた帰りにオランダに入ってから、間違えてドイツ語を喋ってしまったりする事も。
でも、実はそれほど、混乱する事はありません。我が家の長男も、もうすぐ3歳になるが、同じ意味の言葉が2つ、あるいは3つある事は既に認識している。
むしろ、多言語を使用していると、困る事は、別なところにあるのです。
言語というものは、単語をならべただけでなく、必ず背景にその文化をひきずっています。「王様」の直訳ロックが、滑稽になってしまうのは、文化が違うからです。
日常の挨拶にしたって、「ああ、どうも、いつもお世話になってます。ごぶさたしちゃって、すみませんねぇ。みなさんお変わりありませんか」と切り出すところでも、そのまま英語で直訳する人はいない。
"Hello, I always appreciate your support. Sorry that I didn't call you for long time. What's new? Everybody all right?" なんて言っても、ひとつひとつの文章は、正しくても、あまりにも不自然な挨拶にしかならない。
言うまでもなく、日本語を喋るときは、婉曲的に、相手を立て、自分をへりくだって話すのが礼儀だが、ヨーロッパではそんな必要はない。
文化が違い、とくに仕事がらみの会話になると、ヨーロッパでは、日本的に、Yes/Noをはっきりしなかったり、或いは、充分な理由を説明しないで結論だけを告げると、相手が混乱する事が多い。
相手の立場を思いやって、会議の場では反論を避けて、後で個別に話そう、なんて事をやると、事をややこしくするだけになったりする。
数学の論理展開のように、これがこうだと、ああなるから、これはやらなくて、こういう状況になるまでは、こうするしかない、と説明しなければならない。
とうとう、ヨーロッパに住み続けて10年もたつと、こうしたアプローチの違いも一応は身につき、私自身も英語、ドイツ語を話しているときは、攻撃的になったり、ずけずけと目の前にいる人に、苦言を述べたりする。
オランダ語のときは、まだボキャブラリーが足りないので、言われっぱなしになってしまうが、、、、
しかし、日本人の社会では、そうした態度は当然、煙たがられる。
そこでようやく、本題の言語切り替えなのだが、
ドイツ語を話していた直後に、日本人と話をするときに、言語は切り替えが簡単にできるのだが、ずけずけと失礼な事を言ったり、やたら理屈っぽい事をいってしまったりする。
言語の背景にくっついている、文化の方がなかなか、切り替えがついてこれなくて、露骨な言葉で、人の心証をわるくしてしまったり、知らない間に人を傷つけてしまったりすることもあり、後で後悔する事があった。
逆に、日本語を沢山喋ってから、家に帰ると、妻に「なんか、あなたの言ってる事ははっきりしないわね」と言われてしまうこともあります。
ちなみに、ドイツ語で、Sprechen wir Deutsch! と言うと、「ドイツ語で話しましょう」という文字どおりの意味がある一方で、「はっきりモノを言えよ!」と言う意味でも使われます。
それだけ、はっきり意思表示と自己主張をする事が社会規範として、要求されているのでしょうね。
文中で、「ヨーロッパでは」とおおざっぱな表現をしてますが、実はヨーロッパの中でも当然、国によって文化は全然違うし、イギリス人だったら笑ってくれるブラックユーモアも、冗談の通じにくいドイツ人だと、しらけてしまったりする失敗もありました。
最近、自分の日本語がすこし、おかしくなっているのに気付くと共に、言語の習得というのは、単語と文法の丸覚えじゃなくて、文化を理解してはじめて、「流暢に話す」と言えるのだなと、改めて思い知らされました。(こういう表現がすでに、日本的であったりする)
©1998
Mar.21. copyright Hiroyuki Asakura