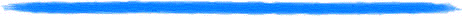
ヨーロッパ10年
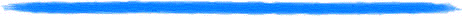
私は、98年6月で、在ヨーロッパ10年の節目を迎えた。
10年一昔というように、結構人間の人生の中では、長い期間となる。歴史の中の10年なんて、瞬きの如く一瞬の出来事だが、この10年、私の人生は、随分変化に富んでいて、いろいろと、中身の濃い期間だった。
ヨーロッパは、大好きです。日本に帰って暮らそうという、つもりは全くなくなってしまった。日本が嫌いになった訳ではないが、私には、はっきりいって居心地が非常に悪い。
でも、日本人であるアイデンティティーは、なぜか結構はっきりと、持ち続けている。不思議なもんだ。へんなやつと思われるだろうが、日本に未練はないが、やっぱり日本人です。
ドイツに7年、オランダに3年。ドイツは、私にはいろんな事を教えてくれた。
でも、ドイツに戻りたいという気持ちは、もう無い。ドイツに住んでいる人には、生意気と思われそうだが、ドイツは知り尽くして、卒業してしまった気分で、むしろ今は、オランダという国の魅力に取りつかれている。
25歳のとき、銀行の転勤辞令で企業駐在員として、ドイツに赴いた私には、初めての海外生活に、カルチャーショックの連続でした。
勤めた銀行の職場の、カルチャーの異常性(エッセイの他の章を参照してください)に驚き、はじめて触れるヨーロッパ流の個人主義にさらされて、日本的な馴れ合い関係に慣れていた私には、悔しかったり、情けない思いをしながらも、いつのまにか、ヨーロッパ人以上に、個人主義的と言われるまでになってしまった。
6年経ったときに、銀行も退職し、妻と結婚して、生活を再スタートし、その一年後には、子供も生まれ、オランダに移住しました。
そんな経緯で、まだまだ奥の深いヨーロッパ、未知の国、世界は数々残っていますが、そんな魅力に取りつかれ、ヨーロッパは、大好きです。
なぜ、日本に帰ると、気疲れしてしまい、ヨーロッパに戻ると、ほっとするのか?街が、人にやすらぎを与えてくれる、余裕と豊かさを持っています。
どこにいっても、緑が豊かで、人が歩く場所には、ゆとりがあり、散歩しているだけでも気持ちがほぐれてくる。
英語で、散歩することを、take a walkと言わずに、ちょっときどった表現で、promenadeという単語を使う事があります。語源は、フランス語からの輸入語ですが、日本では、商店街の意味でプロムナードとなぜか、曲解されてしまっています。
ヨーロッパの街には、れっきとした、散歩の為の道があります。自然の美しい場所に、並木あり、途中で腰掛けるベンチあり、でも売店や自動販売機のような、無粋なものはなく、公園とも商店街とも異質な空間です。
当然、クルマは入れず、歩行者、自転車、乗馬以外の人はいません。人工的になりすぎず、自然の草木が生え、しかし市当局が定期的に並木の手入れをしたり、清掃しています。
散歩が好きな私は、日本に行くと、こうした道がまったく無いのに、閉口してしまいます。
大きな道路は、常にクルマ優先で、申し分けなさそうに、すれちがうのがやっとの幅で、歩行者用歩道がちょこっと、ある。あるだけ、まだいい。国道と呼ばれる道路すら、ひどいときには、両側に白線が引いてあるだけで、すぐ横でクルマがびゅんびゅんと、走っている。
横道にはいると、今度は生活道路になっていて、ところせましと、自動販売機がならび、コンビニエンスストアの店の前におかれた看板は、24時間、人の通行を妨害し続けている。
純粋に、人間が優先して、散歩してリフレッシュする目的で利用できる道が、一体東京都に、どれほどあるだろうか?
街というものを、社会資本のひとつとして、捉えているか、そうでないかの、行政の姿勢の違いを、私は感じてしまうんです。
街の整備というのは、お金と時間がかかるもんです。車椅子でも移動しやすい公共設備を作る、或いは、人が集まる場所は、つねに清掃されていて、花壇に花が植えられている。こういった環境をつくるのは、大変な投資です。
先月、日本に行ったとき、思いスーツケースをころがして出掛け、あらためて気付きました。家を出て、駅の駐車場から駅構内にいくまでに、段差がある場所は、必ず車椅子が通れる幅の、スロープがあります。
私の乗る近所の駅は、昼間に切符売場の職員が1人いるだけの、鈍行しか停まらない田舎駅です。それでも、ホームに上がるために、エレベーターが付いている。
乗り換えのターミナル駅では、ホームには、エスカレーター、エレベーターの両方が付いている。スキポール空港駅もしかり、重い荷物を手押しワゴンに載せてもエスカレーターにのせられる。なんの不自由も感じませんでした。
これが、日本に到着した途端に、この重い荷物が、本当に文字どおり、お荷物になって、厄介でした。階段は、歯をくいしばって、一段毎に荷物を持ち上げて運ぶ。エスカレーターはあっても、ワゴンは使えない。
この例は、単なる一例にすぎず、こうした街や公共の場所に対する整備の度合いが、比較にならないほど、日本の状況はお粗末です。
なぜ、こんなに差がついているのか?たしかに、日本にくらべると、個人の税負担も重いです。給与所得の半分くらいが、税金や、社会保障費で消えてしまうのは、ヨーロッパどこにいっても同じ状況です。
日本の消費税に相当する(ちょっと違うけど)、付加価値税は、どの国でも、15から20%のレベルです。快適に対する代償は、やはり払っています。
こうした負担の積み重ねが、いろんな所で、社会資本への投資にまわっているのですが、日本は、これをやるタイミングを、逸してしまったのではないでしょうか?
日本が、経済大国の仲間入りを果たした、高度成長期には、もっと日本政府の財政は、潤っていたことでしょう(今や、国家財政は、赤字で火の車、借金漬けで、余裕まったくありません)。
でも、くだらない土地開発で、山を切り開いて、海をふさいでコンビナートを建設して、外国の債券に投資したわりには、結局、人間本位で住みやすい、街づくりの為には、金をけちってしまった。
この時に、ちゃんと社会資本に対する、投資を計画的にやっていれば、もう少し日本の街は、住みやすい環境が整っていた事でしょう。
これで、昭和40年代、50年代に怠ってきた、社会資本整備のツケが、まわってきたのが、バブル経済時代だという、考えを私は、持っています。
国が、なにも快適な生活環境を作ってくれない。一方で、輸出産業がうまく、花開いた結果、国全体には、金がどんどん流通しうるようになった。
みんなそこそこ、金持ちになれた。だから、このお金で、快適な生活環境が欲しくなる。国は、何もしてくれないから、民間企業は、リゾート乱開発に走り、それをみんな借金してでも、欲しくなる。
株も土地も、どんどん上がっているから、とにかく買わなきゃ損だ。上がったら、売って、その金で、快適な生活を買おう。
この循環が、個人心理にまで、浸透してバブル経済を引き起こしたのではないかというのが、(完全に私の私論で、なんの裏付け調査は行っていないので、文責はとれないけどね)結論。
ヨーロッパ10年の、回顧と抱負と語ろうかと、書き出したのに、また脱線したままおわっちゃった。上から読んでみたら、変なエッセイだ。起承転結になっていない。ははは。