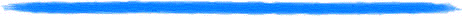
2002年、米国経済破綻
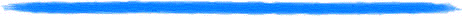
Mar.6.99
先日ポールケネディの、「大国の興亡」について、少し書いた(蘭学大全の項参照)。
歴史を冷静に見れば、結論は明らかである。
冷戦が終わって、今や軍事力、経済力で敵なしの米国の、隆盛にもいつか終わりがある事を、想定しなければならない。
私は、経済学者でも、政治学者でもない(蘭学者だけど、、)一介の、さらりーまんであるからにして、いい切ってしまおう。
2002年に、米国の超大国としての、看板はおろされる。
私の、仮説は、米国が、今日も、ダウジョーンズIndexが、市場最高値をつけ、安泰なのは、US$という通貨が、依然信頼のおける、基軸通貨だからです。
軍事力だけで、世界をコントロールできるかというと、必ずしもそうではありません。
もはや、軍拡競争は、かつての歩兵騎兵のレベルでなく、湾岸戦争が証明していたように、無人の遠隔操縦でできる、ハイテク戦争の時代に突入している。
ミサイル一個とっても、何十万ドルという値段がかかるそうだから、経済力こそが、最終的には、勝敗を決める要素だ。
米国の軍事負担は、重い。
しかし、この負担は、経済的には、投資効果の少ないものになっている。
今のアメリカの、本音を代弁しよう。北朝鮮問題、ユーゴ問題には、あまりお金をかけたくない。
問題解決しても、リターンに、うまみがない話しだ。
どうせなら、金を注ぎ込むのは、イラク問題だ。
理由は、簡単。石油の利権が絡んでいるから。イラクの軍事力は、周辺諸国にとって、脅威だ。
湾岸戦争の、イラクによるクウェート侵攻は、もとはといえば、原油をめぐる経済的利害対立だった。
サウジアラビアに、米軍を駐屯させ、砂漠の見張り番としての役割を、請け負うかわりに、原油ビジネスについては、影響力を保持するのが、米国の政策だ。
BPやシェルのような、欧州系の石油メジャーもあるが、この業界を仕切っているのは、米系だ。
中近東の産油国も、OPECで紳士協定を守っていれば、安定した価格で、米系メジャーが、買い取ってくれた。
ところが、原油価格は、下がる一方だ。私が就職したころは、1バレル20ドルってのが、相場だった。いまや、その半額だ。
これは、油田の掘削開発技術の向上で、いままで難しかった、メキシコ、インドネシア、北海などの油田の開発が、一気に進み、市場供給量が増えると同時に、中近東のシェアが相対的に、下がっている。
原油は、タンカーで輸送する。当然、輸送賃の高い商品だ。
経済効率を考えれば、ヨーロッパの買い手は、北海から、アジアの新興工業国は、インドネシアから、アメリカ中南米は、メキシコのオイルへの、依存度が高くなる。
中近東諸国としても、いままでのお得意さんが、どんどん逃げていくわけで、いつまでも、原油価格表示を、ドルだけで考えてよいのか?という疑問が湧く。
地理的に考えても、欧州は、上得意なんだが、いままでUS$建てで取引きしていたが、どうも為替レートが、乱高下する。
本当に商売をとりたくなったら、ユーロ建ての原油価格表示を始めなければならない。
これで、US$の基軸通貨としての、役割が薄らいでくる。
原油というのは、鉄鋼とならんで、産業の一次産品であり、身の回りにある、ありとあらゆる物の価格に、もろに反映されるのである。
アメリカ経済の、成長は9年続いている。
日本のバブル景気は、80年代初頭に始まり、こけたのが、十年後だ。
一足おくれて、経済が急成長したアジア各国は、80年代半ばから、脚光を浴び、外国から投資家がどんどん、金を注ぎ込んだが、結局10年で、これもはじけた。
ロシアの経済危機も、ゴルバチョフのソ連邦解体、資本主義の導入から10年で、借金が返せない事から、破綻。
生産設備などに、投資を行って、物を作り、商品を売り、利益を出して元を取るまでの、サイクルは、ざっくり言って、5年間。
一回投資して、5年後に、うまく行くと、もう一度生産設備に投資して、もう1ラウンドやろうとする。この第二ラウンドで、大抵、需要に変化が起り、10年たったら、景気は、減速を始めるのである。
2002年、アメリカがとうとう、この10年目の周期を迎える。
98年度の自動車の販売が、二桁の伸びを示したことに、気を良くした、アメリカの自動車メーカーは、需要に応えるため、増産体制をとり、設備投資をこのところ、発表している。
これは、すでにアブナイ徴候だと、言ってよい。
準備通貨というのは、いざというときに、使いやすい通貨をプールしておくこと。
貴金属でいうと、金がそれに相当する。
流通市場がしっかりしていて、価格が安定している。
ダイアモンドにくらべて、金が投資対象として好まれるのは、事実上の通貨に近い性質を持っているからだ。
ドルも、持っていて安心の通貨として、好まれてきた。
その証拠に、世界中どこでも、両替できるし、貿易の中心通貨だ。
「有事のドル買い」という言葉に、象徴される。戦争が起きそうになると、ドルに安心を求めて資金流入し、ドルが強くなる。
しかし、US$がその地位を、確立できたのは、ほんの数十年、それまでは、世界の基軸通貨は、イギリスポンドであった時間の方が、むしろ長いくらいだ。
US$が、こうした準備通貨になったのは、冷戦のお陰である。第二次大戦後の、緊張で、米国が東側の所有する、ドル口座を凍結するのではないか、という疑念が、ドルのアメリカ国外への流出を招き、 ユーロダラーという、アメリカ国外でのドル取引きが、盛んになった。
これに、とって替りそうな、通貨が今年から誕生した、ユーロである。
すくなくとも、ユーロ誕生前は、ヨーロッパではドイツマルクが、事実上の準備通貨だった。
民主化直後に、チェコに旅行したとき、すでにアングラ経済は、ドイツマルクで動いていた。
闇屋の、価格表示は、マルクだったし、事実ホテルのバーでは、ドルとマルクを両方みせると、マルクを選択した。
ドルだけを、中心にして準備しておくと、為替リスクの分散が、はかれない。
いまや、アジアの外貨保有の王者になりつつある、中国も、これから外貨準備のポートフォリオについては、ドル偏重から、ユーロに移し替えをする事を、明言している。
ユーロの誕生を、1月1日に大騒ぎしたが、まだ本当の意味で、市場に浸透しているとは、言い難い。
現金の流通がないからである。
アングラ経済で、準備通貨として認められるためには、現金がなければ話しにならない。
2002年に、いよいよユーロの紙幣硬貨の鋳造発行が、開始され、半年間で、11カ国の通貨は、消滅する。
欧州の周辺国では、すでにドイツマルクが、アングラ経済で幅を利かせているが、さらに汎用性が高くなった、ユーロがその地位を独占するのは、間違いない。
現実として、周辺国は、ユーロ加盟国への、経済的依存度が、輸出入ともに高いので、当然、支払手段として、ドルよりも、好まれる。
米国は、カード社会だ。現金取引きというのは、原則個人の消費を前提にしているものなので、アメリカくらいの、カード社会だと、高額紙幣は必要ない。
しかし、敢えて数年前から、US$100札を、米国は発行を、開始し、増刷している。
これは、アングラマネーの、基軸通貨としての、US$の立場を、意識しての事である。
世界中のアングラ経済で、麻薬取引、密輸品売買、売春の支払い通貨として、ジョージワシントンの1ドルを、いちいち数えて積み重ねてはいられない。
この手の、闇商売では、カードや送金など使えるわけがなく、高額紙幣が必要になるのだ。
ドイツマルクにも、同じ事が言え、1000マルク札があるが、日常生活でお目にかかる事は無い。
2002年から、発行される、ユーロも、(確認を要するが)100ドル紙幣よりも、もっと額面の大きいユーロ札を予定している。
以前、エッセイのなかで、「なぜ、日本は豊かさを実感できないか」という題で、日本は、米国債の大量消化により、アメリカへの資金供給をすることで、忠誠を尽くしてきた。
しかし、これは、日本が、大盤振る舞いできる、お金持ちだから出来たのだが、もう、財政赤字を抱えて、火だるまになった日本国は、そんな余裕がなくなり、今まで米国経済を潤わせる一端を、担っていたジャパンマネーの流入がストップすることで、米国経済にブレーキを掛ける、一因になるだろう。
当然、これには、株価の暴落が伴う。
私が、自分なりに組み立てた、2002年、米国の経済破綻説。はたして、当たるか外れるか、あと3年たったら、私は、オオウソつきか、予言者かのどちらかに、なれるでしょう。


©1999
Nar.5. copyright Hiroyuki Asakura