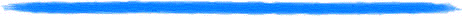
NATOの空爆問題で思った事
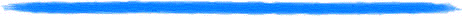
ユーゴスラビアへの、空爆が行われるかとマスコミが騒いでいた10月、なんとかぎりぎりの線で、ミロセヴィッチが譲歩し、最悪の事態は、避ける事が出来たのにほっとした。 同時に、今回の空爆騒ぎは、突然クローズアップされて、あっと言う間に、忘れ去られてしまった感がある。
数週間立った今、あまり新聞にも載らなくなった。 多分、世界中が注目したといっても、正直いって世界中の大半の人には、正直いって「なんだかよくわかんない」事だからでしょう。
いまだに、世界には、外部の第三者にとっては、「よくわかんない」が一杯ある。 当事者にとっては、すごく大切な事なんだけど、どうしていつまでも殺し合いしてまで、戦争をしかけるのか。
私にとっての、この「よくわかんない」は、4つあった。
①英国とアイルランドの、北アイルランド問題とIRAのテロ行為。
②イスラエルとパレスチナ解放機構の、ガザ問題。
③旧ユーゴスラビア解体後の、ボスニアヘルツェゴビナ問題と、セルビアモンテネグロの新ユーゴスラビアと、他の共和国との関係。コソヴォ地区のアルバニア系民族問題。
④カシミール地区の帰属をめぐる、インドとパキスタンの核兵器競争。
どれをとっても、私の日常生活にあまり関係ないので、ずっと無関心でいたが、最近、ロシア人の同僚に「北方領土の帰属問題に、なぜいつまでも日本はこだわるの?」と聞かれて、正直言って、私もあまりはっきりした見解は持っていなかった。 (私の個人的な意見では、もう既成事実として、ロシアが占領しつづけているから、もういらん、勝手にしろ。その替わりに、絶対軍事拠点をおかず、日本に武力行使しないと一筆書けというくらい)それを横で聞いていた、フランス人は、「なんだか、我々には、よくわからん問題だ」と言った。
確かに、外部から見れば、何をやっておるんだという程度の問題なんだろう。
NATOの空爆が始まるか、と情勢が緊迫していた10月に、ユーゴ(モンテネグロ共和国出身)人の同僚が、気をもんでいた。
セルビアに住んでいる、家族や親戚にモンテネグロに、疎開するように頼んでいるが、聞き入れてもらえないと、心配していた。 私は、「はっきり言って、ユーゴの問題は、何故あんなにいつまでも、戦争しているのかわからんよ。どうなってんの?」と尋ねたが、彼に「それを説明するには、まる一日かかるよ」と言われた。
それ以来、「よくわからん」のテーマを、自分なりにクリアーにしておこうと思い、①と③は、いろいろと調べて、事の次第はなんとなく判ってきた。②と④は、まだまだわからん。確かに、それぞれの問題を掘り下げていくと、まる一日かかる。ここに書き出すと終わらなくなるので、割愛する。
戦争のやり方も、変ってきた。かつて、戦争の原因は、大抵は、宗教問題、民族問題、産業上あるいは軍事上の重要拠点の確保等から、関係が悪化して、戦車が軍事進攻して火蓋が切られる物だった。少なくとも、第一次大戦あたりまでは、歴史上の戦争は、大体この範疇に入っていた。(そういえば、第一次大戦のきっかけサラエボ事件にも、セルビアが絡んでいたな。昔から、問題の多い地域ではある。)
第二次大戦あたりから、空爆と空中戦が戦争の要になってきた。太平洋戦争のはじまりは、言わずと知れた、真珠湾攻撃だったし、連合国と枢軸国がしのぎを削ったのは、空中戦の技術で如何に遅れを取らないかだった。
真珠湾攻撃あたりは、それでも敵国の軍事施設を破壊が目的だったが、次第に禁断の、無差別攻撃に変ってくる。海軍の砲撃は、もっぱら相手の軍事力が対象だし、陸軍の侵攻も、軍事境界線を前に進めるものだったが、空爆はそれまで二次元で戦っていた戦術をすっとばして、一般民衆を簡単に巻き添えにする事を可能にした。
私の知る限り、意図的かつ組織的に、この禁断の手を使って、泥沼にはめてしまったのは、ドイツ軍のロッテルダム空爆だった。
当時、まさかこのような、戦闘員以外の一般民衆を攻撃対象として、都市機能そのものを破壊する戦闘のあり方は、常軌を逸していた。オランダ側もまさか、やるとはおもっていなかったので、全く無防備でなす術もなく、あっと言う間に木っ端微塵に街がなくなり、多くの犠牲者を出した。
この空爆は各国の猛烈な批判に晒される事にはなったが、皮肉な事にドイツ軍のこの行為は、連合国側にも「こうなったら何でもあり」の争いに火をつけてしまった。
英国空軍は、ドイツ軍の技術を上回る絨毯爆撃を完成させ、大戦末期には、広島長崎の原爆使用爆撃を除けば、通常戦力で史上最大の破壊力を持ったドレスデン空爆で、ドイツはしっぺ返しを受ける事になった。
絨毯爆撃の残忍性は、一般民衆を銃撃で撃つのでなく、炎熱で焼き殺す事にある。 ドレスデンの攻撃で使われた手法は、徹底的に計算されつくされたものだったと言われる。
最初の小型機は、閃光弾で標的地区をマークして、上空から目標を見やすくする。次ぎに来る爆撃機は、主要建造物を破壊した上で、焼夷弾で町中に火災を起こす。これを繰り返すと、地下に潜り込んでもその熱風で、燻り殺されるのでまさに、逃げ道はない。
一回目の爆撃が終わると、一旦退却して時間差を置いて、第二団が出撃する。
30分後には、周辺で被害を受けていない地区から、救援隊が市内に入ってくるが、今度は、第二団がこの救援隊を直撃してから、外部から順々に、内部をもう一度焼いて、逃げ場を失った生存者を駄目押しで殺戮する。
あまりにも悲惨な空爆だったので、ドレスデン市もその時に崩れ落ちた教会をずっと、戦後も直す事もせず瓦礫のまま保存していたが、50年経った今、ようやく修復する計画が持ち上がっている。
空爆に対する、人道的見地からの非難は、当然戦後も議論されたが、その議論もむなしく、ベトナム戦争では、さらに進んだ軍事技術を使って、米ソ両軍が好き放題に荒らしまわってしまった。
記憶に新しいところでは、湾岸戦争でも専ら空爆が、スポットを浴びCNNでも連日ビデオ中継していたが、むしろ軍事施設の破壊を目的にした、本来の空爆のありかたに近いものだった。
今回のユーゴ問題で、いとも簡単に、「アルバニア系住民救済、の人道的見地から」NATOがベオグラード空爆を決めてしまったのは、個人的に非常に残念だったし、不思議だった。内政干渉とも取られかねない状況で、いきなり空爆というのは、乱暴な結論であった。
世代的に、第二次大戦の空爆を経験している軍事指導者は、いなくなっているから、感覚的にその恐ろしさを認識していないのかもしれないが、いずれにせよ、無辜の市民を犠牲にする戦法は、後日逆に「人道的に」非難されるであろう事を、認識していない筈はないと思う。
少なくとも、今回ベオグラードにいた市民は、ミロセヴィッチのセルビア民族の右翼的体制を支持するもの、反対するものが混在する中、情報管制で必要な情報も入らないまま、空爆決定を迎えた。
今回の一連の空爆決議は、米国主導で行われ、NATO加盟各国の政府の決議を順にとる方法が取られた。
冷戦が終わった今、米国もそろそろ世界の警察官ぶるのはいい加減に辞めて、NATOの一加盟国に過ぎない立場に、方針を変えるべきではなかろうか。下手なでしゃばりが、誰も勝者のいない悲惨な戦いになる教訓を、ベトナムで充分学習したであろうに。
NATOの基本精神は、あくまでもワルシャワ条約機構の対抗勢力として、欧州の平和維持の筈だから、今回のような民族問題に端を発する紛争の解決は、国連軍としての活動にすべきだというのが、私の意見です。
現に、ボスニア問題までは、ずっと国連が紛争解決の当事者として、関わってきたのだから、その流れから行けば、今回もNATOのレベルの話ではない。
明石さんは、非常に公平な仕事をしていたとおもう。少なくとも、対立する三勢力を常に、対等に扱っていた。ところが、セルビア人勢力を悪者に仕立て上げて、征伐したかった米国の方針に反していた為に、米国の逆鱗に触れて、解任されてしまったのが実情だろう。
歴史的に、米国は汎スラブ主義を叩かないと気がすまないようだが、今回のでしゃばり方は、目にあまるものがあり、自粛して欲しかった。


©1998
Nov.1. copyright Hiroyuki Asakura