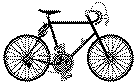
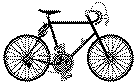
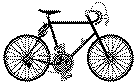
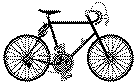
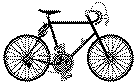
第二章
微妙な交渉 エセルバーサが言ったかもしれ ないこと エセルバーサが実際に言ったこと ハリス夫人が言ったこと ぼくたちがジョージに言っ たこと 水曜日に出発する ぼくたちの精 神を改善しようというジョージの提案 ハリスとぼくの疑念 二人乗り自転車においてどちらがもっとも働くか? 前の乗り手の意見 後ろの男の見解 ハリスはいかに妻を見失ったか? 積み荷問題 わが亡きポジャー伯父さんの叡知 鞄 を持っていた男についての話の冒頭
ぼくはその晩からエセルバーサ相手の交渉を開始した。
まず意図的に多少うっとうしく振る舞うことからはじめた。ぼくの予定はこうだ。エセ
ルバーサがぼくの態度について文句を言ったら、いさぎよく認めて、その後に、
こいつを頭脳への負担のせいにして説明すればいい。話題はおのずと、ぼくの健康状態
一般へと移るだろう。即座に真剣な方策をほどこす必要が明らかである、ということに
落ち着くはずだ。うまくやれれば、エセルバーサのほうから提案させることさえできる
かもしれない。
「ねえ、あなた。あなたには気分転換が必要だわ。完全な変化よ。お願いですから、わ
たくしのいうことを聞いて、一ヶ月でも休暇を取って出かけてくださいな。一緒に来い
なんておっしゃらないで。あなたがそうして欲しいと思ってることは知ってます。でも
だめ。今必要なのは、男のお友達とのお付き合いだわ。ジョージとハリスに一緒に行け
ないか尋ねてごらんになったら?」
「聞いてちょうだい。あなたのように頭脳を使っている方には、家庭の雑事に追いかけ
られる場所から、時々離れることが必要なのよ。しばらくの間、子供たちの音楽のレッ
スンや、靴や、自転車を欲しがっていることや、一日に三度もでてくるルバーブの臭い
のことを忘れていらっしゃい。料理人やインテリアデザイナーや隣の家の犬、肉屋の請
求書といったこともみんなどこかにやってしまって」
「新鮮で興味深くて、疲れた精神を癒してくれるところ、そして心の平和や新しい発想
を見つけることができる、そんな緑の片隅に出かけるといいわ。あなたは息抜きに出か
ける。わたくしのほうは、あなたのことを恋しく思って、あなたの善良さや美徳につい
て考える時を持てると思うわ。もちろんあなたの美点は、いつも私の側にあったのだけ
れど、人間というのは、大切なことをすぐ忘れてしまうもの。慣れてしまうと、まるで
太陽の光や、月影の祝福に気がつかなくなるのと同じなんだわ。いってらっしゃい。そ
して精神と身体を新たにして、今よりももっと明かるい、優れた人間になってーーもし
も今以上によくなるなんてことが、可能だったらですけれどーー帰ってきてください
な」
だがしかし、願いというものは、それが叶ったときにさえも、思ったとおりの形で実現
することはけっしてないのだ。第一に、エセルバーサは、ぼくの頭にくる振舞い方に気
がつかないらしかった。それでわざわざ彼女の注意を喚起しなければならなかった。ぼ
くは言った。
「気にしないでくれ。ぼくはどうも今晩は、まともじゃないみたいなんだ」
妻は言った。「まあ、なにかいつもと違うところがおありになるの?どこか悪いんです
か?」
「どこがわるいのかはわからない」ぼくは言った。
「でも、もう何週間もこんな
感じなんだよ」
「きっとあのウイスキーだわ」エセルバーサ。
「ハリスのうちに行くとき以外
は、触りさえしないじゃないの。ご自分でもいけないってことご存じのくせに。
頭が頑丈じゃないんですもの」
「ウイスキーのせいじゃない」ぼくは答えた。
「そんなものじゃないんだ。ぼく
が思うに、身体のせいじゃなく、精神的なものなんだ」
「また、ああいった批評をよんでいらしたのね」エセルバーサは、親身なようすになっ
た。
「わたしの言うことを聞いて、あんなものは暖炉にほうりこんでやればいい
のよ」
「批評のせいじゃないんだよ」答えた。「最近のやつは、かなり誉めてくれてるの
さ……一つか、二つはね」
「まあ、じゃあ何なのかしら?」エセルバーサ。「何か説明できる原因があるはずだ
わ」
「そんなものはないんだ」と答えた。
「そこのところが際だった特徴なのさ。ぼくはただ、異様な不安感にとりつかれている
ような感じ、としか説明できない」
エセルバーサは、ちょっと奇妙な表情をして、視線をなげかけた。ぼくにはそう思え
た。結局なにも言わなかったので、ぼくは自分で論じ続けた。
「生活の単調さというのはきついものだ。この平和で、平凡な至福の時。恐ろしくなる
んだよ」
「わたしはそういう生活に文句を言ったりしませんわ」エセルバーサはいった。
「だっておっしゃるのとは違う事態にだってなるかもしれないし、そうなったときは、
きっと今よりもっと気に入らないでしょうから」
「さあ、どうなんだろう?」とぼくは答える。
「とぎれることのない喜びの人生には、多少のつらさだって、有難い変化になってしま
うんじゃないだろうか。天国の聖人たちだって、ずっと続く静けさを、時々重荷に感じ
るのじゃないかと思うことがあるよ。不協和音に邪魔されることのまったくない、至福
の人生というのは、いつか絶え難くなっていくものだ。ぼくにはそんな感じがするん
だ」
ぼくは続けた。
「たぶん、ぼくはちょっと変わった種類の人間なんだろうね。時々。自分でもわからな
くなってしまうんだ」そして付け加えた。「時々、ぼくは自分自身が嫌いになることが
ある」
こういうささやかな演説は、抑さえられた感情をほのめかすことで、しばしばエセル
バーサの琴線に触れたものだった。だが今夜は、妻はおかしなほど、優しさに欠けてい
る様子だった。天国と、もし天国に住んだらそれがぼくに及ぼす効果についても、心配
する必要はないだろうと言う。起こらないかもしれない厄介事に自分から係わりに行く
のは愚かしい、と指摘した。
一方、ぼくが変わった奴であることに関しては、彼女の言い分によれば、心配したって
どうにもならないじゃない、ということだ。他の人間がぼくに我慢できるのなら、それ
でいいではないか。人生の単調さというのは、極めてありふれているので、彼女もぼく
の気持ちがよくわかる、と言った。
「わたしだってどんなに」エセルバーサ「たとえあなたからでさえ、時には離れたいと
夢見ることがあるか。そんなことご存知ないでしょうね。でも、実現しないってわかっ
ているから、わたくしはくよくよ考えたりしないのよ」
ぼくは、エセルバーサがそんなことを言うのをこれまで聞いたことがなかった。ぼくは
驚愕して、口にしようもないほど嘆かわしいことだと感じた。
「それは思いやりのない物言いだよ」と、ぼく。
「妻としてふさわしくないと思うな」
「そんなことわかってますわ」と答える。
「だから今まで一度も言ったことがなかったのよ。男のかたにはわからないのよ」エセ
ルバーサは続けた。
「たとえ、女がどれほど夫のことを好ましく思っていても、ときとして飽きることがあ
るって。わかってくださらないかもしれない。でも、どこに行くのか、なぜ外出するの
か、どのくらい長く出ているのか、そして、いつ帰ってくるのかなんてことを、どこの
誰からも詮索されたりせずに、一人でボンネットをさっとかぶって、好きに外出できた
らいいって、女がどれほど願っているかなんて、きっとご存知ないでしょうね」
「そりゃあ、たまにはは自分と子供達の好きなお夕食にしたいわ。あなただったら、見
ただけで帽子をかぶって、クラブに出かけてしまうような献立にね。時々、私には大事
だけれど、あなたが気にいらないってわかってる女友達をうちに呼びたい。
「自分が」好きな所に行って、好きな人に会う。自分が眠くなったら寝て、起きたいと
きに起きる。時々どんなにそうしたいと思うでしょう。二人の人間が一緒に生きるとい
うことは、お互いの要求を相手のために、犠牲にし続けるということだけれど、たまに
は束縛を少しばかり緩めるのもいいことなのかもしれないわね」
後で考えてみると、エセルバーサの言ったことはなかかなか鋭いと思う。でも、そのと
きは、僕は心を傷つけられて、不機嫌になったことを認めなければならない。
「君がそんなふうに」ぼくは言った。
「ぼくを放りっぱなしにしたいと望むなら……」
「まあ。わからずやなことをおっしゃらないで」エセルバーサ。
「ちょっとの間だけ、あなたから離れたいだけなのよ。ちょうど、あなたにだって一つ
や二つ、完全とは言えない面があるってことを忘れるのに十分な間だけね。そうした
ら、他の面ではあなたが素晴らしい方であることを思い出すでしょうし、お帰りを心か
ら待つことができるようになるわ。昔、二人が今のように始終顔をあわせなかったこ
ろ、いつもあなたに会うのを楽しみにしていたものよ。でも、太陽がいつもそこにある
から、日光に気がつかなくなってしまうみたいに、あなたのこともあたりまえだと思う
ようになってしまったのね」
ぼくはエセルバーサの口調が気に入らなかった。どうも彼女には、軽はずみな様子が
あった。ぼくたちの話し合っていたような話題にはふさわしくない気がする。女性
が、夫と3、4週間も離れることを楽しく想像するという事実は、そもそも好ましいこ
とだとは思えないし、ぼくが女らしさと呼ぶものとはかけ離れている。
これはまったくエセルバーサらしくなかった。ぼくは心配になった。もう、この旅行に
出かけたくないような気がした。もしジョージとハリスが居なかったら、あっさりとり
やめにしただろう。でも例によって、面子を保ちながら、考えを変える方法に思いあた
らなかった。
「まあ、いいだろうさ。エセルバーサ」
ぼくは答えた。
「君の好きにすればいいさ。ぼくって男から休みをとって、休養したいっていうんな
ら、さぞかし楽しいだろうな。だけど、不適切な好奇心だと言われないなら、夫として
伺いたいんだけれど、ぼくの留守の間に何をする気か尋ねてもいいかな?」
「あのフォークストンの別荘に行きたいと思うの」エセルバーサは答えた。
「ケイトと一緒に行きたいわ。あと、もしあなたがクララ・ハリスに、世話になってる
礼をしたいと思うのなら」つけ加えた。
「ハリスさんも一緒に出かけるように説得してごらんになったら?そうすればクララも
わたしたちと一緒に行けますもの。あなたたち殿方と一緒になる前に、三人、女同士で
それは楽しい時を過ごしたものだわ。旧交を暖めるのって素晴らしいことじゃないかし
ら?」エセルバーサは続けた。
「ねえ、ハリスさんを、一緒に行くように説き伏せられると思います?」
ぼくは努力してみると答えた。
「ほんとに、あなたっていい方ね」と妻。
「頑張ってちょうだいね。ジョージも一緒に行きたいと思うかもしれないわね」
ジョージが来ることには、たいして有利な点がないのじゃないかと、ぼくは答えた。な
んといってもジョージは独り者で、したがって彼の不在を嬉しがる人間は居ないのだか
ら。だが、女というのは、けっして皮肉を理解しないものなのだ。エセルバーサは単
に、ジョージだけ置いていくなんて不親切にみえるわと答えただけだった。ぼくは、彼
に聞いてみると約束した。
その夕方、クラブでハリスに会って、首尾はどうかと尋ねた。
ハリスは答えた。
「ああ、うまくいったよ。出かけるのにはぜんぜん問題ない」
しかしハリスの声の調子には、なにか不完全な満足を示すものがあった。ぼくはさらに
細かく追求してみた。
「ミルクみたいに大甘だったさ」ハリスは続ける。
「あいつは、ジョージのアイ
デアは素晴らしいし、ぼくのためにも、とてもいい事だと言うんだ」
「じゃあよかったじゃないか」とぼく。
「なにがまずいんだい?」
「なにもまずいことなんかないさ」とハリス。「ちょっと他にも、あいつが喋ったこと
がいろいろとあっただけさ」
「わかるよ」
「まあ、軽薄なたわごさ」とハリスは続けた。
「ぼくも聞いたよ」ぼくはいった。「奥方が同じことをエセルバーサにも吹き込んだ
からな」
「まあな。はめられたことは否定できないな。彼女が他の面で優しくでてくるだけに、
よけいなことを持ちだして議論したりできなかったんだ。結局こいつは、最低でも10
0ポンドの出費になりそうだぜ」
「そんなに?」
「100ポンド全部使ったって足りないだろうさ。見積りだけで、60ポンドだよ」
これを聞いて、ぼくはハリスに同情した。
「それに、料理用ストーブのことがある」ハリスは続けた。
「この二年の間、うちで起きたあらゆる災難は、料理用ストーブの責任だったんだ」
「知ってる」と、これはぼく。
「ぼくたちは結婚以来、7つの家に住んだ。引っ越すたびに、どの料理用ストーブも前
のより悪くなる。今のは、たんに無能というだけでなくて、卑劣なたちなんだ。ストー
ブのやつときたら、ぼくたちがいつパーティをひらくか知っていて、わざわざ最悪のタ
イミングで故障しやがるんだ」
「うちでは新しいのを買うことになっている」ハリスは言ったが、自慢そうな様子では
なかった。
「クララの意見では、二つの出費を、いちどきにまとめてしてしまえば、節約になるだ
ろうと言うんだ。ぼくが確信してるのはね」と、ハリス。「もしも女がダイアモンドの
宝冠を欲しいと思ったら、きっと婦人用帽子の費用の節約になるという説明を持ちだ
すってことさ」
「ストーブはいくらすると思う?」と、ぼくは聞いた。この話題には興味があった。
「知るもんか」ハリス。
「さっきのに加えて、20ポンド。そんなところだろ。その上ピアノの話も出たんだ。
ねえ、君」ハリスは聞く。
「いまだかつて、ひとつのピアノと別のピアノの間に違いがあるって気がついたことあ
るかい?」
「中には、他のよりうるさいものがあるように思えるね」ぼくは答える。「でもそのう
ちに慣れるものさ」
「うちのは、トレブル(高音)がまったくいけないんだ」と、ハリス。「ところで、ト
レブルってなんだ?」
「きいきいと高い音をたてる側さ」説明してやった。
「尻尾を踏み付けられたような音を出す部分だよ。名曲というのは、いつもそういうふ
うに盛り上がって終わるんだ」
「その部分が、まだもっと欲しいんだってさ」ハリス。
「古いのは十分に出ないんだ。古いピアノは、子供部屋に放りこまなくちゃならない。
新しいのを、居間用に買うんだ」
「他には?」
「いや」とハリス。「あいつもこれ以上は思い付かなかったらしい」
「帰ったらわかる」ぼくが言った。
「もう一つ思い付いているだろうね」
「何だい」と、ハリス。
「ひとシーズンまるまるのフォークストンの別荘さ」
「なんで彼女が、フォークストンの別荘なんかに用がある?」
「滞在するためだよ」ぼくは教えてやった。「夏のあいだずっとね」
「あいつは、ウェールズの親戚の所に行くんだ」とハリス。「子供達をつれて休養に
ね。招待されているから」
「だろうね」これはぼく。
「奥方は、フォークストンに出かけるまえに、ウェールズに行くだろう。でなければ、
ウェールズには帰りに寄るかもしれない。にもかかわらず、彼女はこの夏まるまる、
フォークストンに別荘を借りたがるだろう。ぼくは間違ってるかもしれないよ?君のた
めに、間違ってることを祈りたい。しかしぼくには、これは間違っていないという虫の
知らせがするんだ」
「この旅行は」ハリス、「ずいぶん高価なものにつきそうだな」
「だいたい初めから」ぼく。「くだらない思い付きだったんだ」
「あいつの言うことを聞いた我々が、馬鹿だったんだ」ハリスは言った。「あの男のせ
いで、いつかほんとうにとんでもない目にあうに決まっている」
「やつは、いつだって疫病神だったからな」賛成した。
「石頭なんだ」ハリスが加えた。
そのときホールから、手紙の有無を尋ねる声が聞こえて来た。
「なにもいわないほうがいいぜ」とぼくが提案した。「どうせやりなおすには遅すぎ
る」
「やりなおそうとしたって何の得もないからな」ハリスの答え。
「まあ、水回りとピアノはいつかはどうにかしなくちゃならなかったんだし」
やつは陽気な様子でやって来た。
「やあ」彼は言った。「どうだい?なんとかなったのか?」
ジョージの調子には、どうもぼくの好きになれないところがあった。ハリスもむっとし
たのがわかった。
「なんとかなるって、なにが?」ぼくは聞いた。
「なにがって、旅行さ」とジョージ。
今こそジョージに教訓を与える時だと、ぼくは思った。
「結婚生活においてはだね」とぼく。
「男が提案をする。女は従う。それは妻の義務なんだ。すべての信仰はそう教えてい
る」
ジョージは腕をくんで、上目使いに天井を見上げた。
「ぼくたちは、冷やかしや冗談を言い合ったりするかもしれない」ぼくは続けた。
「しかしこと実践に至れば話は違うんだ。ぼくたちは妻に、出発するとただ伝えただけ
だ。当然のことだが、彼女らは悲しんだ。ぼくたちと一緒に来たがっている。それが駄
目なら、ぼくたちに出かけないで欲しいといっている。しかし、ぼくらがこの問題につ
いて自分の希望を伝えたら、それで物事はきまりなんだ」
ジョージは言った。
「あのね。悪いけれど、ぼくにはわからないよ。しょせんぼくは独り者だ。みんなはぼ
くにああ言っては、こう言う。それぞれに違うことをね。ぼくは黙って聞くだけさ」
「そこが君の間違っているところなんだ。君が知識を必要としているなら、ハリスかぼ
くのところに来たまえ。そういう家庭の疑問については、ぼくたちが真実を話してやる
よ」
ジョージは感謝を述べた。そして、ぼくたちは当面の仕事にかかった。
「いつ、出発する?」
「ぼくに関するかぎり」ハリス「早ければ早いほどいい」
ぼくがこっそり思うには、ハリス夫人が他の何かを思いだす前に逃げ出そうということ
だ。次の週の水曜日にでかけることに決めた。
「どこ経由でいく?」ハリスが聞いた。
「いい考えがあるんだ」ジョージ。「君達は、当然、精神修養をしたいと願ってい
ると思うが?」
ぼくが言った。「修道院にはいりたいわけじゃない。でも常識の範囲内で言えば、答え
はイエスだな。つまり費用がかからず、個人的な負担がなければだ」
「できるよ」とジョージ。「もうオランダと、ライン川には行ったことがあるじゃない
か。だから、ぼくの提案は、ハンブルグまで船を使って、ベルリンとドレスデンに寄
る。黒森まで、ニュルンベルグとシュトットガルト経由で行こうよ」
「メソポタミアにも、なかなかいい所があるって聞いたがな」
ハリスがこっそりつぶやいた。
ジョージは、メソポタミアはちょっと道筋からはずれてると言った。だが、ベルリンー
ドレスデン間をとるのは、とても実際的だ。よしあしはともかく、ジョージはぼくたち
を説得するのに成功した。
「ぼくが思うにだね。自転車は」ジョージ。「前と同じで、ハリスとぼくが二人乗り
で、Jが……」
「ちょっと待ってくれ」ハリスが遮った。
「君とJにしてくれ。二人乗りはさ。ぼくは一人乗りがいい」
「ぼくには同じ事さ」ジョージは賛成した。「Jとぼくが二人乗り自転車で、ハリスが
……」
「自分の番の時だけならいいよ」ぼくが口をだす。「でも、ぼくは、旅のあいだ”ずっ
と”、ジョージを運んでいく気はないからな。負担は等分されるべきだよ」
「よし」とハリス「じゃあ、分担しよう。だが、ジョージがちゃんと働くというはっき
りした合意の元にだぜ」
「ぼくが何をするって」
「きみが働くんだ」ハリスは繰り返した。「なにがあろうと。特にのぼり坂ではな」
「なんてけちくさいことを言う奴だ」ジョージがいう。「君らは運動がしたくないの
か?」
自転車二人乗り(タンデム)については、常にこの不愉快な問題がつきまとってい
る。
前にいる男の理論によれば、後ろの者はなにもしていない。同じように、後ろの乗り手
にとっては、自分だけが動力で、前の奴はたんに息をはずませているだけなのだ。この
謎は永遠に解明されることはないだろう。一方では、力を使いすぎて心臓を痛めないよ
うに、と「分別」がささやきかけ、他方では、「正義」が、「なぜおまえだけが全部や
らなくてはならないのだ?こいつは辻馬車じゃない。やつは、おまえの乗客ではないの
だぞ」と尋ねている。それなのにパートナーが、「おい、どうしたんだよーーペダルを
無くしたのか?」と言って来るのだ。
ハリス自身、結婚生活の初期にかなり大きな失敗をしでかしたことがある。それ
も、相乗りの後ろの人間が何をしているかわからないためだった。彼が、妻と一緒に、
オランダで自転車旅行をしているときの話だ。道には石がごろごろしていて、自転車は
かなり上下に跳ねていた。
「しっかりすわっていろ!」ハリスは、後ろを振り向かずに言った。
そのときハリス夫人が、夫が言ったと思った言葉は、「飛び降りろ」だった。いったい
どういうわけで、「しっかり座ってろ」とハリスが言ったところを、彼女が「飛び降り
ろ」と聞いたのかは、二人のどちらも説明できない。
ハリス夫人によると、「もし、あなたが「すわってろ」と言ったのなら、どうして
あたしが飛び降りたりするはずがあると思うのよ?」
ハリスはこう言う。「もし俺が君に飛び降りて欲しかったなら、なんで「すわってい
ろ!」と言うと思うんだ?」
不愉快なしこりは過去のことだが、二人は今日に至るまで、この事について言い争って
いる。
説明をどのようにつけようとも、事実はただひとつで、つまりハリス夫人は飛び降
りたのだ。一方、ハリスは一生懸命漕いで離れて行った。妻が後ろに乗っているという
認識のもとに。
最初奥方は、ハリスがみせびらかすために、坂を駆け上がっているのだと思った。その
ころ二人ともまだ若くて、ハリスは時々そういう真似をしたからだ。彼女は、頂上につ
くなりハリスが地面に飛び降りて、さりげなく優雅に自転車に寄りかかって、妻が上
がって行くのを待っているつもりだろうと思った。
だがしかし、ハリスが頂上を越え、ながい急傾斜を猛スピードで下って行くのを見て、
彼女は驚きのため、つぎに怒りで、最後には恐慌のため、凍り付いた。彼女は頂上に駆
け上がり、叫んだが、ハリスは振り返りもしなかった。彼が一マイル半先の森の中に消
えて行くのをみて、座り込んで泣き出した。二人は午前中にささいなことでくいちがい
があったので、ハリスがそのことを根にもっていて、妻を置き去りにしたのかしらと
疑った。彼女は金を持っておらず、まったくオランダ語が喋れなかった。
何人かの人々が通りかかって、気の毒そうな顔をした。彼女はなんとか起こったことを
わからせようと努力した。人々はどうも彼女が何かを無くしたらしいと、見当をつけた
が、何を無くしたのかはわからなかった。彼女を近くの村に連れて行って、警官を見つ
けてくれた。警官は誰かが彼女の自転車を盗んだのだとの結論に達した。連中は、電信
を打って捜索作戦を開始して、4マイル離れた村で、古くさい型の婦人用自転車に乗っ
ていた不運な少年を発見することになる。少年が荷車で連れてこられたが、彼女は少年
も、少年の自転車も欲しがらないらしいので、彼を放してやり、ふたたび当惑している
しかなかった。
一方、ハリスのほうはとても楽しく走り続けていた。なんだか自分が突然に、前よ
り強くて、あらゆる点で優れたサイクリストになった気分だった。彼はハリス夫人だと
思い込んでいるものにむかって言った。
「この自転車がこんなに軽く感じられたことは、ここ数ヵ月ないな。思うに、ここの空
気のせいだろうな。ぼくの健康にいいんだ」
そして妻に「怖がるなよ」と注意して、その気になれば”どんなに”彼が速く走れるか
見せてやろうと言った。ハンドルの上に身体を倒して、気合を入れた。自転車はあたか
も生あるもののように道の上を跳躍し、農家や教会、犬や鶏が近づいては、飛び去って
いった。老人達は彼を見つめて、子供達は歓声を上げた。
こんなふうにして、彼は陽気に、5マイルほど前進した。
そのうちに、彼の説明によるところでは、何かが酷くおかしい、という感覚が徐々にわ
きあがってきた。妻の沈黙はかまわなかった。風が激しく吹いていて、自転車もがちゃ
がちゃとかなりの音をたてていたからだ。彼にせまってきたのは、なにか空虚な感覚
だった。後ろに手を延ばして探ってみた。そこには空っぽの空間以外なにも存在しな
かった。
ハリスは飛び降りた。いや、ほどんど転がり落ちた。そして来た道を振り返った。
道は暗い森の中に、白くまっすぐに延びていた。そこに生きた人間の姿は、ただ一つも
見あたらなかった。ハリスは自転車に乗りなおして、とって返して丘をのぼった。10
分とたたないうちに、彼は道が4岐に分かれているところに来た。そこで自転車を降
り、じぶんがどの岐からやってきたのか、思い出そうとした。
ハリスが考えこんでいるところに、ひとりの男が通りかかった。馬に横座りして。
ハリスは呼び止めて、妻を見失ってしまったことを説明した。男は特に驚いたり、同情
する様子ではなかった。話しているところに、もう一人の農夫が通りかかった。最初の
男が話を伝えていたが、どうも重要な事故というより、面白い話として話している様子
だった。二人めの男をもっとも驚かせたのは、ハリスがそんなことで大騒ぎをしている
ことらしかった。ハリスはどちらからもまったく理屈にあう言葉を聞くことができな
かったので、悪口雑言を吐きながら、再び自転車に乗って、運を天にまかせ、真ん中の
道をとった。
半分行ったあたりで、ハリスは、二人の若い女性と、間に挟まれた若い男一人という一
行に出会った。彼女らは、無駄なくその男を有効利用しているという感じだった。ハリ
スは彼らに、妻を見かけなかったかと尋ねた。相手は、彼女がどんな外見かと聞いた。
ハリスは、妻の事をうまく描写するのに十分なオランダ語を知らなかった。彼が言えた
のは、とても美しい、中肉中背の女性だということだけだ。明らかにこの説明は連中を
満足させなかった。つまり、その描写はあまりに一般的で、どんな男もそんなことは言
えるし、だとしたら、自分のものでない奥さんを、つかまえようとしているということ
だって有りえるではないか。彼らはハリスに妻の服装を尋ねた。ハリスはどうしても、
そいつを思い出すことができなかった。
ぼくは男というものが、別れて十分以上たった後で、女性が何を着ていたか思い出
すことができるか、疑わしいと思う。ハリスは、青いスカートと、それからなにかしら
首までつながっているものを思い出した。たぶん、ブラウスだったかもしれない。ぼん
やりと、ベルトのような像を記憶していた。でもどんなブラウスだったろう?緑だった
か、黄色か、それとも青?カラーがあったのか、それともボウタイで首を結んでいたっ
け?帽子には羽飾りがあったっけ、それとも花がついていただろうか?だいたい、帽子
をかぶっていただろうか?
もし間違った相手を追いかけて、何マイルも行かされたらという怖れのために、ハリス
はきっぱり明言できなかった。二人の女はくすくす笑いころげ、その時のハリスの精神
状態には、とてもいらだたしく感じられた。若い男は、明らかにハリスをおっぱらいた
いとの一心で、隣町の警察署を教えてくれ、ハリスはそこに行った。警察はハリスに一
枚の用紙を渡して、妻の外見を描写し、いつどこで彼女を紛失したのか、細かい点まで
届け出るようにと指示した。ハリスは、どこで彼女を見失ったのか知らなかった。わか
るのは、昼食をとった村の名前だけだ。そのときは彼女が一緒で、それから二人で出発
したことは確かだ。
警察官は疑わしそうな顔をした。彼らは三点の疑問をつきつけた。ひとつは、その 女性は本当にハリスの妻なのか?ふたつめは、ほんとうにハリスが彼女を見失ったの か?第三に、なぜ彼は妻を見失ったのか?しかし、多少の英語を話す宿屋の主人のおか げで、やっと疑惑をはらすことができたのだ。警察は手配をしようと約束してくれて、 夜には彼女を、ほろ付きの馬車にのせて、費用の請求書と一緒に連れてきた。再会は心 暖まるものではなかった。ハリス夫人は、芝居が上手な女ではない。いつも感情を押し 隠すことが苦手だった。この時は、まったくもって押し隠す努力なんかしなかったと、 彼女は今でも率直に認めている。
自転車の問題にかたがつき、あの永遠に繰り返される手荷物の問題が持ち上がっ
た。
「いつものリストさ。だろう?」ジョージは書き出す用意をした。
これはぼくが二人に教えてやった教訓だ。何年も前、ぼく自身がこのやり方を、ポ
ジャー伯父さんから学んだのだ。
「いつでも、荷造りを始める前にだ」伯父さんは言ったものだ。「リストをつくれ」
彼は、極めて段取りのいい男だった。
「一枚の紙切れをとって」彼はいつもこうはじめた。
「おまえがおそらく必要とするものをすべて書きとるんだ。それから内容を全部チェッ
クして、おまえがなんとかそれなしでやっていけるものが、ひとつも含まれていないよ
うにするのさ。寝床についているところを心に浮かべて見ろ。何を着ている?よし、そ
れを書き取れ。いっしょに、後の変更もな。そして起きる。何をする?顔を洗う?なに
を使って顔を洗う?石鹸だな?石鹸とそこに書け。全部書いてしまえ。それから服だ。
足から始めろ。何を履いている?ブーツ、靴、靴下。そいつらも書き込め。栓抜き?そ
れもだ。全部記録しろ。そうすれば何一つ忘れやしない」
これがいつも彼のやり方だった。リストがつくられ、伯父さんは注意深くそれを検討
し、いつも何ひとつ忘れていないように、注意した。それからもう一度はじめからおわ
りまで検討し、切り捨てることができるものは、全部線を引いて消した。
そして伯父さんはいつも、そのリストをなくした。
ジョージが言った。「一日か二日の旅に、充分なだけ自転車で一緒に持っていけば
いい。大きな荷物は、町から町へと送ってしまわないといけないだろうな」
「気をつけなけりゃいけないぜ」ぼくは言った。
「昔ある男を知っていたんだがね、彼は……」
ハリスは腕時計を見た。
「その男のことは、船の中で聞くよ」
ハリスが言った。「ぼくはクララと、ウォータールー駅で半時間のうちに待ち合わせて
いるんだ」
「この話は30分もかからないよ」ぼくは言った。「いいかい、こいつは正真正銘の話
で……」
「じゃあ、無駄にするなよ」とこれはジョージ。
「黒森ではよく夜に雨が降るんだってさ。話をそのときのためにとっておいてよかった
と思うかもしれないぜ。今やらなくちゃならないのは、リストを終わらせることだ」
あとで振り返ってみると、結局ぼくは、今にいたるまで、一度たりともその話を始める
ことができなかった。何かしらが常に邪魔をしたのだ。正真正銘、本当のところ。