住民参加型の意思決定プロセス
メトロの意思決定プロセスの最大の特色は、あらゆる局面での住民の参加が徹底して行われていることです。勿論、最終議決権は議会にあり、政策検討および立案は専門技術を持つ職員を中心に進めらますが、そのプロセスは行政主導ではなく、住民協議に基づく大変ダイナミックなものです。ポートランド地域では伝統的に住民自治が根付いている上に、憲章も州の土地利用法も住民参加を条文に盛り込んでおり、かつ一部のプロセスは憲章で明確に義務づけられているためです。具体的な住民参加の方法は以下のようなものです。
メトロ諮問委員会諮問委員会は議会、知事、そして職員に対する様々な勧告、助言を行うものです。メンバー構成は各委員会の目的により様々ですが、メトロの知事や議員、職員も出席して、隔週程度の頻度で集合しています。現在、設置されている12の諮問委員会に関する説明を下に添えました。なお、諮問委員会は市民参加室(Office of Citizen Involvement)によって、運営されます。メトロの会議への参加、および資料の公開議会から日常の職員の打ち合わせまで、全てのメトロの会議は住民が自由に参加することが認められています。特に、議会や諮問委員会では住民が証言を行う時間が必ず設けられており、それを受けて職員への詳細な作業支持が出されます。また、メトロは住民に請求されれば、全ての資料を公開する義務があります。これらの情報公開は法律で義務づけられています。住民ワークショップメトロ職員は計画の初期段階から住民を対象にしたワークショップを管轄地域のあちこちで開き、住民のニーズを探り、また計画への支持を取り付けていきます。通常のワークショップでは、150〜300人位の住民が参加します。これらのワークショップには、知事や議員も普段着で参加します。また、重要な意思決定の局面では、議員主導で住民ヒアリングを行うこともあります。これらは全て自発的に行われており、法律で規定されているものではありません。世論調査メトロは頻繁に住民への世論調査を行い、住民のニーズを探り、また計画への支持を取り付けていきます。マスコミ(テレビ、ラジオ、新聞など)、人の集まる場所でのパンフレット配布、郵便、電話、FAX、インターネットなど、考えうる全ての手段を用いています。先日の調査には、11,500もの住民が回答を寄せました。これらは全て自発的に行われており、法律で規定されているものではありません。
少数意見への配慮は不可欠であるとはいえ、まちづくりの原則は大多数の住民の利益の追及です。統計的に信頼できる与論調査によって、メトロの計画は多くの住民に支持されていることが実証されている以上、現在の計画の方向性は間違えていないと私は考えます。そして、今後重要なのは、さらにプロセスを改善し、計画に少数の声を反映していく作業です。先日、監査役からメトロの都市計画プロセスは、もっと信頼性を上げる余地があるという旨の報告書が出され、住民の間でも注目されています。こういった自浄機能がメトロに存在し、地域内でメトロの機能(時には存在意義そのもの)に関する議論が継続的に行われている事実は、ポートランド地域における住民自治の成熟の証拠であると思います。 |
メトロのまちづくりへ戻る
 メールはこちらへ
メールはこちらへ
このページは![]() の提供です。
の提供です。
無料のページがもらえます。
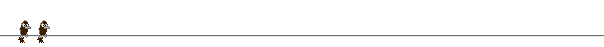
 ホームページに戻る
ホームページに戻る