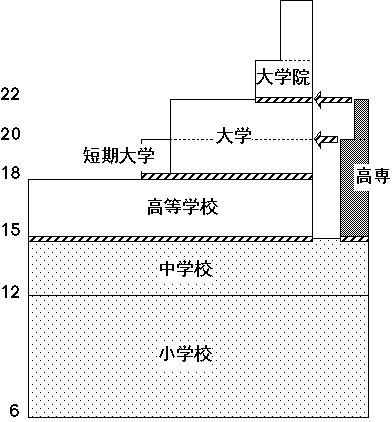
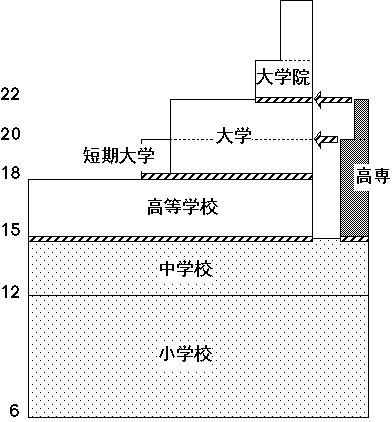
この図は、日本の学校制度における高専の位置づけを示したものです。高専(高等専門学校)は、中学校の卒業生を受け入れて、5年間または、7年間の一貫教育を行う教育機関です。従来は、高専5年を修了した卒業生は直接社会に出ることが前提で、即戦力となる技術者を養成するものと考えられていましたが、近年は、大学3年次への編入、または、2年間の専攻科を経て大学院修士課程に進学する者が増え、専門基礎教育を充実させる必要性が強まっています。
一方、高専に入学してくる学生の基礎数学力は、(皮肉なことながら)普通科の高等学校のように入試による輪切りがなされていないので、ばらつきが大きく、一斉授業だけでフォローすることは難しくなってきています。 高専の教員は、教育、研究職という位置づけで、高学年や専攻科の学生と行う研究活動と、低学年の学生と行う基礎教育のバランスを取りながら進める必要がありますが、近年は低学年学生に対する教育に重点を置かないと学科運営が難しくなりつつあります。
特に電気工学科では、第1、2年で学ぶ基礎解析や、微分積分学などの修得を前提に、第2学年以降の「電気回路」、「電気磁気学」等、電気工学基礎科目が配置されていますが、この前提条件は、近年、明らかに崩れてきています。
電気工学で用いられる数学力の定着には、基本的な計算演習を豊富にすることが必要ですが、学生諸君が時間外に行う演習量は不十分で、また、講義中に、演習時間を確保することも難しいようです。また、高専では、高等学校に比べて教員が研究に忙しく、講義時間外に系統的な演習を行う余裕はありません。
そこで、本システムは、授業時間外に、学生諸君が自主的に行う演習を支援して、彼らの演習不足を補うことを目的として、開発を始めました。システムは、高専の充実したコンピュータネットワーク(豊田高専には、全校学生約1000名に対し、情報教育センターに演習専用端末が100台、情報工学科、専攻科、図書館等に演習用端末約80台を持ち、研究室や学生実験用の端末を含めると、かなりの数の端末を比較的自由に使うことができます)を活かし、システム側からの制約を極力少なくして、演習の「失敗から学ぶ」ことを目指しました。