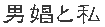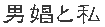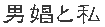
波がわたしたちを呑み込もうとする勢いで打ち寄せていた。
穏やかである筈の海は、わたしたちの休暇の最終日を締めくくろうとするかのように、荒々しい凶暴な顔を見せていた。分厚い雨雲に覆われた天空から、濁った雨の粒が、白い砂浜にぽつりぽつりと落下している。それは次第に強く激しくなり、最後には大雨とまでなったが、人気のない浜辺に取り残されたように並んで座るわたしたちのどちらも、そこを去ろうとはしなかった。
頭上で雷鳴が轟く。雨音が波音を掻き消し、波音もまた雨音を遮断した。波と雨との壮絶な二重奏が奏でられている間中、わたしたちは無言だった。おそらく、それぞれに異なる境遇に置かれたわたしたちは、その時ばかりは互いに同一のことを念頭に置いていたに違いない。
「いつ出るの」
半ば大声を出して藤真は問うた。
ホテルのチェックアウトはとうに済んでいる。所持していた荷物も駐車場の車のトランクに収まっている。いつでも出発は可能な状態だ。
藤真が云いたいことは、その言葉ではないことをわたしは理解した。
見ると、髪も衣服もずぶ濡れだ。わたしの心象風景と今の藤真はぴたりと一致していた。
「これから色々と忙しくなる。式のあとは二週間旅行に行くし、引っ越しもあるし、それが終わったら仕事もまた忙しい時期になる」
わたしは特に藤真の言葉にも答えず、意味のない話題を話していた。
わたしの云いたいことも、このようなことではないのだと、わたしは知っていた。
雨の雫が滝のように流れる前髪を払って藤真は云った。
「気をつけてな」
わたしは頷いて荒れる海をみた。
恐ろしい勢いで打ち寄せ、打ち返していく。高波だ。
わたしはこれが最後になるだろうと感じた。そしてそうするのは他でもない、このわたし自身なのだと気付いた時に、何故か笑い出したいような気持ちになった。ぼんやりと十年後の自分を脳裏に描いてみたが、それは波にさらわれて遥か彼方へ連れ去られてしまった。波が戻って来た時に、わたしはもう一度これが最後なのだと、確信した。
藤真の羽織っているシャツはボタンがはだけており、素肌が見えていた。その胸のやや上方、鎖骨の部分に朱色の斑が微かに痕を残していた。わたしは云った。
「それが消える頃かな。次に会うのは」
藤真はわたしの視線を辿って自分の胸元を見下ろし、頭の中で日を数えているようだった。常にその染みを身体の何処かにしるしている彼には、どれだけの日数でそれが癒えていくのか既に記憶しているようでもあった。
でもわたしはその時に考えていた。
その染みは、いつか誰か他の愛人たちの染みと重なり、交わってやがてはもう誰が誰のものやら判別がつかなくなり、いつまでも残っているような、既に消えてしまったような、それでいて本当のところは何も分からない、そんなものになるだろう。
そしてそれこそがわたしの望んだことだった。
「おれ仕事辞めようかな。また販売員でもしようか」
藤真は云った。
「どうして」
彼は笑った。
「云ってみただけ」
「やめるなよ」
とわたしは云った。
藤真は不思議そうにわたしを見た。わたしは自分の利己心を意識してそれを打ち消す為に彼を引き寄せて抱いた。
わたしたちは砂浜で抱き合い、雨水が身体を冷やさぬように熱烈に身体を重ねた。わたしたちに可能なのは唯一それだけだった。わたしたちはセックスしかしなかった。それだけがわたしたちの未来だったのだ。口に出したとして、言葉は全て波にさらわれることが分かっていた。
わたしたちは無力だった。だがそれは力を持たないから無力なのではなかった。
力を誇示しないから無力なのであった。
藤真はわたしの胸元の片隅に、朱い染みを残した。
会話はない。肉体を酷使した気怠い疲労感で四時間余りの道のりを、わたしたちは無言で通した。濡れそぼった身体を暖めようとしても無駄だった。
藤真は、都心へ近付いたところで車を降りた。中年の男の客に詫びを云い、埋め合わせをしなくてはならないと云った。わたしもそれを必要なことだと感じ承諾した。
雨など一切降っていない町並みに、わたしたちは不自然に乱れただらしない恰好で存在していた。わたしたちの存在自体が不自然で歪だった。ドアを開け、トランクから荷物を取り出しまたウィンドウの側へ戻って来た藤真は、初めて会った時よりも青ざめた不健康そうな顔をしていた。
いや、何も変わっていないのかも知れない。ただ彼の周囲には不幸因子が蔓延っているというだけで。わたしもおそらくは、瓜二つの顔つきをしていたのだろう。
窓ガラスを開けると、多少屈み込んだ姿勢で藤真は云った。
「じゃ」
わたしは口の中で同じ言葉を小さく反芻し、頷いた。
短い間だけわたしたちは奇妙に視線を停滞させて互いを見ていた。でもどちらも何も云わなかった。藤真は背を向けると都会の喧噪の中へ歩き出して行った。わたしはその後ろ姿を見送った。
あるいはわたしは、その時に藤真を引き止めることが出来ただろう。
藤真もまたわたしの元へ引き返すことが可能だったろう。
わたしたちは共通の言葉を胸の内に埋葬していた。わたしは藤真を振り向かせて、それを云うことも十分出来た。その一言だけで、わたしたちは永遠となった。
わたしは一切を捨て、一切を失い、そして全てを得ることが出来た。
その一言。
まだ言葉にはならず、曖昧な感覚として身体に滲みているそれを、わたしが気紛れか何かで、あるいは自暴自棄にでもなって口にしさえすれば、それだけでわたしと藤真はいつまでもわたしと藤真であり続けただろう。
繋ぎ止める一言を、切り札をわたしが口にしたのなら。
わたしはそうする代わりに、アクセルを踏んで車を発進させた。
これがわたしたちの最上のあり方なのだ。
わたしと彼のこれからの人生のその気の遠くなる程長い道程で、わたしちたちの取りうる最善の方法はこれだったのだ。この一つを失ったおかげでわたしたちは今後ありとあらゆるものを手に入れるだろう。しかし反対に、もしこの一つを手中にしたのなら、わたしたちは来るべき未来の全てを喪失しただろう。その選択が間違っていなかったことは、この後わたしたちがそれぞれに身を持って体験していくことだろう。
何を犠牲にすべきかわたしたちは知りすぎていた。
知っていた為に、そうせざるを得なかったのだとも云える。
何をしているの。
背後から声をかけられわたしは振り向いた。
この頃ではすっかりわたしの妻を気取ったトモ子が興味津々にこちらを見ている。わたしは遠く眼前にその頭頂部だけを見せている街外れの橋を眺めていた視線を室内に戻し、全ての荷物が取り去られだだっ広い空間と化しているかつてのわたしの部屋を見回した。新居を見に行くというので張り切っているトモ子を従えて、マンションを後にした。
新居には既にわたしの荷物とトモ子の荷物が運ばれており、頼んでおいた家具も整っていた。一通りを間取りを見て取って、トモ子は満足そうに笑顔を向けた。その日は片づけはせず、そのまま街へ出て食事をした。
休日ともあって人出の多い大通りを歩いている時、トモ子はわたしの耳元で囁いた。
あたしね、今迄描いてきた夢が全部叶う幸福をこれから毎日味わえるわ。あなたと結婚出来て、それから沢山の人たちの祝福を受けて式を挙げて貰える。ウェディングドレスも、愉しみにしててよ。あたしはオーダーメイドが夢だったの。女の子が生まれたら、その子にあげるのよ。毎日仕事に行くあなたを送り出して、花の咲いている庭のある家にあたしたちは住んでいて、あなたの為にご飯を作る。本当にこれからが愉しみなの。でもね。
そこでトモ子は一段と声を低くして、気恥ずかしそうに云った。
まだ恋人同士でいる内に、一度だけあなたとホテルに泊まってみたい。
些細で他愛なくちっぽけなトモ子のもう一つの夢をわたしはその日の内に叶えることにした。トモ子も最初からそのつもりであったのか、躊躇うことはなかった。
ホテルに入ると、初めて見る内装にいちいちトモ子は驚き、悦んでいた。秋は次第にその速度を早め近付いてきたが、室内は空気が乾燥し、異様なまでに暑かった。トモ子は不快を訴え、その原因を突き止めようと室内を探索していた。わたしは壁際の装置に向かって進み、スイッチを押して暖房を止めた。トモ子は何か驚いた様子で、それからわたしの手慣れた仕種に傷ついたようだった。
初めてじゃないのね、別に構わないけど。
さっきまでの無邪気な自分を恥じるように云って顔を赤らめた。
わたしはトモ子のいじらしさを想う反面、その言葉で別のことを想起していた。
別々にシャワーを浴びた。わたしは自分の身体の胸の端に、既に朱色の斑がなくなっていることに気付いた。痕跡すらなくそれは姿を消していた。そうするとわたしが残した染みの方ももうとうに消えている筈だった。
わたしは一人笑った。
曖昧な口約束は決して果たされることはない。その言葉が希望に酷似し、哀願に近いものであっても、それは守られるべきでない約束であった。
今後わたしの身体に同じような染みがつくこともあろう。しかしその染みはもう消えてしまった朱の斑とは同じ重みで存在することはないのだ。全く別の意味すらもない染みとなるだけだ。
あの小さな斑に隠された、熱狂する程の想い。言葉には託せず、形を変えてわたしの身体に存在したそれは、今はもうないのだが、わたしはきっとその朱の斑が秘めていた幾多の感情を忘れることはないだろう。
絶対に有り得ないだろう。
今夜も彼は誰か他の男の腕に抱かれている。
そうしてわたしのことを想っているに違いないのだ。
白いシーツに包まれてわたしを待ちわびているトモ子の元へ歩き出しながら、わたしはそれを確信した。
完
|| 後書き ||
|| 伽藍堂 || 煩悩坩堝 ||