 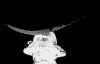 |
 「線路の上を走るもの」が“電車”と総称されている例が、最近は多いようだが、私はそれが嫌いだ。何故なら、電力で動かないものが多くあるからである…古くは“汽車”と言ったので、そういう言い方も未だにあるが、これは蒸気機関車を念頭に置いた表現である以上シックリしない…ということで、私は中立的な表現ということで“列車”という言い方を好んでいる… 「線路の上を走るもの」が“電車”と総称されている例が、最近は多いようだが、私はそれが嫌いだ。何故なら、電力で動かないものが多くあるからである…古くは“汽車”と言ったので、そういう言い方も未だにあるが、これは蒸気機関車を念頭に置いた表現である以上シックリしない…ということで、私は中立的な表現ということで“列車”という言い方を好んでいる…北海道内の長距離列車は、その多くが鉄道技術用語で言う“電車”ではない。何故なら“未電化区間”が圧倒的に多いからである。線路が写っている写真を、少しだけ注意してご覧いただきたいが、北海道の線路では、線路の周辺に電柱が無く、線路の上に電線も無い場所が多いということがご理解いただけるであろう。 “未電化区間”では、ディーゼルカーが活躍している。“汽動車”(きどうしゃ)という表現もある。数両からなる編成に動力装置が分散配置されていて、線路上を自走するものが一般的である。輸送量が少ない場所向けに一両のみで動ける仕掛けになっているものもある。これは電車も同じなのだが、電車は車両の屋根にパンタグラフが付いていて、電線から電力を取ってモーターを回す。ディーゼルカーは燃料でディーゼルエンジンを動かす。 出発を待つ列車は、ガタガタとエンジンを温める音を立てている。地元稚内の周辺で活躍する、寂しく一両で走る各駅停車も、この特急<スーパー北斗>もそれは同様である… 因みに北海道内で電車と呼んで全く差し支えの無いものが活躍している、或いは活躍出来るのは、小樽から旭川までと、室蘭から札幌まで、函館から青函トンネルまで位なものである… |
 上段の写真は、運転台を備えた列車の先頭だが、正面は車両を増結して繁忙時に対応するなど出来るよう、“貫通扉”が備えられている。見通しが良いように高くなった場所に運転台が設置されており、貫通扉を利用する場合は通路となる場所から線路が覗ける。
上段の写真は、運転台を備えた列車の先頭だが、正面は車両を増結して繁忙時に対応するなど出来るよう、“貫通扉”が備えられている。見通しが良いように高くなった場所に運転台が設置されており、貫通扉を利用する場合は通路となる場所から線路が覗ける。