 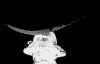 |
 多少厳かな気分で参道を進み、金堂や宝物殿の辺りに来ると、しらける程俗な雰囲気になる。地元の文化センターにある、約1200名収容の大ホールでイベントがある際も、こんなに雑然と人が集まっている様は見受けられない…次々に小旗を先頭にした団体が押し掛けて来る。ふらりと一人でやって来た者が入り込む隙を見付けるのが大変な位だ。団体の陰になって、何処で拝観券を入手するのか判らなかったが、少しだけ人の波が切れた時、様子が見えた。 多少厳かな気分で参道を進み、金堂や宝物殿の辺りに来ると、しらける程俗な雰囲気になる。地元の文化センターにある、約1200名収容の大ホールでイベントがある際も、こんなに雑然と人が集まっている様は見受けられない…次々に小旗を先頭にした団体が押し掛けて来る。ふらりと一人でやって来た者が入り込む隙を見付けるのが大変な位だ。団体の陰になって、何処で拝観券を入手するのか判らなかったが、少しだけ人の波が切れた時、様子が見えた。 |
 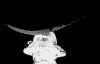 |
 多少厳かな気分で参道を進み、金堂や宝物殿の辺りに来ると、しらける程俗な雰囲気になる。地元の文化センターにある、約1200名収容の大ホールでイベントがある際も、こんなに雑然と人が集まっている様は見受けられない…次々に小旗を先頭にした団体が押し掛けて来る。ふらりと一人でやって来た者が入り込む隙を見付けるのが大変な位だ。団体の陰になって、何処で拝観券を入手するのか判らなかったが、少しだけ人の波が切れた時、様子が見えた。 多少厳かな気分で参道を進み、金堂や宝物殿の辺りに来ると、しらける程俗な雰囲気になる。地元の文化センターにある、約1200名収容の大ホールでイベントがある際も、こんなに雑然と人が集まっている様は見受けられない…次々に小旗を先頭にした団体が押し掛けて来る。ふらりと一人でやって来た者が入り込む隙を見付けるのが大変な位だ。団体の陰になって、何処で拝観券を入手するのか判らなかったが、少しだけ人の波が切れた時、様子が見えた。 |
 拝観券を入手し、宝物殿と金堂を見学することにした。 拝観券を入手し、宝物殿と金堂を見学することにした。宝物殿の入り口横に、地元信金のキャッシュディスペンサーを発見した。ここでお金の出し入れをすると、何かご利益でもあるかもしれない… 宝物殿は、一種の美術館であった。金堂は、壊れ易い金堂を、小ぶりなビルでスッポリ覆ったものである。 中尊寺が興って、奥州藤原氏の保護を得て栄えていた頃、日本の仏教界では空海の真言宗に連なる密教が盛んだった時代である。空海が都で本拠地にしていたという京都の東寺−京都駅の比較的近くに、高い五重塔が聳えていてお馴染み…−にも密教美術の傑作が見られる場所があったが、中尊寺の宝物殿には、それらに劣らない精巧なものが多く納められていた。金堂は、文字どおり全て黄金細工という趣の、見事と言うより他に表現が見当たらないものである。 こうした見事なものに触れ、1000年の昔を偲ぶのも良いが、通勤ラッシュの地下鉄のような状況では如何ともし難い…中国人の団体が来ていると見受けられ、金堂では中国語の説明テープが大音量で鳴り、「恐れ入ります、詰めてください!」の放送が鳴り響き、内部の温度も上昇して汗が噴出す始末である。 |
| PREVIOUS NEXT |