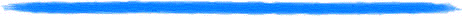
国際結婚について
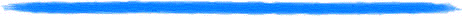
国際結婚をしていると、いろんな人から「大変でしょう」とまず言われる。何が大変なのか、よくわからないが、とにかく「大変」らしい。(国際結婚のお仲間、やすちかさん、健さん、どうですか?大変ですかねぇ)
恐らく、日常生活の文化、言語の違いの事だと思うが、特に意識することはない。これも慣れの問題です。
結婚する前から、そのくらいは承知しているので、後で苦労するという程の事でない。確かに、どちらかが、相手の言語のネイティブスピーカーでない以上、伝達出来るボキャブラリーには限度がある。微妙な言い回しが、母国語のようにいかないのも、事実です。
しかし、微妙な言い回しを使い分けないと、家庭の会話が成り立たないようであれば、逆の意味で大変問題です。たとえ言語が同じでも、伝わらない夫婦は所詮だめです。
口喧嘩になれば、当然母国語の方が簡単だから、お互いに自分の言葉になる。口喧嘩というのは、相手に伝えるのが目的でなく、自分の怒りを昇華させる為に言葉にしているだけだから、相手が理解しようがしまいが関係ない。
我が家で、強いて言えば、食生活の違いの問題はある。私の欧州生活も10年目に入り、生活習慣はかなり、現地化してしまっている。しかし、どうしても変わらないのは、食べ物の嗜好である。これも言語と同じで、幼児期に形成されるらしい。
私は、朝食には米、味噌汁、漬けもの、焼き魚が欲しい。勿論、焼き立てのパン、オランダの美味いチーズ、こってりしたバターにジャム、コーヒーの朝食も好きだ。
しかし、長期間、朝食に米がないと、どうしても寂しい。昼食、夕食はもうこだわらない。何故か、朝食だけはこだわりがある。理由は分からない。日本にいたときは、パンの朝食をずっと毎日続けていたのに、、、
かくして、朝食は別メニューです。自分の分は自分で作る。息子は和食党でして、私の味方です。
実際に、経験しないかぎり、必要のない知識でしょうが、一体国籍が違う場合の結婚というのはどうなっているのだろう?と疑問をお持ちの方は多いでしょう。
これは、相手国により全て違います。だから一概にどうと言えないのです。ご存知のように、世界中の国が一夫一妻制でありませんし、何を以って婚姻成立とするかの基準も違いますので。
国際結婚は 両国において、婚姻の手続きを終えて初めて婚姻が成立します。 従って
の2つのケースがあります。("International Marriage Reference on the WEB"より引用)
私の場合、物理的にドイツにいた事と、どうせ日本でのこの手の手続き体制は、後れていて融通が利かないのは目に見えていましたので、迷わずドイツ法に基づいた婚姻を済ませてから、日本に後で届ける後者を選びました。
さて、まずドイツの法制上、私に要求された書類
それに加えて、婚姻の届出書を妻と連署して、ドイツの戸籍役場に出す。
この後市役所に8日間公示され、その後簡単な面接がある。
しばらくしてから、結婚式の日取りを選び、公証人立ち会いにより、法的な結婚式を行う。この際、新郎新婦はそれぞれ、血縁者以外の証人を立てて書類に連署してもらう。
後々離婚係争など生じたときには、この時の証人は関係者として、呼び出しをくらうそうだ。私の場合は、大学の同級生に証人になってもらったが、彼は既に転勤して日本に帰国してしまった。この後必要があったときにはどうすんのかな。
ドイツの戸籍編成は、国籍は必要とされていないらしい。日本人のままなのに、私の名前は正式にドイツの戸籍に記載されている。
これは役所の手続きで、教会での結婚式や披露宴は別途行ったので、その日は二人で写真館に行って記念撮影しただけ。
本当の結婚式はやはり教会結婚式という習慣がいまでもある。ただし、ドイツの場合、正式なキリスト教徒でないと、教会での結婚は出来ない。
私の場合、日本でカトリック教徒として洗礼を受けていたので、日本の教会から洗礼証明書(pro migrante)を取り寄せて教会に提出した(なんとラテン語で書いてあった、いまでもこの世界ではラテン語が公用語のようである)。
これで終わりかと言うと、まだあります。今度は日本の戸籍法上の手続きが残っている。
ドイツでの婚姻成立の日から3ヶ月以内に、日本法での婚姻届を提出して戸籍編成をしておかないと、戸籍法違反になってしまう。
またいろいろ書類を作るはめになった
という訳で、えらい厄介な手続きだった。もう二度とやりたくない(普通二度やろうと思って結婚する人はいないと思うが)
国際結婚を考える人がいたら、私はまず反対しない。外国人の男がカッコイイからとか、日本が嫌で、国際結婚すれば外国暮らしが出来るというような考えの人には、勿論反対する。そこまで甘いもんじゃない。
100年前なら、北海道の人が鹿児島の人と結婚するだけでも、大騒ぎだっただろう。
時代は確実に人間の行動範囲を変えている。たまたま、結婚しようと言う相手の持っているパスポートが、自分のと違うだけであり、それしきの事で踏みとどまるのは、逆におかしいと思う。
国籍が違ったって、相手は同じ人間である。もっとも、一夫多妻制が認められている国の男性と結婚する女性は、自分以外の妻がいても平気かどうか、自問してほしい。
遠い国の人だといっても、いまや、一日あれば、地球の裏側だって行けるのだから。
私は、東京で仕事しているころは、盆正月くらいにしか里帰りしていなかった。今でも年に最低でも一回は、里帰りしているから、なんら変っていない。
1997年7月17日
©1997 copyright Hiroyuki Asakura