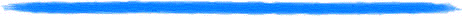
趣味の映画
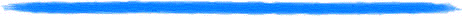
ベネチア映画祭で、北野監督の、「HANA-BI」受賞のニュースを、当地オランダのTVでも流していました。
どうも、近頃の風潮として、映画の評価をする時に、アカデミー賞ばかりが注目され、伝統あるベネチア、カンヌ、ベルリン映画祭での受賞というのは、取り上げかたが少ないのは残念だ。
私は映画が結構好きだ。学生時代から暇さえあれば、映画館に通っていた。最近は、家庭を持ってからなかなか、そうも行かず、貸しビデオで我慢しているが、映画館の雰囲気も好きです。
大画面と大音響に囲まれて、暗い映画館で見れば、映画の世界にどっぷり漬かることが出来る。
ホームビデオだと、スリルある場面で、どっかのあほが電話かけてくる、ほろりと泣かせる場面で、ガキが泣き出してぶちこわしになる事もある。
私個人の映画趣味から言うと、アカデミー賞の受賞基準のレベルは、かなり低い。あれは、ハリウッド映画の為にある賞で、内容を競うよりも、金をつぎ込んで造り、如何に観客動員数を商業的に稼げるか、という基準で決まっているように思える。
私は、ハリウッド映画に興味がない。その場で楽しませてくれるけど、繰り返し見たいと思う作品は、あまりにも少ない。
人間の感情のひだを、映像に投影しきれる作品も少ない。これは、単細胞なアメリカ人を観客の基準に置いているから、あまり、複雑で観客に、考える余地を残すような、含みのある映画を作っても受けないからだろう。
スピルバーグの作品なんかを見ていると、この人は、もっといい物を作れる力があるのに、気の毒に、ハリウッドの商業主義に合わせるために、自分が作りたい物を、わざわざ押し殺しているようだ。
「Independence day」を見て、がっかりを通り越して、私は憤慨した。こんなクソ映画どこがいいのか理解できない。
完全に、木戸銭返せ!のレベルだった。
でも、US本国では、観客に感動を巻き起こし、大ヒットを記録したというから、改めて、平均的アメリカ人のセンスの低さを認識させられた。
かの国では、7月4日は特別な意味を持つのかもしれないが、それにしても、ひどい映画だった。
ずいぶん前だが、アメリカ人と映画の話をしたことを、思い出した。
映画好きだ、というので、お互いの好きな映画監督なんかの話を、始めたが、まったく噛み合わない。
私が、好きな監督は、ゴダール(仏)、ヘルツォーク(独)、ヴェンダース(独)、ブニュエル(スペイン)、エリセ(スペイン)、フェリーニ(伊)、ヴィスコンティ(伊)、ベルトルッチ(伊)、ワイダ(ポーランド)だと、ならべると、相手は困惑した。
ひとりも知らないという。ここで私が語っているのは、全部ヨーロッパの映画だった事に気がついた。ハリウッドの映画監督が一人もいない。彼は、コッポラやスピルバーグ、ウッディ アレンがいいと言う。
アメリカ映画をこき下ろすのも、失礼だから言わなかったけど、どうもアメリカでは、国産映画以外が上映される事は、どうも少ないようだ。
本当に、ヨーロッパの古い映画を見る機会が、少ないらしい。「天井桟敷の人々」「道」「灰とダイアモンド」、どの話題も、相手は「知らない」の一辺倒。
やっぱり、アメリカ人は、自分たちが世界の中心に住んでいて、外界になにがあるのか、基本的に興味をもっていないようですね。
世界には、いい文化があちこちに、散在しているのに、それを学ぼうとする姿勢がないのは、勿体ないですね。
これは、日本人に対しても言えることですけどね。
©1997
copyright Hiroyuki Asakura