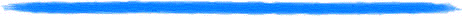
ベルリンの壁 私の怒り
(命をかけて自由を求めた人たち)
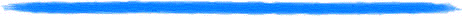
私がドイツに移り住んだ1988年は、まだ冷戦が終わっていなかった。雪解けムードが出て、何かありそうだなという雰囲気は既にありました。
ドイツは当時ドイツ連邦共和国(西ドイツ、元首コール)とドイツ民主共和国(東ドイツ、元首ホーネッカー)の分断国家でした。
このへんの経緯と、ベルリンの壁については、興味を持っている人以外にはわかりにくい話なので、少し詳しく補足しておきます。
第二次大戦後の終戦処理の結果、ヒトラーの率いた、旧ドイツ帝国は1949年に戦勝国の米英仏ソの統治下に移り、米英仏の占領地区は西ドイツ、ソ連占領地区は東ドイツとして独立宣言をしました。
西ドイツは暫定憲法として基本法を発布し、国境の分断により東ドイツに編入されたドイツ人も、亡命を求める者は、西ドイツ国民と同様に庇護と市民権を与える旨規定しました。
この分断状態も、そう長く続かないだろうと、当時は誰もが思っていたので、「暫定憲法」だったのですが結局、その後50年間ドイツは統一されなかったので、そのまま憲法として定着してしまいました。
また、反共軍事同盟NATOと、防共軍事同盟ワルシャワ条約機構が成立して、冷戦が開始したのはこの時です。
しかし、その一年前の1948年に、別の問題が発生していました。
旧ドイツ帝国の首都ベルリンは、地理的にはソ連の占領する東ドイツ地区の中にある飛び地でした。ベルリンだけはソ連の単独統治を認めず、米英仏ソの共同統治下におかれました。
ソ連はこの飛び地に、米英仏軍が駐留する事を好まず、ベルリンを孤立させて事実上東側に組み込もうとしました。これが有名な1948年のベルリン封鎖です。
ベルリンに通じる陸路を封鎖されたために、西ベルリン市民は兵糧攻めにあったのですが、米国を主導に、物資の大空輸を西側からパラシュートで運び続けて、西ベルリンの統治は保たれました。
この西ベルリンがあったため、東ドイツの人たちはいつでも西ベルリンに逃げ込んで亡命することができました。
戦後10年が経ち、西ドイツの経済復興が成功し、生活レベルの差がつき、思想統制の締め付けが強くなると、続々と東ドイツの人は西ドイツに、亡命を始めました。
業を煮やした東ドイツは、この亡命者の流れを止めるため、1961年8月に突如ブランデンブルグ門を境に、有名なコンクリートの壁をあっと言う間の早業で築きあげました。
1963年には、NATOが、西ベルリンを何があっても死守する姿勢をアピールするために、米国のケネディ大統領も自ら、ベルリンの壁の前を訪れて、西ベルリン市民の熱狂的歓迎を受ける中、ドイツ語で
"Ich bin ein Berliner" (私はベルリン市民だ)と宣言する有名な演説を行ったわけです。
NATOとワルシャワ条約機構で、ヨーロッパは東西の軍事境界線ではっきりと2分割されました。ここで見落とせないのが、ユーゴスラビアでした。
ユーゴは、日本あたりから見ると、社会主義国家として、東欧の中に一緒にされる事が多かったのですが、カリスマ的なティトー大統領が多民族にまたがる小国を連合させて、米国にもソ連にも靡かず、第三勢力を標榜してNATOにもワ条約機構にも入りませんでした。
逆にこのような独立を死守するため、バラバラの多民族が結集して国家を保ったので、冷戦が終結すると逆に、統一国家の意味がなくなり、ご存知の激しい内戦が始まってしまったのです。
しかし、ユーゴ以外の東欧諸国はソ連の軍事圧力に屈し、自由民主化の動きがあれば、すぐさまソ連の軍事介入を受けて、つぶされました。チェコでは、プラハの春(「存在の耐えられない軽さ」、って映画見た人は知ってるね、ジュリエット ビノシュが可愛かった!)とか、ハンガリー動乱なんかが、その例です。
それを正当化するために、ソ連はブレジネフドクトリンを発表します。「社会主義を守る為ならば、一国の主権よりも優先する」と言うやつです。
ベルリンに話を戻すと、社会主義を脅かす反共主義者や亡命を企てる者は、国家公安警察(Stasi)に殺されても、文句言えない状況でした。
ヴィム ヴェンダース監督のヒット作「ベルリン、天使の詩」という作品で、主人公の天使が、サーカス団のブランコ乗りの女に恋をして、人間に堕落するシーンが、丁度ベルリンの壁の横でした。
人間になる前は、東側の無機質な壁。人間になった途端に西側の落書きだらけの壁際にいたのは、まさに西ベルリンが人間性を表現できる世界であり、対照的な世界が東ベルリンです(私の勝手な解釈ですが、見た人はそのシーンわかるでしょう)。
東西の雪解けの象徴として、1989年の11月9日のベルリンの壁開放は誰でも知っている事件です。1988年からドイツに来た私は、丁度よいタイミングでその歴史的瞬間を体験できました。
しかし、実際には、ベルリンの壁が開放される前に、長いやり取りがあったのです。
ドイツに来て、しばらく慣れて、ドイツ語の新聞やニュースが分かるようになった1988年だったと思います。東独のLeipzigで、民主化を求める人達の大規模なデモがあったという記事を読みました。
へぇ、こんなデモが許されるようになったのかという感想を持ったんですが、それほど大きな扱いではありませんでした。まだその頃は大騒ぎしてなかったんです。
しばらくして、ハンガリーがオーストリアとの国境を分断していた鉄条網を撤去するという電撃的なニュースが伝えられました。
最初はその意味がよく分からなかったのですが、要するに、鉄のカーテンの間に隙間が出来たということです。ということは、東独の人は自由に行き来できるハンガリーを使って、永世中立国オーストリアを目指せば、西ドイツに亡命できる可能性が出てきたのです。それ以来、連日このルートを目指して亡命希望者が殺到しました。チェコスロバキアの西ドイツ大使館にも亡命希望者が、つめかけました。
前述の西ドイツ基本法の規定により、亡命希望すれば東独国民は簡単に国籍、市民権を取得できた上に、支度金として西ドイツ政府から100マルクが支給されました。
こうなったら、人の流れを止めるのは不可能です。体制を維持しようと試みた東独政府は国民に完全にそっぽを向かれ、最後には11月9日にベルリンの壁の自由通行を許可し、あっと言う間に国家主権も形骸化して、ドイツ統一を迎えました。
その日、私は他の銀行の資金ディーラーと会食があり、結構酔っ払って帰宅してTVをつけました。
すると、ニュースでアナウンサーが興奮して「信じられないような事件です。ベルリンの壁が開放されました」と伝えていました。
ただ、突然の事だったので、カメラ中継は間に合わなかったようで、何がどうなっているのかアナウンサー自身もわかっていないようでした。私も酔っていたので、「ん?聞き間違えかな」と思いました。
翌日の朝のニュースで、壁の上に人がよじ登って立っている、有名な光景が映し出され、このニュースが真実であることを、私もようやく確信しました。
野次馬根性旺盛な私は、記念すべき光景を見たくて、車を飛ばしてベルリンに行きました。
ハノーバーから東に向かい、国境通過ビザを買ってベルリンにつくまでにずいぶん時間がかかったのを覚えています。なにしろ東独地域では、制限速度が100km/hでした。
ベルリンは、快晴。ご多分にもれず、壁に上って記念写真を撮り、周辺を歩き回りました。
記念に壁を削る為のハンマーとノミをレンタルして、小遣い稼ぎをしている少年達、東独の軍服や、ソ連軍アーミーグッヅの不法路上販売などで、ごった返し、平和を楽しむ雰囲気が漂っていました。
有名なブランデンブルク門は、戦前の旧国会議事堂ライヒスタークのすぐ側にあります。確か壁の向こうには、東ベルリンのアパートが立っていましたが、そこから飛び降りて壁の反対側に亡命するのを防ぐために、壁に面した部屋は、すべてコンクリートで塗り固めてあり、不気味な冷たさを感じました。
わたしが、上に延々と長い話を書いてきたのは、これから下の事を説明したかったからです。ここまで読んでくれた人ありがとう。
ライヒスタークのわきに、小さな墓標がいくつか立っています。これは、東独から自由を求めて亡命を試みたが、望み果たせずに射殺された犠牲者のために立てられたものです。目立たない一角ですが、今でも献花が絶える事はありません。
ここで、私はものすごいショックを受けたのです。墓標に刻まれた死亡日を見ると、たしか、1987年の犠牲者人もいました。私がドイツに来るほんの少し前に、西側の自由を求めて命を落とした人がいる事実がショックだったのです。
平和な日本でずっと生まれ育った私には、イデオロギーの違いから国家が分断され、人の生命も容赦なく断ってしまう政治体制が、現存していることが許し難かった。
この時改めて、日本の隣りの朝鮮半島にもうひとつの分断国家がある事を思い出し、今までの自分の無知と無関心を恥じました。
この1987年の犠牲者は、あと一年我慢すれば、壁が開放されて往来ができるようになる事など、夢にも思わなかったでしょう。
何のために、この人は命を落としたのだろう。西側には一体何があると言うのだろうか。
ドイツ語を話し、ドイツ文化をもつ東独市民が、ベルリンの壁を数メートル乗り越えて西ドイツに入国するために射殺された。その墓標の前に立つ私は、はるか極東の孤島日本から、飛行機を使って、何の問題も無く、同じ目的地、西ドイツに入国した。
この犠牲者の数奇な運命を思い、私は黙とうをささげました。
ドイツが統一され、旧東独の元首ホーネッカー元議長に対する、裁判が行われました。容疑は、国境での亡命者に対しての射殺命令を定めた張本人として、etc...
この裁判の結果に、私は興味を持っていましたが、被告の高齢、健康状態の悪化により裁判は打ち切り。
この報道を聞いて、私もプッツン切れました。罪の無い国民を平気で射殺する命令を出し、国家公安警察を使って市民を監視し、造反者を処刑した張本人に、年齢や健康状態で裁判を中止するような、酌量の余地があるのか?法の裁きもきちんと行わずに済ます事が、ドイツ人の世界で通用するのか?
ベルリンの壁を、越えられずに、犬死にしたあの、墓標の犠牲者の命の重みは無視されるのか?
しかし、年月が経てば、忘れてしまうもんです。私も忘れていました。でももう一度、最近腹が立っておもいだしたのです。
NATOの東方拡大をめぐる首脳会議で、ロシアのエリツィン大統領も参加し、「ミサイルの弾頭照準から、NATO西欧諸国を外す」と宣言して、ワルシャワ条約機構の終結後、はっきりと、ロシアが西側を敵国とみなさないという初の確認でした。
たまたま、私はこのニュースを出張先のモスクワで聞きました。
夕方、クレムリンの前の「赤の広場」を一人で散歩しながらレーニン廟を眺め、冷戦が完全に終わりを告げたが、レーニン以来の共産主義の実験で、イデオロギーの犠牲になって死んだ人が一体どれだけいるのだろうか?と考えていました。
そして、この時また、あのベルリンで見た犠牲者の墓標を思い出したのでした。
ホテルに戻って、CNNのニュースを見ていたら、NATO会議以外に、もうひとつ政治関係の国際ニュースがありました。
「旧東独の国家公安警察スパイ組織の大ボス、Wolf被告Duesseldorf裁判所で判決」
結果は、確か無罪か、執行猶予つき判決だった。とにかく、実刑なし。判決の条件として、ベルリンの福祉団体に、いくらかの寄付を命ず、というような内容でした。
無辜の市民を殺戮した、総責任者に対する判決として、被告弁護側の「当時の東独という国家体制の中で、やむなくおこなった過失であった、統一後のドイツで裁く問題ではない」という主張が通ったようでした。
こんな事が許されていいのだろうか?悪事を働けばかならず、ツケが回ってくるべきだ。
と、私は文句を言える何の権限も無い。しかし、何かおかしい、すっきりしない感情を持ったもんです。その怒りのやり場がなく、このエッセイに形をかえた次第です。
最後まで読んでくださった方、ありがとうございます。
June.26.97
©1997 copyright Hiroyuki Asakura