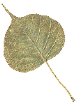1996/05/17  虎跳峡は中国雲南省北部に位置し、ヒマラヤ山脈の東辺を為す玉龍山脈(5,596m)と哈巴山脈(5、396m)に挟まれた全長約40Kmの峡谷を言う。間を縫うように金沙江(長江源流の一つ)が濁流となって流れており、途中、虎が跳んで渡ったという伝説のある地点が三ヶ所あり、ゆえにこの名がある。
虎跳峡は中国雲南省北部に位置し、ヒマラヤ山脈の東辺を為す玉龍山脈(5,596m)と哈巴山脈(5、396m)に挟まれた全長約40Kmの峡谷を言う。間を縫うように金沙江(長江源流の一つ)が濁流となって流れており、途中、虎が跳んで渡ったという伝説のある地点が三ヶ所あり、ゆえにこの名がある。橋頭(Qiao Tou)から大具(Da Ju)までのうち、絶壁の高さはもっとも高いところで3,700m、両岸は最も狭いところで30mを切っており、わかりやすく言えば富士山を縦にすっぱりふたつに割ったところに河が流れていていて、両脇の絶壁を見上げながら歩くようなもの。こんなんで説明になってるか??? さて、私は前回の91年夏に行けずじまいであった虎跳峡に、今回ぜひとも行きたくてたまらなかった。かつて公安の許可をとってCITSでジープをチャーターしても、その途中までしか行けなかった虎跳峡が、外国人に開放されたと聞いていたからだ。しかし相棒は鈍くさい私には無理だという意見と、二人だけでは危険だという判断から、あまり乗り気ではないのであった。 ところが、本日昼に入ったレストランで、スイス人旅行者によって95年2月に作成された地図が壁にはられているのを発見、またレストランに置いてあった旅行者の感想ノートから、虎跳峡は現在すでに麗江への外国人旅行者にとっては非常にポピュラーなルートであることが判明した。 ノートによれば、全長40kmの橋頭−大具間には、ほぼ真ん中に核桃園(通称Walnuts grove)という集落があり、宿泊可能とのこと。また虎跳峡を通貨する外国人は、シーズン中には一日多いときで20人を越えるらしい。同時に、悪天候時には地滑り、落石が非常に危険であること、また強盗による死亡者が複数出ていることもわかった。 昼すぎ、宿の廊下で水と食料品を抱えたイギリス人の老夫婦とすれちがい、もしやと思って尋ねると思ったとおり明日の朝虎飛峡へ向かうとのこと。彼らのほかに少なくとも3人のフランス人が同じバスを予約していたということなので、1)7人いれば強盗の心配はない(これまでの被害者はすべて単独トレッカー) 2)現地納西族によれば現在は乾季で、悪天候の心配は全く無い 3)運動神経の鈍い私に歩けない道ならすぐに引き返す(重要) 以上を確認した上で、我々も明日出発することにした。 その夜、食料、ミネラルウォーター5本、懐中電灯(かなり多くの旅行者が山の中で迷っている)などを買いそろえた。 1996/05/18  翌日7時のバスで橋頭に向けて出発。こちらからのルートの方が登りが少なく、やや楽なためである。橋頭から徒歩で虎跳峡風景区に入境。しばらくは車でも入れる広い道が続く。
翌日7時のバスで橋頭に向けて出発。こちらからのルートの方が登りが少なく、やや楽なためである。橋頭から徒歩で虎跳峡風景区に入境。しばらくは車でも入れる広い道が続く。峡谷沿いに細々と連なるこの道は、車で入れる道の終点とともに突然頼りないものとなった。 (右の写真真ん中あたりの人影が我々。) 広くある歩きやすくなる部分もあるにはあるが、多くは角張った石だらけの歩きづらい道である。滝を4つ越え、岩を登り、無数にある地滑りの後を落石と転落に注意しながら歩くのは、私にとっては初めての経験だ。絶壁に細い道が危うく連なっている場所では、風が吹くたびにひやりとし、急斜面に連なる幅15センチぐらいしかない山羊道に泣きそうになることもあった。  風の強い日にこのルートをたどるのは恐らく極めて危険なのだろうと思う。下は崖で、その下は濁流だ。死体すらも上がってこないのではあるまいか。また、雨の日には絶対に歩くなと何人もの人に警告された。悪天候で虎跳峡に向かった日本人がすでにひとり行方不明になっているという。
風の強い日にこのルートをたどるのは恐らく極めて危険なのだろうと思う。下は崖で、その下は濁流だ。死体すらも上がってこないのではあるまいか。また、雨の日には絶対に歩くなと何人もの人に警告された。悪天候で虎跳峡に向かった日本人がすでにひとり行方不明になっているという。我々が出発した日は、きわめて理想的な一日だったのだろう。薄い雲が太陽の日差しを遮り、ほどよい追い風はついに一度も突風とはならなかった。核桃園までの23kmは5〜8時間ぐらいで歩くのが標準だそうで、我々は5時間で到着した。晴れた暑い日であれば、もっとかかったことだろう。熱射病で亡くなった外国人も、やはり2名ほどいるという。 同行のイギリス人老夫婦はトレッキングが夫婦共通の趣味とかで、トレッキング歴25年のベテラン。フランス人のうち一人はフレンチアルプスのふもと出身、玉龍山脈をみあげては俺はむしろあっちに登ってみたいとつぶやく本物のクライマー。彼らをペースメーカーに、必死で付いていったための6時間であった。あとふたりのフランス人は結局遅れ、2時間後に到着した。 核桃園の景色は抜群だった。対岸の絶壁は雄大にそそり立ち、一面に黒っぽく、まばらに草木が生えている。こちら側では急斜面にへばりつくようにして民家が散在し、人々はずりおちそうな小麦畑をかろうじて耕作している。 外国人にWalnuts Groveと意訳され、愛されているこの集落の名は、もちろん胡桃(中国語では核桃)の樹が多いことから名づけられた優雅な名だ。この小さな集落にも宿が2軒あり、どちらも外国人相手に繁盛している。宿の主人によれば、ここのやってくる旅行者の99%までが外国人だそうだ。 この村のほとんどの住人は、清朝末期に四川省から移民してきた人々で、日常語としては四川語を話し、普通語をうまく話せない人も多い。宿の主人は小学校に2年間いった後、12歳のときに我々が今日歩いてきた道を村の若い衆とともに橋頭へ向かい、それからは雲南省と四川省を仕事をしながら流れ歩いてきたのだという。流れ歩いたといっても別に怪しい大男というわけではなくて、小柄でひょろひょろした、笑みを絶やさないお兄さんなのだが・・・。 この村のあまりの風景のよさ、静けさ、かつゴハンのおいしさ(放し飼いの鶏を一羽しめてもらいました・・・)、なんとびっくり手作り太陽熱ホットシャワーシステム、清潔なトイレ、などなどに感動した我々、もう一泊することに決定。なまけものの私だけなら、一週間はここでぼけぼけしそうだ。ちなみにこの宿の記録はドイツ人の23泊だそうである。 さて、その夜は15人ほどの旅行者が我々の宿に泊まっていた。その中に連れのフランス人男性とはぐれたという日本人・オランダ人の女性二人連れがいて、連れのことを非常に心配していた。彼女たちは我々とは反対に、大具から入ったのだが、川を渡る前に彼とはぐれ、そのままそれっきりになってしまっているそうなのだ。夜になっても来ないということは、どこかで道に迷い、夜を過ごしているのだろう。渡し舟や大具で聞いてみることを約束した。 1996/05/19  ところで、1996年2月3日の麗江大震災には、核桃園でもかなりの揺れがあったという。夜7時ごろ、多くの旅行者がすでに到着して夕食を取っている最中に地震は起こったそうだ。これが白昼、彼らが歩いている時間帯に起こっていたら、いったいどうなっていただろうか。村にいてさえ、落石で村人が一人死亡したほか、多くの村人と二人の外国人が負傷しているのである。
ところで、1996年2月3日の麗江大震災には、核桃園でもかなりの揺れがあったという。夜7時ごろ、多くの旅行者がすでに到着して夕食を取っている最中に地震は起こったそうだ。これが白昼、彼らが歩いている時間帯に起こっていたら、いったいどうなっていただろうか。村にいてさえ、落石で村人が一人死亡したほか、多くの村人と二人の外国人が負傷しているのである。60すぎのおじいちゃんと話をすると、30年ぶりの地震に若い世代は肝をつぶしたそうな。地震の瞬間、山のあちこちでダイナマイトを仕掛けたような爆音が鳴り響き、見る間に対岸の黒い絶壁が見渡す限りの白い粉塵−衝撃で砕けた岩の破片−で覆われた。絶え間無い落石の音が尾を引く中、やがて粉塵は風に乗ってこちら側に届き、あたり一面を白い世界に変えてしまったという。 その後の数日間、村はもちろん外界から孤立した。数日後、公安と軍隊が外国人の安否を確認し、彼らを保護するために道を開きながらやってくるまでー。 宿の雑貨売り場に、なにげなくピストルが置いてあった。もちろん売り物ではない。ぞっとしながら主人に尋ねると、一人で橋頭に行くときにはこれなしでは恐くて行けないという。ヨソ者の強盗は、襲う時には外国人でも現地人でも区別なしで襲うという。なんでも、この北の方にある採石場で囚人が労働力として使われており、そこからの脱走犯が複数潜伏しているのではないかという噂だそうだ。このへんの村人は町へ出る際には何人か集まり、腰にナイフをさげて行くのが普通だとか。 1996/05/20  核桃園に2泊し、三日目の朝に日本人男性二人と連れ立って、計4人で大具へ向けて出発した。ミネラルウォーターを3本用意したが、これは後から考えると少なすぎた。
核桃園に2泊し、三日目の朝に日本人男性二人と連れ立って、計4人で大具へ向けて出発した。ミネラルウォーターを3本用意したが、これは後から考えると少なすぎた。核桃園から大具までは、最短コースをとれば17km。途中かなり大規模な地滑りの跡と、絶壁にかろうじて開かれた細道(左の写真参照)を過ぎれば、あとは危険な道を歩くこともなくなった。ところがである。 ここから先は道が何ヶ所かで分かれるため、もっとも道に迷いやすいと聞いていたところなのだが、大具への道を示す道標が何者かによって破壊され、別の道を指すように置き換えられているのだ。置き換えられた矢印は急斜面を下るよう指示していたが、我々はこれを悪質ないたずらと判断、先に進むことにした。なにしろカラカラに乾ききった炎天下であるため、余計に歩いて水分を消耗したくないのだ。また、目的地大具はもはや対岸前方に見えつつあった。 この日は不幸にも非常に天気のよい日で、大具がはっきりと見えた時点で水が3本ともなくなってしまった。深い谷を迂回したあと、道はまた二股に分かれた。左の大きな道は登り坂、右の道は右手に見える平らな土地へ緩やかに降りてゆく。そろそろ川を渡るために川辺へ降りてもいいころではないかと考えた我々は、左の道を離れて右の道へ進んだ。 しばらくゆくと、道はまた三叉に分かれた。左の小道は急な坂を垂直に登ってさっき分かれた大きな道と交わり、さらに丘を越えて行くのが見える。真ん中の道は平らな土地をまっすぐに進んでいるが、どうしたわけだか途中で大小の石が積まれ、道がふさがれている。右の道は急斜面をまっすぐに川辺へ降りてゆくようだ。ここで川を渡るのだろうか? 左手の丘に羊の放牧にやってきた女性に尋ねると、右の斜面を降りろ降りろという。丘の上と下で、大声でやりとりしていると、少年がやってきて自分のおじさんがこの下にボートを持っていると言い出した。我々は、ここはどうやら本来の渡し場ではない、おそらく道標に細工をしたり、道を石でふさいだりしたのはこの下にボートを持っているその連中だと見当をつけたが、しかし渡れるようなら渡ってもよいのではないかと迷い、しばらく立ちすくんでしまった。 そうこうしているうちに、我々に先行していたアメリカ人のカップルが、左の丘を越えて戻ってきた。行き止まりだったらしい。私が「この下にボートがあると言ってるけど」と少年を指すと、「写真で見た本来の渡し場はここではないようだから、進むことにする」と一番左の大きな道を進んでいった。 我々はどうする?と、休みがてら相談していると、2時間早く出発したはずのイギリス人4人が真ん中の道から引き返してくるのが見えた。するとアメリカ人カップルの行った左の大きな道が本来の道なのだろうが、みるからにきつい登り坂で、また対岸の大具から次第に離れてゆくようでもある。イギリス人も含め、私たちはここで川をわたることに決定した。(下の写真では対岸に大具が見えている)  急斜面をずりおちるように下ること30分。川面に手漕ぎボートが見えた。かなり大きなボートだが、二人の漕ぎ手以外は3人までしか乗れないという。大勢乗せると対岸につける前に流されてしまうのだそうだ。確かに大変な急流で、川の中ほどでは川底から吹き上げるように沸く水で、川面が盛り上がっている。
急斜面をずりおちるように下ること30分。川面に手漕ぎボートが見えた。かなり大きなボートだが、二人の漕ぎ手以外は3人までしか乗れないという。大勢乗せると対岸につける前に流されてしまうのだそうだ。確かに大変な急流で、川の中ほどでは川底から吹き上げるように沸く水で、川面が盛り上がっている。我々の乗ったボートは、川の中央に出るなり見る見る下流へ流された。流されつつもなんとか対岸へつけ、流れのゆるやかな所を選んで、えっちらおっちら上流へ船を進め、ボートの出発点のちょうど対岸で停泊した。 ちなみに料金は外国人15元、中国人5元。本来の渡し場ではそれぞれ10元、3元である。 3人ずつ渡してもらって、船は何度か往復。ここから大具まではさっき降りたのよりさらにきつい急斜面をよじのぼることとなった。大規模な地滑りのあとを、道を選んで横断したとき、子どもの背中ほどの岩に何気なく足をかけた瞬間、岩が砕けて私は横転した。この時山側ではなく谷側に倒れていたらどうなっていたか、今考えてもとゾッとする。幸い足もひねることなく、右手のひらを2個所切ったことと、右ひじ、右腰を強打したことだけで事は済んだ。この地すべりは2月の地震の際にできたものだとあとで聞いた。  地滑りを無事横断し、峡谷をひとつ迂回して一時間ほどきつい勾配をあがると、チーズケーキのように見事に平らな盆地に出た。小麦の収穫が終わったところらしい。一面の切り株の向こうに、納西族の集落、大具が見える。我々は全員、「ビールビールビール・・・」とつぶやきながら(叫ぶ元気がもうない)、小麦畑を突っ切ってまっすぐ歩き出した。
地滑りを無事横断し、峡谷をひとつ迂回して一時間ほどきつい勾配をあがると、チーズケーキのように見事に平らな盆地に出た。小麦の収穫が終わったところらしい。一面の切り株の向こうに、納西族の集落、大具が見える。我々は全員、「ビールビールビール・・・」とつぶやきながら(叫ぶ元気がもうない)、小麦畑を突っ切ってまっすぐ歩き出した。こうして、虎跳峡全40km走破という、怠け者の私にとって画期的な体験は無事終わったのであった。 (玉龍山(5,596m)のふもとの村、大具。村を覆う影は対岸の哈巴山(5、396m)のもの。) 追記。 左の大きな道を上がっていったアメリカ人カップルは一時間ほどあとに大具に到着。やはり彼らのたどった道が本来の道だったらしい。歩きやすい道だが、やや遠回りになるようだ。我々が取った道は、最短距離ではあるらしいが、斜面や地滑りが多く危険な道である。このカップルは大具付近の地図を作成し、麗江でホテルやレストランに配布していた。良心的な人々だ。私は外国人があつまるカフェのノートに注意事項を書き付けてきた。 追記2。 例のはぐれたフランス人男性とは、麗江のホテルで会った。彼は川を渡るなり道を間違え、山の中で3夜を過ごしたしたのだという。最初の2晩は岩のかげややぶの中で、三日目の夕方に村をみつけ、そこで始めて水と食料と寝場所を得、村人の案内で大具まで引き返したという。もういちど虎跳峡へ行く気ある?と尋ねたら、「Non! 今ボクに必要なのは休息だけ。」と答えた。鼻の頭が気の毒なぐらい日焼けしていた。 |