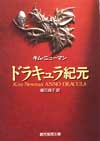2002/5/4
S○NY爆弾にやられていたVAI○が修理から戻ってきた。(説明しよう。S○NY製品の中には保証期間を過ぎると爆発する正確な時限爆弾が入っているのである。S○NY製品は壊れやすいのではなく、科学の粋を集めた装置なのだ)
んじゃ、ネットにでも繋ぐか、と、無料系プロバイダにかけるが全然繋がらない。VAIOに元々入っていたAOLにサインアップしようとしても繋がらない。IIJ4Uも繋がらない。SO−NETも繋がらない。みんな繋がらない。GWということで、全日本人がネットをやってるのか?
ニュースで見た海外流出する人達や、高速道路のちょー蛇……もとい、長蛇の車の列はマスコミのウソか?
最後にDreamNetが繋がって、思わずカードでオンラインサインアップしてしまった。数年前のネットワーカーのように繋がりやすさのみでプロバイダを選んだ私であーる。
『ゴースト・ドラム−北の魔法の物語−』(スーザン・プライス/ベネッセコーポレーション) 読了。
これはすごい。87年度のカーネギー賞受賞作だそうだが、そんな肩書きはなくても読んだだけですごさがわかる。(カーネギー賞はイギリス児童文学のアカデミー賞らしい)
100%の純正ファンタジー。甘くもなければ、勧善懲悪でもハッピーエンドでもない。ただ溢れるばかりの詩情とイマジネーション。こんな作品が児童文学として出版されるあたり、イギリスってすごい国だ。
しかし、日本では、この名作も絶版。これは日本人がファンタジー後進国なせい……ばかりでもなく、出版形態が悪いような気がする。子供の本として出版するには、あまりに内容が教育的でないもんな。どこか出版形態を変えて再発してくれないかなあ。
とりあえず見本に、ワンシーンなどメモっておきましょう。主人公の魔法使いチンギスが、先代の魔女から魔法を学ぶシーン。
「文字というのも、よくある魔法のひとつだよ」老婆がいった。「これを学ぶにはまず、文字の読み方をおぼえて、こういった印が本からなにをかたりかけているのかが、わかるようにならくっちゃいけない。これが文字の魔法の簡単なやつなんだが、あなどっちゃいけない! とても強い力を持っているんだからね。いいかいチンギス、この本が読めるようになると二千年もまえに死んだ魔法使いが、そこからおまえにかたりかけてくるようになるだろう。魔法のことをあまり知らないものたちでさえ毎日、本を開いて死者の言葉に耳をかたむける。そうして死者から教えてもらうううちに、死んだ者たちがいとおしくなってきて、まるで生きているかのように思えてくる。それは強い魔法なんだよ」
 タイトルリスト
タイトルリスト
 作家別リスト
作家別リスト