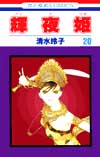2002/10/7
出発待ちの時間に読もうかと思ったら、案外アッサリ乗れてしまったので行きの飛行機の中で読んだ『輝夜姫(20巻)』(清水玲子/白泉社)。
読んでいる時には気がつかなかったが、もう20巻か。前の連載が13巻くらいだったので、それくらいの時点で1巻から一気読みした。(だって、ちんたら読んでるのたるいじゃーん) こんなに長くなるとは思わなかったよ。それから結局1巻ごとに読んでいるので、13巻まで貯めておこうと一緒じゃん(笑)。
ストーリー紹介は白泉社のHPからもらっちゃおう。
時は21世紀、日本の孤島・神淵島(かぶちじま)で育てられた少年達が、再び島へ集められた。それは、彼らがたどる激動の運命のプロローグだった…! 衝撃のSFロマン。
うーん、これだけじゃ何がなんだかですね(笑)。
神淵島は天女伝説の残る島。タイトルの『輝夜姫』は「かぐやひめ」と読み、この日本人なら誰でも知っている昔話が物語りのベースになっている。
でも、一筋縄ではいかないのが清水玲子の描く世界。
神淵島に集められた少年・少女は世界の要人のクローンで、交換部品として生を受けたものだった。神淵島の天女伝説の真実とは何なのか。月の石とは一体何なのか。
思うに、繊細で美しい絵柄で、どろどろと醜い人間の姿を描くのが著者の真骨頂だろう。この巻でも、愛情の渦巻き具合がものすごい。
私がやられた、と、思ったのが17巻。
ロシアに拘束された守に面会に行く主人公・晶(あきら)。晶は輝夜姫の生まれ変わり、という設定で、神淵島に育った少年のほとんどは晶に恋しているわけですね。
クローンとしての意識が暴走して、晶の目の前で人を殺した守が叫ぶ。
「いつまでもこんな汚いところにいるな、早く行け!」。
これはそのまま晶が過去に(意識のないうちに)犯した殺人の風景とだぶる。
「行け」
(行かないで)
「いつまでもこんな汚いところにいるな」
(血で汚れても、変わってしまっても)
「早く行け!」
(それでも好きだといって)
理解されて愛されたいと思う、ものぐるしい激しい思い。
こんなに重いドラマティックなシチュエーションにいない普通の人間でも、誰もがかかえる思い。やたらハッピーエンドが好きな私が、決して読後感がいいとは言えないこの作品を読むのも、毎回、そんな思いに動かされるからだろう。
たぶん、誰もが愛されて許されることを望んでいる。
そして、本当に理解されることはとても少ない。
だからこそ、私はハッピーエンドを受け取り手に送り出したいと思ったりするのだ。
 タイトルリスト
タイトルリスト
 作家別リスト
作家別リスト


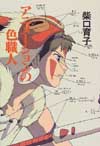
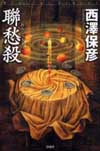


 近所で「野口久光・ヨーロッパ名画座展」をやっていた。
近所で「野口久光・ヨーロッパ名画座展」をやっていた。